小規模事業者持続化補助金の申請は、採択率82%超のコンサルタントに相談を

数ある補助金の中でも、日本全国で大人気となっている小規模事業者持続化補助金。
多くの事業者が活用できる制度となっており、「もらわなきゃ損」である一方、申請にはいろいろなハードルがあるのも事実です。
もし以下のような点にお悩みがあれば、ぜひ補助金のプロフェッショナルにお任せください。
- 申請のためにかける時間が無い
- 事業計画書の作成方法がわからない
- ルールが細かすぎて正確に把握できない
- 採択率を上げる方法がわからない
- 相談できる相手がいない
- 獲得後に計画どおり実行できるか不安
- 自社に合う補助金がないか教えてほしい
目次
- 1 補助金を知り尽くすプロ集団がサポートします
- 2 小規模事業者持続化補助金の申請サポート内容
- 3 小規模事業者持続化補助金の支援事例
- 4 【2025年12月最新速報】小規模事業者持続化補助金の次回スケジュールは?
- 5 小規模事業者持続化補助金の採択率の推移
- 6 小規模事業者持続化補助金の目的
- 7 小規模事業者持続化補助金で対象となる経費
- 8 小規模事業者持続化補助金の活用例
- 9 小規模事業者持続化補助金の申請枠の種類
- 10 申請に必要なものと提出書類
- 11 申請内容で評価されるポイント
- 12 小規模事業者持続化補助金の加点・減点要素
- 13 小規模事業者持続化補助金の申請の流れ
- 14 小規模事業者持続化補助金の採択後に必要なこと
- 15 その他のいろいろな注意点
- 16 その他のいろいろな注意点
- 17 よくある質問
- 18 無料相談&お問い合わせ
補助金を知り尽くすプロ集団がサポートします

当オフィスが連携している補助金のプロフェッショナル集団は、現在までに300以上の支援実績があり、採択率82%以上を誇る精鋭部隊。
2025年の小規模事業者持続化補助金をサポートした事業者様に至っては、採択率100%というパーフェクトな実績を誇っています。
補助金は申請すれば必ずもらえるわけではなく、大量の申請事業者の中から「採択」されなければなりません。
そして「採択」されるかどうかは、事業計画書の出来にかかっています。
小規模事業者持続化補助金の採択率は、以前は60%前後で推移していたものの、近年はその水準がかなり低下してきており、直近では40~50%前後と、確実に難易度が上がってきています。
そんな状況とはいえ、あきらめる前にぜひ一度私たちの申請サポートをご検討ください。
以下では補助金申請を強力にバックアップする私たちのサービス内容に加えて、小規模事業者持続化補助金の基礎知識についても網羅的にご紹介していきます。
小規模事業者持続化補助金の申請サポート内容

私たちは中小企業専門の経営相談所として、様々な分野のプロフェッショナルと連携し、経営に関する幅広いお悩み解決をご提供しています。
各種補助金・助成金の申請サポートでは、事業者様の予算やご要望に応じて、例えば以下のようなご相談を承っております。
- 事業計画書の作成を手伝ってほしい
- 採択率を高めるためのアドバイスがほしい
- 申請後の実績報告をサポートしてほしい
- 新規事業の舵取りを任せたい
- その他に使える補助金制度が知りたい
- 補助金以外の経営課題も相談したい
計画策定に慣れていない事業者様には、中小企業診断士や行政書士による手厚いサポートにより、ルール違反にならない範囲で可能な限りお手伝いさせていただきます。
料金体系
料金体系については、主に以下の2つに分かれています。
- 計画書作成サポート
- 伴走支援サポート
サポート内容、申請金額、着手金の有無など、内容によってどうしても変動する部分があります。着手する前に十分なご説明を差し上げ、明確にした上で実行に移ることをお約束します。
計画書作成サポートの場合
計画書作成サポートの料金は、主に「着手金」と「成功報酬」に分かれています。
申請に関連するアドバイスや、採択後の手続き、実績報告といった内容もセットとして含まれており、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。
「成功報酬」を中心の料金体系にすれば、万が一採択されなかった場合でも、事業者様にとって損するリスクはかなり小さくなります。
伴走支援サポートの場合
伴走支援サポートでは、計画書の内容に関するフィードバックやアドバイスに加えて、申請する事業の「実行」をお手伝いします。
ご要望であれば、経営のその他のお悩み解決も承ります。
実際にサポートを開始する前に、まずは無料相談にて詳細をご説明しますので、ぜひ実際に話を聞いてみてください。
小規模事業者持続化補助金の支援事例

実際の補助金サポート事例についてご紹介します。
A社の事例(中古車販売業)
この事業者様の課題は、地域での自社の存在があまり知られていないため、認知度を向上させることでした。
そこで小規模事業者持続化補助金を活用し、集客力の強化に取り組むことに。
計画書には当社をとりまく現状を詳細に書き込んだ他、競合他社と比較した強みを最大限に表現し、補助金を活用する有効性を審査者にアピールします。
結果として200万円の補助金獲得に成功し、幹線道路沿いに目立つ看板を設置できた他、チラシをはじめ充実した集客施策をスタートすることができました。
B社の事例(菓子製造小売業)
地元で昔から評判の、小さなお菓子屋さんの事例です。
地域の町おこしにも精力的であった当社では、地元産の材料を用いたオリジナルのお菓子を開発し、品評会でも大変な好評を得ていました。
しかしながら製法が特殊ということもあり、従来の生産体制では生産量が限られることで、安定供給を図るのが難しいという課題に直面。
そこで小規模事業者持続化補助金の申請をサポートし、当社の製品や取り組みの素晴らしさを計画書に盛り込んだ結果、見事に採択を勝ち取ることに成功します。
補助金を使って購入した高額な機械により、商品の生産効率が大幅にアップし、売上の大幅な向上を実現しました。
C社の事例(飲食サービス業)
コロナ禍で大きな打撃を受けていた、地方の飲食店様の事例です。
地元産の食材を使った料理のクオリティは素晴らしく、コストパフォーマンスも高いお店として評判でした。
しかしながら少人数で運営していることもあり、予約の電話などに手が回らない他、情報発信の面は決して十分とは言えませんでした。
そこで小規模事業者持続化補助金の申請を提案し、お忙しい中で徹底的にサポートさせていただいた結果、無事に採択を勝ち取ることに成功。
WEB予約が可能なホームページを新設しただけでなく、ショーケースの導入まで同時に実現し、お店の魅力を存分にアピールできるようになりました。
【2025年12月最新速報】小規模事業者持続化補助金の次回スケジュールは?

第18回公募における主要なスケジュールは以下の通りです。
締め切りに関しての注意点
第18回の申請は締切となりました。
次回の申請スタートは、2026年の5~6月頃が予定されていますが、詳細については決定していません。
まだまだ先のように思えますが、事業計画はアップデートしておくのに越したことはなく、今から申請の準備を始めたとしても、決して早すぎるということはないと思います。
いざ申請が始まると、あっという間に締切日がやってきます。
申請書類の中でも、商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」は見落としがちなので注意しましょう。
今までのパターンからすると、公表されている締切日よりも1週間以上前に「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があり、これが事実上の締切日となっています。
公募要領では「いかなる理由があっても」締切後の依頼は受け付けられないと明記されており、商工会・商工会議所への依頼も単なる手続きではなく、実質的な審査プロセスの一部であるとも捉えられます。
したがって事業計画の全体像を早いうちから固めつつ、商工会・商工会議所への相談も済ませておきましょう。
とにかく公式の申請締切日よりも、実質的な準備のデッドラインがあるため、早めに着手することに越したことはないと覚えておいてください。
災害支援枠
2025年10月28日、災害支援枠の第9次公募要領が公開されました。
申請受付開始は令和8年1月23日(金)の予定となっています。こちらは令和6年の能登半島地震等で、直接的な被害を受けた事業者様のみが対象なのでご注意ください。
今後についての注意点
次回の第19回公募は、よほどのことが無い限り実施されるとは思われます。
しかし期間に大幅なズレが発生したり、今までと異なる条件が追加されるなど、ルールに大きな変更の可能性がある点にも留意が必要です。

小規模事業者持続化補助金の採択率の推移

直近の採択率の推移を見ると、難易度が上がっていることが一目瞭然です。
小規模事業者持続化補助金の目的

ここからは小規模事業者持続化補助金という制度について解説していきます。
どのような補助金でも共通する前提として、「その補助金がどのような目的で設計された制度なのか」を知ることが重要です。
当たり前のようですが、意外とこの視点が抜けてしまう事業者様も多く、見当違いの申請内容を作成してしまわないように注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が直面する経営環境の変化に対応し、持続的な発展を遂げることを支援するために設計されています。
その目的は単なる資金提供に留まらず、事業者の経営計画策定能力の向上と、国が推進する経済政策への適応を促すことにあります。
制度の根幹をなすのは、小規模事業者が自ら策定した「経営計画」に基づいて行う販路開拓や業務効率化(生産性向上)の取組を支援すること。
支援の結果として、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の、生産性向上と持続的発展を図ることを目指しています。
事業者自身が主体的に計画を策定することが厳しく求められており、もし事業者自らが検討していなかったことが発覚すれば、その際は評価以前に不採択となってしまう可能性が警告されています。
政策的背景
公募要領では、事業者が直面する制度変更として「物価高騰」「賃上げ」「インボイス制度の導入」が具体的に挙げられています。
これは、本補助金がこれらのマクロ経済的な変化や政府の政策導入に対して、小規模事業者が円滑に対応するための支援策という側面を強く持っていることを示しています。
つまり補助金の活用は、これらの外部環境の変化を乗り越え、事業を成長させるための戦略的投資として位置づけられています。
この制度設計から読み取れるのは、政府が補助金というインセンティブを通じて、小規模事業者層の経営体質強化を図ろうとする意図です。
申請にあたっては、単に「新しい機械が欲しい」「広告を出したい」といった短期的な要望を述べるだけでは足りません。
例えば「インボイス制度導入による対応するため」「環境変化による新たな顧客層を開拓する必要があるため」などのように、自社の経営計画が国の政策や経済環境の変化にどう対応するものなのかを明確に示すことが、採択の可能性を高める上で重要となります。
小規模事業者持続化補助金で対象となる経費

補助対象となる経費は、策定した経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組に必要なものに限定され、8つの経費区分が定められています。
すべての経費は、①事業遂行に必要不可欠であること、②交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了すること、③証拠書類によって支払金額が確認できること、という3つの条件を完全に満たす必要があります。
以下に、8つの経費区分ごとに、対象となる経費の例と対象とならない経費の例を詳述します。これらの区分を正確に理解し、適切な経費計上を行うことが、補助事業の円滑な実施と実績報告の承認に不可欠です。
経費規定の根底にあるのは、「日常的な事業運営経費」と「新たな販路開拓や生産性向上のための投資」を厳格に区別するという思想です。
例えば汎用性の高いパソコンや、既存設備の単なる更新が対象外とされるのは、それらが事業維持のためのコストであり、新たな価値創出への直接的な投資とは見なされないためです。
申請者は計上するすべての経費について、どのように経営計画に掲げた「新たな取り組み」に直結するのかを、具体的かつ論理的に説明しなければいけません。

小規模事業者持続化補助金の活用例

本補助金は、多様な業種や事業内容に合わせて柔軟に活用することが可能です。
公式資料では、販路開拓と業務効率化のそれぞれについて、具体的な活用事例が示されています。
販路開拓のための取組事例
販路開拓は、新たな顧客層の獲得や、新市場への進出を目指す活動全般を指します。
物理的な改善からマーケティング活動まで、幅広い取り組みが対象となっており、特にWEB関連の施策についても使えるという点では貴重な補助金となっています。
物理的な店舗・設備の改善
- 新商品を陳列するための棚の購入: 新商品の魅力を効果的に伝え、顧客の購買意欲を高める。
- 店舗改装: 小売店の陳列レイアウト改良や、飲食店の内装改修により、新たな顧客層(例:ファミリー層、高齢者層)を呼び込む。
マーケティング・広報活動
- 新たな販促用チラシの作成、送付、ポスティング: 新商品や新サービスを地域住民や特定のターゲット層に直接告知する。
- 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加: 企業間取引(BtoB)の販路を開拓したり、海外市場への足がかりを築く。
- 国内外での商品PRイベントの実施: 顧客との直接的な接点を設け、商品の魅力を体験してもらうことでファンを獲得する。
新商品・新サービスの開発
- 新商品の開発: 既存の技術やノウハウを活かし、新たな市場ニーズに応える商品を開発する。
- 新商品開発に伴う成分分析の依頼: 商品の品質や安全性を客観的に証明し、信頼性を高めることで販路拡大に繋げる。
業務効率化(生産性向上)のための取組事例
販路開拓の取組とあわせて行う業務効率化の取組も補助対象となります。
これにより、バックオフィス業務を効率化し、経営者や従業員がより付加価値の高い販路開拓活動に集中できる環境を整えることができます。
ただし業務効率化の取組のみでの申請は認められないという点には注意が必要です。
サービス提供等プロセスの改善
- 従業員の作業導線の確保や整理スペース導入のための店舗改装: 作業効率を高め、生産性を向上させる。
IT利活用
- 倉庫管理システムの導入: 在庫管理と配送業務を効率化し、時間とコストを削減する。
- 労務管理システムの導入: 人事・給与管理業務を自動化し、管理部門の負担を軽減する。
- POSレジソフトウェアの導入: 売上データをリアルタイムで分析し、より効果的な販売戦略の立案に役立てる。
- 経理・会計ソフトウェアの導入: 決算業務を効率化し、正確な経営状況の把握を支援する。
これらの事例は、補助金の活用方法が単一ではないことを示しています。
自社の課題がどこにあり、それを解決するためにどのような投資が最も効果的かを経営計画の中で明確にし、それに合致した活用法を組み立てることが重要です。
小規模事業者持続化補助金の申請枠の種類

この補助金にはいくつかの種類があるのですが、ここでは申請の中心となる「一般型・通常枠」と「創業型」の2つについて解説します。
その他の「型」は、申請条件が一部に限られるためここでは触れませんが、気になる方は公式ページを見てみてください。
「一般型・通常枠」について
この補助金で最も多く申請されているのが「一般型・通常枠」です。
ややこしいのですが、「通常枠」の中にさらに「特例」が設けられ、国の政策的要請に応える事業者を手厚く支援する建てつけとなっています。
このような「特例」の他、一部条件によって補助上限額や補助率が変動するため、自社の状況に最も適したものを選択することが重要です。
以下のように表にまとめると理解しやすくなります。
「一般型・通常枠」の特例に関する注意点
特例を利用して申請する場合、極めて重要な注意点があります。
それはもし補助事業終了時点で特例の要件を一つでも満たせなかった場合、特例による上乗せ部分だけでなく、補助金全体が交付対象外となるという「オール・オア・ナッシング」のルールです。
例えば「賃金引上げ特例」で申請し、販路開拓の取り組みは成功したものの、約束した賃上げが達成できなかった場合、補助金は1円も交付されません。
この厳しい条件は、特例が国の重要政策(インボイス制度への移行促進、賃上げ促進)と直結していることの表れです。
特例の活用は、補助額を大幅に増やす機会であると同時に、達成できなかった場合のリスクも非常に大きいことを意味します。
したがって、特例を申請する事業者は、その要件達成を事業計画の最重要目標の一つとして位置づけ、確実な実行計画を立てる必要があります。
「創業型」について
小規模事業者の中でも、創業初期の事業者を重点的に支援するための制度で、概要としては以下のようなものになります。
- 対象者: 創業後3年以内の小規模事業者
- 補助上限額: 最大200万円(特例適用時は最大250万円)
- 補助率: 2/3
補助上限額は魅力的ですが、一般型と比べて狭き門となっており、採択率は低い傾向にあります。
例えば第17回公募では、一般型の採択率が51.1%だったのに対し、創業型は37.9%でした。
これには創業間もない事業であるため、計画が楽観的であったり、実現可能性が低いと判断されたりするケースが多いのも一因かもしれません。
「創業型」特有の申請要件
創業型には、一般型にはない特有の申請要件がいくつかあります。
中でも特徴的なのが「特定創業支援等事業」の受講で、これをクリアしないと申請自体が認められません。
申請する前の段階で、所在地の市区町村などが実施する「特定創業支援等事業」を受講し、その証明書を取得している必要があります。
これには一定の期間を要するため、事前の計画的な準備が不可欠となります。
また創業型という名称ではあるものの、「これから開業する」という段階では対象外です。申請時点で開業届を提出しているだけでなく、実際に事業活動を開始し、売上が発生している実態が求められます。
これを証明するため、決算期を一度も迎えていない場合は「売上台帳」の提出が必須となります。
さらに採択が決定した後の手続きにおいても、「一般型・通常枠」よりも厳格なルールが存在します。
申請に必要なものと提出書類
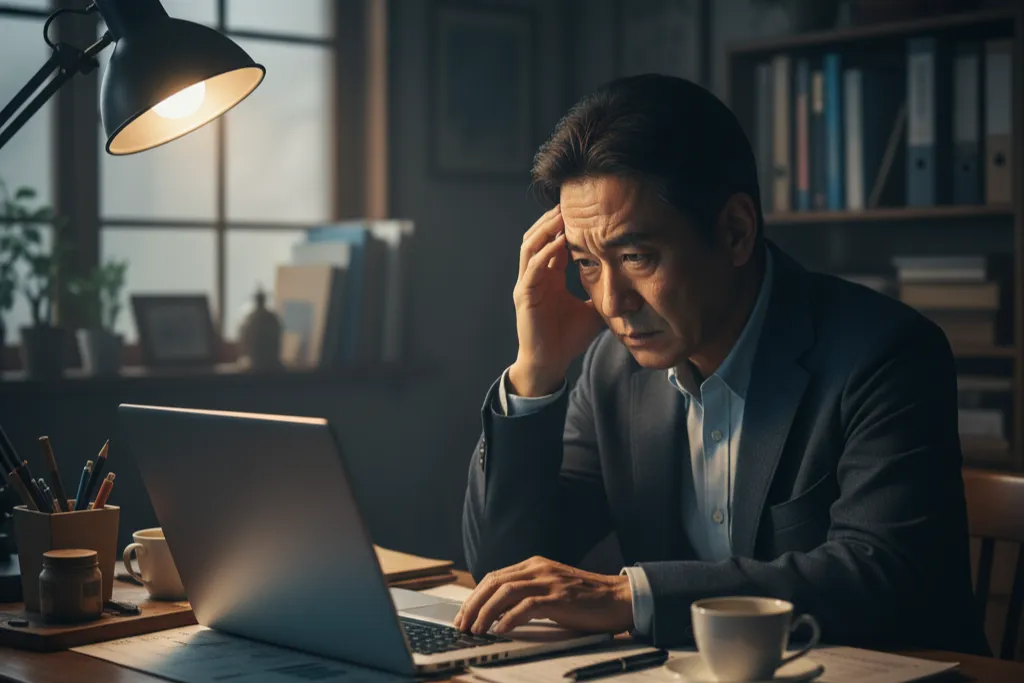
申請は完全に電子申請システムで行われ、郵送での申請は一切受け付けられません。
申請にあたっては、事業者自身の情報、経営計画、そして事業形態や希望する特例・加点に応じた各種証明書類を漏れなく準備する必要があります。
全ての申請者に必須のもの
GビズIDプライムのアカウント
電子申請システムの利用には、GビズIDプライムのアカウントが必須です。取得には数週間を要する場合があるため、未取得の事業者は速やかに利用登録を行う必要があります。
システムへの直接入力情報
- 持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
- 経営計画兼補助事業計画①(様式2)
- 補助事業計画②(様式3)
- 補助金交付申請書(様式5)
- 宣誓・同意書(様式6)
システムへのアップロード書類
- 事業支援計画書(様式4): 地域の商工会・商工会議所が発行。発行依頼には面談が必要な場合があり、十分な余裕をもって依頼する必要があります。
事業形態別に必要な提出書類
特例・加点を希望する場合に追加で必要な書類
希望する特例や加点に応じて、以下の追加書類が必要となります。
書類の不備は、審査の対象外となる致命的なミスとなります。公募要領の指定するファイル名規則に従い、全ての書類を正確に準備することが強く求められます。
申請内容で評価されるポイント

採択審査は、形式的な要件を確認する「基礎審査」と、計画内容を評価する「計画審査」の二段階で行われます。評価の高いものから順に採択されるため、計画の質が直接的に採否を決定します。
基礎審査
これは、申請が審査の土台に乗るための最低条件を確認するプロセスです。以下の要件を一つでも満たさない場合、その時点で失格(不採択)となります。
- 必要な提出資料がすべて提出されていること。
- 補助対象者、補助対象事業、補助率・上限額、補助対象経費の各要件に合致していること。
- 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること。
- 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること。
計画書の審査
基礎審査を通過した提案は、経営計画および補助事業計画の内容について、以下の4つの観点から加点方式で評価されます。
自社の経営状況分析の妥当性
- 自社の経営状況を客観的に把握しているか。
- 自社の製品・サービス、強み・弱みを適切に理解し、分析できているか。
経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 上記1の分析結果(強み・弱み)を踏まえた経営方針・目標になっているか。
- ターゲットとする市場(商圏)や顧客のニーズを的確に捉えたプランか。
補助事業計画の有効性
- 計画が具体的で、実現可能性が高いか。
- 策定した経営方針・目標を達成するために、必要かつ有効な取り組みか。
- 独自の技術やアイデアに基づき、顧客にとって新たな価値を生み出す取り組みが含まれているか。
- デジタル技術を有効に活用する取り組みが見られるか。
積算の透明・適切性
- 事業費の積算が正確・明確で、事業実施に真に必要な金額が計上されているか。
- 補助事業計画に合致した、費用対効果の高い経費計画となっているか。
これらの評価項目は、「現状分析」→「戦略・目標設定」→「具体的行動計画」→「予算計画」という、論理的で一貫性のある事業計画の策定プロセスそのものを評価していると言えます。
したがって、優れたアイデアを持つだけでなく、そのアイデアがなぜ自社にとって今必要なのかを、客観的な自己分析と市場分析に基づいて説得力をもって説明できるかどうかが審査の鍵となります。
特に「デジタル技術の有効活用」が評価項目として明記されている点は、国が中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したいという明確な意図の表れであり、計画にデジタル要素を盛り込むことは有効な戦略です。

小規模事業者持続化補助金の加点・減点要素

計画審査の評価に加え、国の政策的観点から特定の要件を満たす事業者を優先的に採択するための「加点制度」と、補助金の公平な配分を目的とした「減点調整」が存在します。
これらを戦略的に活用・理解することが、採択の可能性を大きく左右します。
加点審査
加点は【重点政策加点】と【政策加点】の2つのグループに分かれています。
注意しなければならないのが、それぞれのグループから1種類ずつ、合計2種類まで選択できるという点であり、2種類以上は加点対象外となってしまいます。
加点項目は、政府が現在重視している政策課題(賃上げ、事業承継、地方創生、災害復興など)を反映しています。
申請者は事業計画を策定する前にこのリストを確認し、自社の取り組みがこれらの政策課題に合致するかを検討するべきです。
計画内容を少し調整することで加点対象となる可能性もあり、採択に向けた重要な戦略となります。
減点調整
より多くの事業者に補助金を活用してもらう観点から、過去に本補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠など)で採択された事業者については、採択回数に応じて段階的に減点調整が行われます。
これは初めて申請する事業者や、過去の採択から時間が経過している事業者が相対的に有利になる仕組みです。
小規模事業者持続化補助金の申請の流れ

申請プロセスは、事業者単独で完結するものではなく、GビズIDの取得や商工会・商工会議所との連携など、複数のステップを計画的に進める必要があります。
- GビズIDプライムのアカウントを取得
- 電子申請に必須。未取得の場合、これが最初に行うべき作業です。アカウント発行には時間がかかるため、公募開始後すぐに手続きを開始することが推奨されます。
- 事業計画(様式2, 3)の策定
- 自社の現状分析、目標設定、販路開拓や業務効率化の具体的な計画、経費の見積もりなど、申請の核となる内容を作成します。
- 商工会・商工会議所へ「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼
- 策定した事業計画を持参し、所在地区の商工会・商工会議所に相談します。計画内容について助言を受け、確認・承認を得た上で、様式4を発行してもらいます。このステップには厳格な締切(2025年11月18日)が設定されています。
- 電子申請システムで申請書類を提出
- GビズIDで電子申請システムにログインし、必要事項の入力と、発行された様式4を含む全ての必要書類のPDFファイルをアップロードします。申請受付締切(2025年11月28日17:00)までに全ての操作を完了させる必要があります。
- 審査・採択
- 提出された申請内容について、事務局および外部有識者による審査が行われます。
- 採択結果の通知
- 申請者全員に対し、採択または不採択の結果が通知されます。採択案件については、事業者名や事業概要等が公表される場合があります。
小規模事業者持続化補助金の採択後に必要なこと

補助金は採択されたことがゴールではなく、ここから交付に向けたプロセスが始まります。採択後から補助金の入金までには、厳格な手続きと義務が伴います。
見積書等の提出
採択通知後、計画に計上した全ての経費について、価格の妥当性を証明する見積書等を提出します。
100万円(税込)を超える契約や、中古品(金額問わず)については、原則として2者以上からの相見積もりが必要です。
この書類提出には期限が設けられており、遅れた場合は採択が取り消されます。
交付決定後の流れ
提出された見積書等が審査され、問題がなければ事務局から「交付決定通知書」が送付されます。
補助事業(発注、契約、支払い等)は、この交付決定通知書に記載された「交付決定日」以降にしか開始できません。
交付決定日より前に行った経費支出は全て補助対象外となります。
採択発表から交付決定までには1~2ヶ月程度かかる場合があるため、事業開始時期はこの期間を見込む必要があります。
- 補助事業の実施
- 交付決定後、補助事業実施期間内に、計画に沿って事業を実施し、全ての支払いを完了させます。事業内容や経費配分を変更する場合は、事前の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
- 事業完了後、定められた期限(事業終了から30日後、または2027年3月10日のいずれか早い日)までに、事業内容と支出経費をまとめた実績報告書を、全ての証拠書類(見積書、契約書、請求書、領収書、振込記録等)と共に提出します。
- 確定検査・補助金額の確定
- 提出された実績報告書に基づき、事務局が内容を精査(確定検査)し、最終的な補助金額を確定します。書類に不備があれば修正を求められ、解消されない場合は補助金額が減額またはゼロになることがあります。
- 補助金の請求と交付(入金)
- 補助金額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出します。その後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。
- 事業効果報告書の提出
- 補助事業終了から1年後に、事業の成果や賃上げの状況等を報告する「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出が義務付けられています。これを怠ると、将来の補助金申請が制限される場合があります。
採択から入金までのプロセスは、厳密な書類管理と期限遵守が求められる行政手続きです。
特に事業開始のタイミングを左右する「交付決定」の存在は、全体のスケジュールを計画する上で最も重要な要素の一つとなっています。
その他のいろいろな注意点

本補助金を活用するにあたり、事業者が必ず認識しておくべき重要な注意事項がいくつかあります。
これらは、資金繰り、法的義務、長期的な責任に関わるものであり、安易な申請は大きなリスクを伴う可能性があります。
補助金は後払い(償還払い)であること
補助事業にかかる経費は、一旦事業者が全額自己資金で立て替えて支払う必要があります。
補助金は、事業完了後の実績報告と確定検査を経て、最後に入金されます。
したがって、事業を遂行するための十分な自己資金(または融資)を確保しておくことが大前提となります。
不正受給に対する厳しい罰則
近年、虚偽の申請や補助金の目的外利用などが相次いだことで、補助金事務局といても不正行為についてはかなり力を入れているようです。
補助金交付決定の取消・返還命令(加算金付き)、事業者名の公表といった行政処分に加え、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という刑事罰の対象となる可能性があります。
処分制限財産
補助金で購入した単価50万円(税抜き)以上の機械装置や、外注で構築したウェブサイト、店舗改装などは「処分制限財産」と見なされます。
これらの財産は、補助事業終了後も一定期間(通常5年)、補助金事務局の承認なしに目的外使用、譲渡、廃棄等をすることができません。無断で処分した場合、補助金の返還を命じられることがあります。
収益納付の可能性
補助事業の実施によって直接的な収益(例:補助金で出展した展示会での売上、有料セミナーの参加費収入など)が生じた場合、補助金額を上限として、その収益の一部または全部を国に返納(収益納付)する義務が生じることがあります。
書類の5年間保管義務
補助事業に関する全ての帳簿および証拠書類は、事業が終了した年度の終了後5年間、保管しなければなりません。
この期間中、会計検査院等による実地検査が行われる可能性があり、その際は協力する義務があります。
GビズIDの取り扱い
第三者の支援者等にGビズIDのアカウント情報を開示することは、利用規約違反となります。申請手続きは必ず事業者自身が行う必要があります。
賃上げ未達時のペナルティ
「賃金引上げ特例」や「賃上げ加点」を受けて採択されたにもかかわらず、正当な理由なく賃上げ要件を達成できなかった場合、その後の一定期間、中小企業庁が所管する他の補助金(ものづくり補助金、IT導入補助金等)の審査において大幅な減点措置が取られます。
これらの注意点は、本補助金が単なる資金援助ではなく、厳格なルールと長期的な責任を伴う公的資金の活用であることを示しています。
申請者は、これらの義務とリスクを十分に理解した上で、誠実かつ計画的に事業に取り組むことが求められます。
その他のいろいろな注意点
最後にもう一度、我々のサービスについてご紹介させてください。
私たちは「中小企業専門の経営相談所」として、経営コンサルタントの国家資格を持つ、様々な分野の専門家を集めて活動しています。
そのため補助金の申請だけで終わらず、採択された後にどのように事業を進めていくかなど、ご要望に応じて事業における様々なサポートが可能。
補助金をもらうことだけで終わらず、補助金を活用してどのように経営を改善するかという視点で、幅広いお手伝いができることが私たちの強みと考えています。
計画書作成のお手伝いだけでももちろん可能ですが、申請した事業に関するその後の実行段階や、その他経営全般のお悩みについてもぜひご相談ください。
よくある質問
無料相談&お問い合わせ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

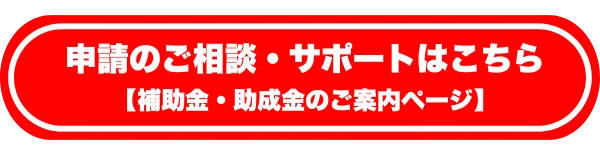

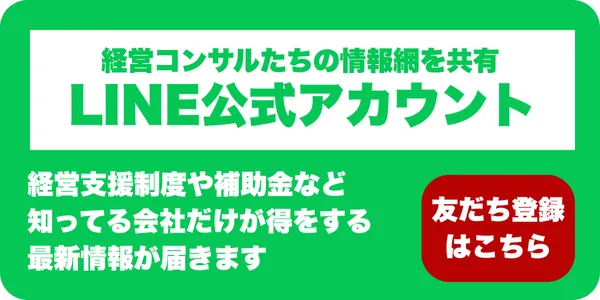













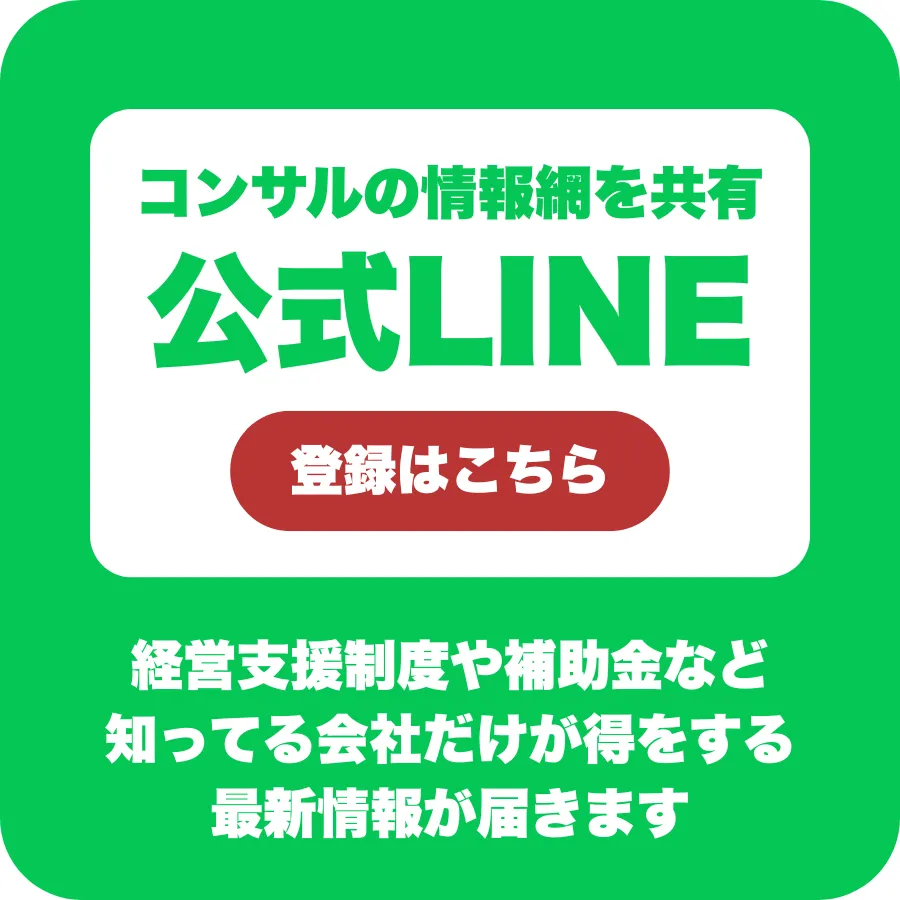












この記事へのコメントはありません。