- ホーム
- 経営全般, 販売・マーケティング
- 中小企業が実店舗の売上を上げる定番施策3選。小売業やサービス業に必須の施策とは
中小企業が実店舗の売上を上げる定番施策3選。小売業やサービス業に必須の施策とは

中小企業専門のコンサルティングオフィス、エクト経営コンサルティングです。
今回は日々の店舗運営に尽力されている中小企業様に向けて、実店舗の改善を得意とする経営コンサルタントが、お店の売上を上げるための定番施策を3つご紹介します。
お金や人手が限られている中で、さらに売上を獲得していくためにはどうしていくべきか。多くの中小企業が同じような悩みを抱える中、ライバル店に差をつけるために抑えておきたいポイントを、実際の事例を交えつつ解説していきます。
さらに後半では、3つの定番施策を最大限活かすために必要な考え方や、これから必要とされる実店舗の戦い方についても触れていきたいと思います。
実店舗の売上を上げたいと考えている中小企業経営者の皆様、この記事で改善のヒントを見つけてください!
目次
定番施策1:店舗のデータ分析と仮説検証

まず当たり前かもしれませんが、お客様は何かを求めてお店に来ています。
お客様が自分の店舗に求めていることは何なのか、徹底的に考え直してみることで、売上向上のための大きなヒントが得られます。とはいえお客様一人一人に、根掘り葉掘りお店に来た理由を聞くのは現実的ではありません。
そこで大活躍するのが「データ」です。近年は中小企業の店舗においても、データ活用の有無によってその命運が分かれる場合もあるほど、データというものは経営で非常に重要な要素となっています。
実店舗におけるデータは、以下のように大きく2種類に分けられます。
商品のデータ
取扱商品のうち、何がどれだけ売れたかという情報を中心としたデータです。
基本的には、自社が取り扱う全商品の販売データを収集していることが理想です。「販売データなんて忙しくて取れない」という場合も、少なくとも主力商品、もしくは主力となりえる商品だけでも、データの集計を始めましょう。
データの集計手段としては、POSレジからデータを抽出する方法が一般的です。POSレジがない場合は、手計算による日々の集計となってしまいますが、正確性や手間の少なさからもPOSレジの導入をおすすめします。
顧客のデータ
誰が、いつ、どの商品を、どれくらいの量・周期で購入するのか。商品だけでなく、より有益なデータを収集・抽出する仕組みを構築するために、顧客のデータは必要不可欠です。
会員登録などによって顧客マスターが蓄積されるオペレーションなら、これらのデータを収集・抽出することは比較的容易になります。顧客マスターが無い場合は、簡易なポイントカードなどを用意することで、大まかな傾向を把握することができます。
いずれの場合も、商品ごとのリピート率(離反率)や、新規顧客・既存顧客の割合などが分かれば尚良しと言えるでしょう。
仮説と検証
商品と顧客、得られた2つデータから売上の傾向を分析し、お客様の要望に応えて売上を上げるにはどうしたら良いのか、仮説を立てて施策を考えてみましょう。
重要なのは、簡単でもよいので計画を立てることです。計画を立ててスケジュールが明確になっていないと、施策の正確な検証や改善ができません。
仮説を立てて計画を作成し、実際に施策に取り組み、その結果得られたデータを検証して、再度仮説を立てて計画を作る、これを繰り返して販売分析を精緻化していくのです。
販売価格や販売数量などの正確なデータが得られることにより、取扱商品を選別し、商品選定という部分でも役に立つはずです。
以上のようなデータ活用と、施策についての仮説検証の仕組みを構築することが、売上向上のための第一歩となります。
定番施策2:販売戦略のための体制づくり

データを分析していくうちに、どのような商品を売るべきか、どのような売り方に注力するべきかという販売戦略が見えてくるはずです。
販売戦略をうまく実行するにあたっては、内部の体制を整えることが必要不可欠です。計画に合わせて店舗全体のオペレーションを整えることにより、従業員全員の仕事が噛み合うように連動させていきましょう。
以下ではその具体的なポイントを説明していきます。
顧客に合わせたプロモーションの実施
データから売るべき商品を決めたら、広告や販売促進施策を想定顧客に合わせて実施しましょう。
極端に悪い例にはなりますが、若年層向けに新聞広告を打つ、ご高齢の方向けにTikTokを投稿する…などといった施策は、全く効果を生まないことが容易に想像できます。このような想定顧客に合わないプロモーションは、間違いなく広告予算を無駄にするだけで終わってしまいます。
また広告手段を選択する際は、必ず「効果測定できるもの」を選んでください。選択した広告手段は本当に効果があったのかという検証ができないと、正しい意思決定や後での再現ができなくなってしまいます。
接客のシミュレーション
プロモーション施策で来店を促進できたら、その受け口としての内部体制を整えます。来てくれたお客様に対して、接客の流れを構築しておきましょう。
売るべき商品の特性やお客様のニーズという情報については、従業員数10名程度の規模までであれば、スタッフ全員への周知を目指しましょう。そのためには時間がかかったとしても、販売のシミュレーションを実施することが望ましいです。
シミュレーションのやり方としては、仮のオペレーション案を立てた後に、ロールプレイングという手法で精緻化する方法がおすすめです。
ロールプレイングは従業員同士で役を演じるというシミュレーションで、「お客様役」の従業員に対して模擬接客するという方法です。大手企業でも取り入れられている手法であり、従業員間のコミュニケーション促進や、個人の課題発見という点でも効果が期待できます。
組織風土
シミュレーションは大切ですが、「現場で機能しない」ということも珍しくはありません。
そういったパターンを前提として、全員でシミュレーションを繰り返し、全員で検証して、全員でオペレーションを精緻化していく、という習慣を構築していきましょう。
ここで重要なのは、経営者が「一緒にやる姿勢」を見せることです。こういった点に配慮できているかどうかで、組織の風土は大きく異なります。手法や技術というよりも、気持ちという部分に対しても重視することで、店舗全体のより良いオペレーションを構築していくことができるのです。
以上のように、データを元にした戦略を最大限活かすための「集客と体制整備」は、売上向上のために欠かせない施策となります。

定番施策3:在庫管理の仕組みづくり

売るべき商品と販売戦略が決まり、売るための体制を整えることができたら、後は「売れ続ける」ための仕組みづくりが重要です。
とりわけ大切なのが、在庫管理のオペレーションをしっかり構築すること。
作った仕組みを継続することは、口で言うだけなら簡単なように思いますが、意外と難しくすぐに綻びが発生するものです。そこで以下で挙げるような点に注意し、安定した在庫の供給体制を実現しましょう。
日次管理
商品が「何曜日に何個売れるのか」など、日次の需要の特性を把握しておきます。すべての在庫の動きを把握できればベストですが、売るべき注力商品だけは特に注視しましょう。
ここにもデータが活きてくるところで、日次で集計した細かいデータをよく分析しておくことで、在庫数の適切化につながります。適切な在庫数を把握できれば、欠品だけでなく廃棄も最小化できます。
なおデータを集計するシステムが無いと、店舗運営全体の効率性が大きく低下しますので、ぜひとも優先して導入を検討することをお勧めします。どうしてもシステム導入が難しい場合には、売るべき商品の入出庫だけでも記録する仕組みを整えてください。
情報共有
売るべき商品の販売数量や在庫状況については、従業員全員がすぐに確認できる仕組みと習慣を構築しておきましょう。
在庫管理システムがあれば、どのタイミングでチェックしてどの方法で他の従業員に伝えるかという点を決めておくことができます。売るべき商品の在庫を細かく把握することだけでなく、従業員への意識付けという意味でも、こういったルールがあることが望ましいです。
せっかく商品が売れていても、もし在庫が無くなってしまえば、販売機会を逃してしまいます。以上のように日次管理や情報共有の仕組みを徹底すれば、欠品という事態を最低限に抑えられるはずです。
しかしながら従業員も人間です。次第に管理が行われなくなってしまう可能性を考慮し、仕組みやルールはできる限りシンプルで、継続しやすい方法にしておいた方がよいでしょう。
近年は人手不足も深刻化しており、効率化や仕組みづくりの重要性も欠かせません。
中小企業の実店舗の成功事例

実際に3つの施策が絶大な効果を発揮し、売上が前年比130%以上まで向上したという、私の経験した事例を紹介していきます。
ある中小企業様が運営するこの店舗は、改善に着手する前は以下のような状況でした。
- 従業員数:10~15名
- 客単価:業界平均より15~20%程度低い
- 客数:業界平均もしくはやや多い程度
- 販売経路:実店舗、自社ECサイト
固定のお客様はそれなりにいるものの、いつもと同じものを習慣的に買うという方がほとんどです。従業員も日々の運営を「回す」ことに手一杯で、接客や管理に甘さが見られました。
そういった中で販売データを分析すると、やや高価ながら品質が良いという「商品X」のリピート率が高いことを確認することができました。
データから高付加価値商品の訴求を提案
まずデータを確認したところ、顧客の平均年齢は40歳前後であり、一定以上の収入を得ている層であることが推測できました。
そこで「良いものを体験することへのニーズがあるかもしれない」という仮説を立て、「商品X」について試供品提供などのプロモーションをかけることにしました。
その結果として興味を持つお客様は多かったため、そこからは「商品X」に関する集中的な接客シミュレーションを実施。これが奏功し、お客様に十分に納得していただいた上で、購入商品を高単価な「商品X」へ切り替えるという単価アップを進めることができました。
このようにデータに基づいた施策により、店舗全体の客単価向上を実現しただけでなく、顧客満足度の向上についても両立することができたのです。
在庫の安定化とまとめ買いの促進
その後は欠品防止を主な目的に、段階的に「商品X」の在庫量を増やしていくことにしました。
過去実績を基準とするとやや過剰気味になりましたが、「まとめ買いを提案すること」を接客フローに組み込んだことで、客単価がさらに大きく向上。当初は8,200円ほどだったところ、11,000円近くまでの上昇を実現できました。
その後のデータでは、まとめて購入したお客様の来店頻度が低下していることを確認しました。
しかし顧客1名あたりに対する接客時間に余裕が生まれたため、全体として売上を大きく改善しながら、口コミ評価の上昇にもつなげることができたのです。
店舗とECのシナジー効果
これまでの施策により、既に実店舗の売上は大幅に改善していましたが、データを確認すると客数の伸びに限界が感じられ、さらなる売上向上のためには客数の増加が必要と判断しました。
そこで新たな施策として、「商品X」を継続購入するお客様に対して、自社ECサイトへの案内を徹底することに決定。
短期的には「実店舗の利用者がECに移動しただけ」という状況になりましたが、2つの購入経路を示したことで顧客が離反しにくくなり、中長期的な結果としては店舗・ECトータルでの客数増加を実現しました。
実店舗ではアプローチできなかった新規顧客をECで開拓できた成果は大きく、WEB上で紹介クーポンを設定するなど、販促のレパートリーも増やすこともできました。
成功する施策を生み出すための考え方
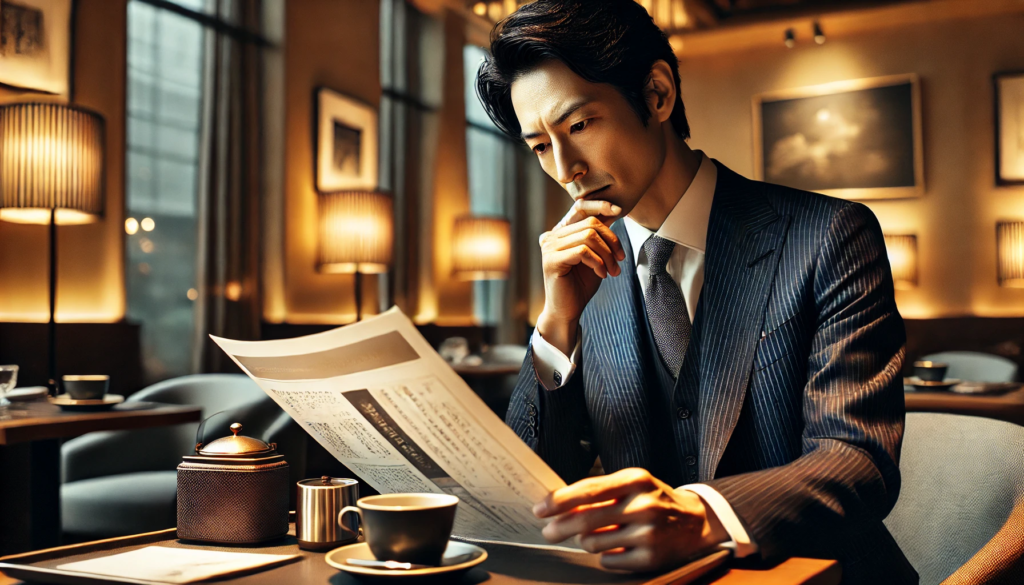
以上が店舗の売上前年比130%以上という、優良な成功事例のご紹介です。
まさに3つの定番施策がうまくいった事例ですが、このように自社の店舗に合った有効な販売戦略を導き出すためには、様々なアプローチが存在します。
その中でも「売上の分解」と「差別化」を起点にする方法は、わかりやすく様々な形態の店舗で使える考え方なので、ここで紹介させていただきます。
売上を分解して考える
売上を上げようと意気込んでも、売上自体が何でできているかという点を曖昧なまま進めてしまうと、有効な販売戦略は生み出せなくなってしまいます。
そこで販売戦略を考えるにあたっては、まず売上そのものについて理解を深める必要があります。売上の構造について、基本的な部分を改めて考え直してみましょう。
売上というものは、以下の式で表すことができます。
売上 = 客単価×客数
さらに分解すると、以下のような式に展開できます。
客単価 = 商品単価 × 購買点数
客数 = 新規顧客数 + (既存顧客数 × リピート率)
客単価は、例えば高付加価値商品の提案やセット販売を実施することにより向上します。客数は、新規顧客獲得とリピーター育成に注力することで増加します。
今回の事例では、まさに客単価と客数を上げることに着目したことで、最適な施策に辿りつくことができました。
このように売上を分解した視点に基づいて、データ分析から顧客ニーズを把握し、有効な販売戦略を考えていくとよいでしょう。
差別化を考える
中小企業の経営には「差別化」が重要なキーワードとなります。
他社と差別化できている商品があると、競争が激しい市場で価格競争に巻き込まれにくい、自社のブランド価値を高める、リピーターの増加につながるなど、多くのメリットが得られます。
先程の成功事例では、短期的に着手できる施策として「既存商品の中から売るべき商品を見つける」という例を取り上げましたが、差別化商品があればまた違った戦略も立てられたと思います。
とは言ったののの、昨今は他社との差別化が非常に難しくなっています。
中小企業の理想としては「他社が簡単に模倣できない独自の商品を持つこと」なのですが、それを実現することが現実的でない場合も多いでしょう。
開発コストや訴求力不足といった自社の事情に加え、すぐに新しいものが求められるため、苦労の末に差別化商品ができても、すぐに陳腐化してしまう可能性もあります。
そこでお伝えしたいのは、「差別化できるのは商品に限らない」という点です。
ご紹介した「データ分析と活用」「販売体制の構築」「在庫管理体制の構築」という3つ定番施策は、いずれも自社ならではのノウハウとして模倣されにくい優位性になる可能性を秘めています。
販売戦略を考える上では、まず自社の内部を工夫することでどのように差別化できるか、という点を切り口にすると良いでしょう。

実店舗の環境変化と今後について

近年、実店舗を取り巻く環境は大きく変化してきました。
とりわけEC市場の拡大は、実店舗を経営する中小企業にとって大きな脅威となっているはずです。
総務省統計局の2024年までのデータを確認すると、ECを利用する世帯割合が拡大するとともに、ネットショッピングへの支出額も増加していることが確認できます。一方で家計の消費支出については、15年近くの数値に大きな変化は見られませんでした。
消費支出額に変化が見られない一方、ECの支出額が増加しているという事実からは、「今まで実店舗で購入していた商品をECサイトで購入するようになった」と判断できます。
実店舗の販売額が低下しているとの報告書も多く見られ、少なくとも10年前より厳しい環境に置かれていることは間違いないでしょう。
こういった現状ではありますが、一方で実店舗には実店舗でしか実現できないニーズがあります。
実際の商品を確認できる「体験価値」、スタッフと相談できる「コミュニケーション」、その日に商品が手に入る「即時性」などは、実店舗だからこそ提供できる大きな強みであるはず。
こういった部分を最大限に活かしつつ、今回ご紹介したような定番施策をキッチリとこなし、自社にとって適切な販売戦略を構築することが、実店舗で今後生き残っていくために必要不可欠となるはずです。

実店舗の売上向上はプロフェッショナルに相談を
貴社では適切な販売戦略を構築できているでしょうか。
お店の売上低下に危機感を抱いているけど、具体的にどう改善したら良いかわからず、お悩みの経営者様も多いのではないかと思います。
人件費も物価も高騰する一方で、店舗には投資が求められる。近年の経営環境の変化はすさまじく、中小企業様が単独で実店舗を改善していくには、なかなか難しくなってきているのが実情です。
もし貴社がそういった状況であるなら、外部のコンサルタントに相談するのが近道かもしれません。
エクト経営コンサルティングは、実店舗改善の専門家を含め、多様なジャンルの専門家が集まるコンサルティングオフィスです。
担当させていただくコンサルタントは、経済産業省の登録する中小企業診断士だけに限定。小売業やサービス業を得意とする専門家をはじめ、中小企業支援に必要とされる様々なプロフェッショナルが、貴社の店舗改善を5万円からの価格でサポートさせていただきます。
売上を上げるための販売戦略構築はもちろん、利益率向上、人材育成、業務効率化といった分野まで、ご相談次第で店舗運営全般の様々なお手伝いも可能となります。
もし実店舗の運営にお悩みであれば、お気軽に以下のフォームよりご相談ください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

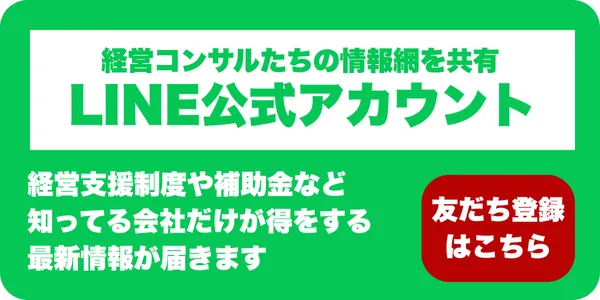













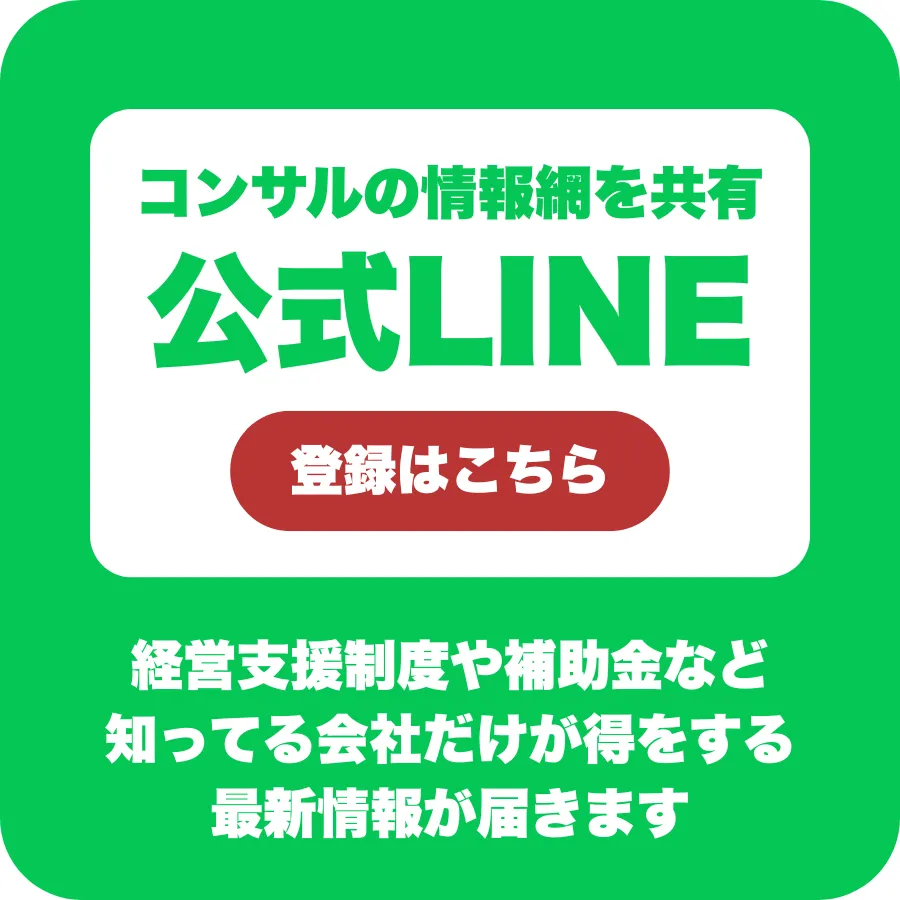










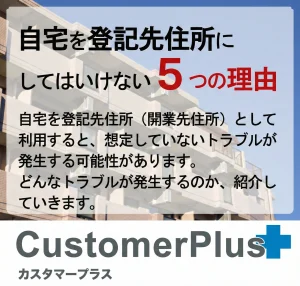

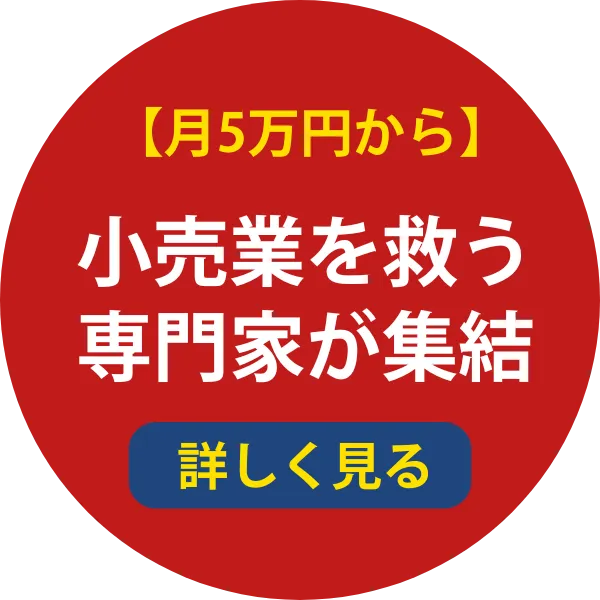
この記事へのコメントはありません。