ものづくり補助金の申請は、採択率82%超のコンサルタントに相談を

ものづくり補助金は2013年から続いており、多くの中小企業が活用している代表的な補助金です。
2025年現在、ものづくり補助金はルールを変えて継続されていますが、申請のハードルは上昇傾向にあります。
もし以下のような点にお悩みがあれば、ぜひ私たちの申請サポートをご利用ください。
- 申請のためにかける時間が無い
- 事業計画書の作成方法がわからない
- 申請に関連する業務代行を依頼したい
- ルールが細かすぎて正確に把握できない
- 採択率を上げる方法がわからない
- 相談できる相手がいない
- 獲得後に計画どおり実行できるか不安
- 自社に合う補助金がないか教えてほしい
【着手金0円プラン新登場、詳しくは以下のボタンから】
目次
- 1 補助金を知り尽くすプロ集団がサポートします
- 2 ものづくり補助金の申請サポート内容
- 3 【2026年1月最新速報】第22次公募に間に合わせたい方、お早めにご相談ください
- 4 補助金の専門家に申請のポイントをインタビューしました
- 5 ものづくり補助金の支援事例
- 6 ものづくり補助金とは?
- 7 ものづくり補助金の対象になる事業者
- 8 ものづくり補助金の対象となる経費
- 9 ものづくり補助金申請に必要な提出書類
- 10 2025年からの主な変更点
- 11 ものづくり補助金申請の流れ
- 12 ものづくり補助金事業計画書の作り方
- 13 ものづくり補助金の審査項目と評価ポイント
- 14 ものづくり補助金採択後に必要なこと
- 15 補助金コンサルタント活用のポイント
- 16 よくある質問
- 17 無料相談&お問い合わせはこちら
補助金を知り尽くすプロ集団がサポートします

エクト経営コンサルティングは、中小企業専門の経営相談所です。
当オフィスが連携している補助金のプロフェッショナル集団は、現在までに300以上の支援実績があり、採択率82%以上を誇る精鋭部隊。
補助金は申請すれば必ずもらえるわけではなく、大量の申請事業者の中から「採択」されなければなりません。
そして「採択」されるかどうかは、事業計画書の出来にかかっています。
ものづくり補助金全体の採択率は、以前は60%前後で推移していた時期もありましたが、近年はその水準がかなり低下してきており、直近ではなんと30%前後にまで落ち込んでいます。
そんな難しい状況とはいえ、あきらめる前に補助金コンサルタントの活用も検討しましょう。
以下では補助金申請に伴って発生する業務の代行をはじめとして、私たちのサービス内容をご紹介しつつ、ものづくり補助金の基礎知識についても網羅的にご紹介していきます。
ものづくり補助金の申請サポート内容

私たちは中小企業専門の経営相談所として、様々な分野のプロフェッショナルと連携し、経営に関する幅広いお悩み解決をご提供しています。
各種補助金・助成金の申請サポートでは、事業者様の予算やご要望に応じて、例えば以下のようなご相談を承っております。
- 事業計画書の作成を手伝ってほしい
- 採択率を高めるためのアドバイスがほしい
- 申請後の実績報告をサポートしてほしい
- 新規事業の舵取りを任せたい
- その他に使える補助金制度が知りたい
- 補助金以外の経営課題も相談したい
その他にも、補助金申請に関連して発生する幅広い業務代行も可能。
計画策定に慣れていない事業者様には、中小企業診断士や行政書士による手厚いサポートにより、ルール違反にならない範囲で可能な限りお手伝いさせていただきます。
料金体系
料金体系については、主に以下の2つに分かれています。
- 計画書作成サポート
- 伴走支援サポート
サポート内容、申請金額、着手金の有無など、内容によってどうしても変動する部分があります。着手する前に十分なご説明を差し上げ、明確にした上で実行に移ることをお約束します。
計画書作成サポートの場合
計画書作成サポートの料金は、主に「着手金」と「成功報酬」に分かれています。
計画策定、申請に関連するアドバイスや、採択後の手続き、実績報告といった内容についても、ご要望に応じて柔軟に対応いたします。
「成功報酬」を中心の料金体系にすれば、万が一採択されなかった場合でも、事業者様にとって損するリスクはかなり小さくなります。
伴走支援サポートの場合
伴走支援サポートでは、計画書の内容に関するフィードバックやアドバイスに加えて、申請する事業の「実行」をお手伝いします。
ご要望であれば、経営のその他のお悩み解決も承ります。
実際にサポートを開始する前に、まずは無料相談にて詳細をご説明しますので、ぜひ実際に話を聞いてみてください。
【着手金0円プラン新登場、詳しくは以下のボタンから】
【2026年1月最新速報】第22次公募に間に合わせたい方、お早めにご相談ください
12月26日に申請がスタートした第22次公募について、2026年1月30日(金)の締切が迫っています。
申請を検討していたけど、なんだかんだでギリギリになってしまった場合もあると思います。
貴社の状況や申請内容にもよりますが、締切2週間前にご連絡いただければ間に合うかもしれませんので、お急ぎの方はこちらのフォームから何卒お早めにご相談ください。
ひとまず最大のポイントとなる計画書をはじめとして、書類の準備になるべく早めに着手されることをおすすめします。
2025年10月24日、ものづくり補助金第22次の公募要領が発表されました。
前回の第21次公募より、以前までと異なる重要な変更が発表されています。
直近の採択率は30%台と非常に厳しく、まさに「狭き門」となってしまったものづくり補助金。何も知らずに準備を進めると、スタートラインにすら立てない可能性があるので注意してください。
2025年10月27日には、20次公募の採択結果も公表されました。採択率は33.6%と、かなり厳しい結果となっています。
よろしければ以下から、LINEで補助金の最新情報をGETしましょう。
第22次公募のスケジュール
まずは基本情報として、今回のスケジュールをしっかり押さえておきましょう。
これまでと異なる変更点に要注意
2025年の第21次公募からは、形式的な不備で一発アウトになるルール変更が加えられています。
従業員0名では申請不可に!
これまで可能だった従業員がいない事業者(一人社長など)の申請が、21次からは一切できなくなりました。
これは「賃上げ」が補助金の必須要件であるため、「給与を支払う対象がいない場合は制度の目的を満たせない」という判断によるものです。
設立直後の法人や個人事業主の方は、申請前に人員体制を整える必要があります。
計画書の添付資料ルール
事業計画の補足資料として添付できるPDFが、3ページから5ページに増量されました。
図や写真を盛り込みやすくなった一方で、1ページでも超えると即審査対象外となる厳しいルールが明記されています。
なお空白ページもカウントされるようなので、提出前には細心の注意が必要です。
重複申請のペナルティ強化
他社の事業計画を安易に真似るなど、重複が疑われる申請へのペナルティが大幅に強化。
これまでは「次回の申請が不可」でしたが、今回からは「次回とその次」の2回にわたって申請資格を失うことになりました。
オリジナリティのある、自社の強みを活かした計画作成がより一層求められるようになったと言えます。
申請の難易度
ものづくり補助金をかなり前に活用したことのある事業者様なら、申請方法や採択のための要件が、以前よりも簡略化されてきたようにも見えるかもしれません。
しかし実際のところは複雑そのものであり、申請回のたびにルールが変更されることも多いため、情報を整理することすら骨が折れるはずです。
経営者様とお話しする中で、「ものづくり補助金は魅力的だけど、諸々の手間がかかりすぎて使えない」というお声を聞くことも珍しくありません。
最近の第19次公募では、以下のとおり採択率が約31.8%となっており、3社に1社しか通らない非常に厳しい結果となりました。
これは単に申請件数が多いだけでなく、審査基準そのものが厳しくなっているのも一因のはずです。
とはいえこれで申請を諦める事業者が増えれば、ものづくり補助金の競争が緩和され、逆にチャンスが生まれるかもしれません。
また過去の採択率も大幅にブレており、劇的に改善する可能性もあるということで、ぜひ前向きに取り組んでいきましょう。
採択率の推移
採択のためにぜひとも抑えておきたいポイント
申請を検討されている中小企業様は、以下のポイントは必ず抑えて挑戦しましょう。
ポイント1.加点項目の取得
最新のデータでは、加点0個の事業者の採択率が約33%だったのに対し、3個取得した事業者は53%と、実に20%もの差が生まれています。
特に短期間で準備できる「パートナーシップ構築宣言」と「成長加速マッチングサービス」は必須と考え、積極的に取得するとよいでしょう。
ポイント2.計画書のブラッシュアップ
審査では計画書の内容が厳しく見られています。
作成にあたっては、補助金採択の実績とノウハウを保有する、専門知識を持ったコンサルタントを活用しましょう。
なお付加価値額や賃上げ率はどれくらい上げればよいか、という疑問はよく聞かれますが、基本的には高い目標値の方がよいものと考えられます。
しかし賃上げ目標は、未達の場合補助金返還のリスクがあります。経営にも大きなインパクトを与えるため、実現可能な範囲で設定するよう注意してください。
今後の見通し
ものづくり補助金の採択率は改善される可能性もあるとはいえ、難易度自体は以前より確実に高くなっています。
他の一部の補助金にも当てはまりますが、ただでさえ業務に追われている中小企業様が自力で申請するには、もはや現実的ではなくなってきているのが現状です。
そこで本気で申請に取り組むのであれば、信頼のおける適切なコンサルタントを活用し、採択の可能性が高い計画書作成サポートを受けることをおすすめします。
補助金の専門家に申請のポイントをインタビューしました

ものづくり補助金の採択を受けるために必要なことについて、当オフィスと連携している補助金の専門家に話を聞きました。
これまでの補助金に関する経歴を教えてください
計画書の作成を中心として、申請のサポートは数え切れないほど携わってきました。
特にものづくり補助金は得意分野の一つで、2025年に私が支援したものづくり補助金の事業者様は、今のところ採択率100%という実績です。
他にも事業再構築補助金や、東京都中小企業振興公社による助成金をはじめとして、幅広い申請のお手伝いを経験しています。
詳しくはお話しできませんが、以前には某補助金を運営する側の事務局に在籍していたこともあります。
採択されるために重視すべきポイントは何でしょうか?
ポイントはいろいろありますが、最重要なのは「補助金の制度趣旨」と「自身の事業プラン」が合致しているかですね。
国がどのような目的でその補助金を出しているのかと、自社のやりたいことが自然にマッチしている必要があります。補助金の要件に合わせて、本来想定していた方針を無理やりねじ曲げてしまうと、どうしても計画書の内容に歪みが生じます。
結果として実現可能性の説明に無理が発生し、不採択の可能性も高くなってしまうのです。
また数あるポイントの一つをお伝えすると、「直近の公募要領の変化」を見逃さないことが大切です。
まさにものづくり補助金が代表例ですが、名称は同じ補助金制度であっても、長い歴史の中でルールが幾度もマイナーチェンジされています。
そして直近で変更された点こそ、重点的に審査されるポイントということが多いんです。
例えば最近のものづくり補助金も、「革新性」と「実現可能性」が必要であることが明確に打ち出され、審査において実際に重視されていると考えられます。
このようなポイントを意識しつつ、計画書にしっかりと落とし込まなければ採択は勝ち取れません。
ポジショントークになってしまいますが、以上のような点で専門家の力を借りるというのも重要、というかもはや必須条件になってきているとすら感じています。
事業者様はただでさえ忙しいのに、計画書作成に膨大な時間なんてかけられないのが普通です。
それに自分で作った計画書のクオリティが、はたして高いのか低いのかといった判断も、慣れていないと正直難しいですからね。
「革新性」と「実現可能性」はどのように理解すればよいでしょうか?
まず「革新性」について、これは少々抽象的でイメージが湧きにくいですよね。
一つの考え方として、単純に新しいだけでなく「市場が抱えている課題を、新しい技術やアプローチで解決する」という文脈が評価されやすいと思います。
さらにSDGsなど、社会全体の課題解決につながるストーリーがあると、加点対象にならなくても審査員の心に響きやすく、評価される傾向にあると感じています。
「実現可能性」については、一言で言えば数字の根拠と納得感ですね。
例えば「1,000個売ります」という収益計画があったとして、審査員がその計画を見た時に「確かにこの商品ならこの価格で1,000個売れそうだ」と違和感なく思えるかどうかが勝負です。
こういった客観的な妥当性があるかという意味でも、自社だけでなく補助金に詳しい専門家にサポートを依頼することをお勧めします。
どうしても難しければ、経営者仲間など第三者にチェックしてもらえるとよいでしょう。
どれくらい「賃上げ」すればよいのでしょうか?
結論として、採択のためには高くした方がよいと考えています。
近年は多くの補助金で賃上げが要件に盛り込まれていますし、政府としても非常に重視しているテーマであることは間違いないですからね。
多くの事業者様は、賃上げの申請要件はギリギリで計画を作りがちです。実際に採択されている企業の中央値を見ると、ギリギリよりも高い水準で賃上げ目標を掲げているケースが多いと思います。
とはいえ補助金が欲しいあまりに、無理して賃上げをすることは決しておすすめしません。
採択率は上がるかもしれませんが、高すぎる人件費は財務面を強烈に圧迫するだけでなく、達成できなければ返還義務が生じることすらあるのです。
サポートを依頼するにはどうしたらいいですか?
ご希望の方は以下よりお気軽にお問い合わせください。
私を含めて申請支援実績300以上、採択率82%超という、数多くの補助金の採択実績を持つ専門家集団が、全力でサポートさせていただきます。
まずは複雑な制度の理解や、申請内容をどうするかといった部分からでも喜んでお手伝いします。
【着手金0円プラン新登場、詳しくは以下のボタンから】
ものづくり補助金の支援事例

連携している専門家たちによる、実際の補助金サポート事例についてご紹介します。
A社の事例(医療関連卸売業)
クリニック向けに歯科医療の特殊素材を販売されている事業者様で、製品需要の拡大するために新しい設備を必要とされていました。
そこでものづくり補助金の活用を提案し、その申請と業務代行をサポートしたところ、無事に採択を勝ち取り最新機器の導入に成功。
これによって従来は素材の卸売のみだったところ、自社内での加工品の製造・販売が可能となったことで客単価が大きく向上します。
さらに短納期で提供できるようになったことで、取引先の満足度も高めることができ、企業としての成長だけでなくより安定した経営を実現することができました。
B社の事例(ファブレス製造業)
自社で設備を持たず、独自の「製品開発力」と「技術力」を強みに、専門的な機械製品の開発・設計を行っていた事業者様です。
製造委託により社内に製造ノウハウが蓄積されない、リードタイムが1年前後の大型案件が多いといった課題解決のため、ものづくり補助金の活用による設備導入をサポートしました。
結果として見事に採択を勝ち取り、高性能な大型製造機械の導入に成功。
単純に受注案件が増大しただけでなく、短納期の自社製造が可能となったことで売上が平準化され、多角化による経営安定化を実現できました。
C社の事例(製造小売業)
自社ブランド製品を扱う、アパレルの製造メーカー様の事例です。
市場環境の変化とオンライン販売の拡大に対応するため、販売力の強化と業務効率化が必要となり、多額の初期投資が必要となるシステム導入にものづくり補助金を申請。
サポートによって採択が実現し、オンライン上で最適な仕様を選択できる選択支援機能や、効率的な在庫管理の構築に成功します。
加えてECサイトのSEO対策も強化することができ、新規顧客の獲得も増やすことができました。
ものづくり補助金とは?

そもそも補助金制度がよくわからないという方のために、ここからはものづくり補助金という制度のルールについて詳しく解説していきます。
どんな補助金でも共通する前提として、「その補助金がどのような目的で設計された制度なのか」を知っておかなくてはなりません。
当たり前のようですが、意外とこの視点が抜けてしまう事業者様も多く、制度の目的と噛み合わない計画書を作成してしまわないように注意が必要です。
ものづくり補助金の正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と言います。
この補助金の概要としては、中小企業の新製品開発などにかかる費用を、国が補助してくれるというもの。それによって中小企業の生産性向上を促進し、経済活性化を実現させることを目的としています。
大前提となる話として、ものづくり補助金は新しい挑戦が求められる補助金です。
そのため単なる設備投資にとどまらず、革新的な新製品・新サービスの開発や海外事業の実施など、新たなチャレンジに取り組む事業が補助の対象となります。
もし既存の製品・サービスについて、業務やプロセスを単純に効率化・省力化するだけであれば、別途用意されている「中小企業省力化投資補助金」などを検討した方がよいでしょう。
また名前に「ものづくり」とついていることもあり、一見すると製造業が設備投資をするための補助金のように思われがちですが、新たなチャレンジや海外展開に取り組むのであれば、幅広い業種が対象となる補助金です。
いろいろ紛らわしいことが多い補助金なので、まず最初にこういった点を理解しておきましょう。
※申請ルール等は随時変更となる可能性があるため、必ず最新の公式情報もご確認ください。

ものづくり補助金の対象になる事業者

ものづくり補助金の申請に適している企業
ものづくり補助金の申請に適している企業の条件を挙げるとすれば、まずは革新的なアイデアと、それを実現できる力のある企業だと考えられます。
単に既存の設備を更新するのではなく、自社の技術力や強みを活かして、市場に新たな価値を提供する新製品や新サービスの開発を目指していることが重要です。
次に生産性向上と持続的な賃上げに、積極的に取り組む意思と計画がある企業というのもポイント。
というのもこの補助金をもらうためには、付加価値額の向上、従業員の給与水準の引き上げ、事業所内最低賃金の引き上げといった明確な数値目標を達成する具体的な計画と、それを実現できる見込みがあることが不可欠だからです。
特に賃上げは国の政策としても重視されており、補助金を得るだけでなく、従業員への還元を通じて企業全体の成長を目指す姿勢が評価されるでしょう。
さらに一定の経営基盤があることも重要です。
補助事業には単価50万円以上の設備投資が必須であり、自己資金や金融機関からの融資を含めた資金調達計画の実現性も審査されます。事業計画を確実に実行できる技術力、人材、社内外の連携体制が整っているとより望ましいでしょう。
もしこれらの要素を総合的に満たし、新たな挑戦に取り組もうとしている企業であれば、ものづくり補助金の申請に最適な企業であると考えられます。
補助対象となる事業者
ものづくり補助金は主に以下のような事業者を対象としています。(他の事業者でも対象となる可能性が考えられます)
補助対象外となる事業者
以下にあてはまる事業者は、ものづくり補助金を獲得することができません。
無駄骨にならないように、自社が補助対象者に該当するか、また対象外のケースに当てはまらないかは、事前にしっかりと確認することが不可欠です。
- みなし大企業: 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等。
- 過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者。
- 本補助金の申請締切日を起点にして16ヶ月以内に特定の補助金(中小企業新事業進出促進補助金、中小企業等事業再構築促進補助金、ものづくり補助金)の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、または申請締切日時点においてこれらの補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
- 過去のものづくり補助金で「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者。
- 過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者。
- 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業(みなし同一事業者(親会社と子会社等)を含む)。
- 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
- 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者。
ものづくり補助金の対象となる経費

そもそも申請する経費が対象になるのかという点も、しっかりと把握しておくべきポイントです。
補助対象経費となる主なもの
経費に関するルールと注意点
ものづくり補助金の申請にあたり、以下のような点は意外と見落としがちなため注意が必要です。
- 交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外です。
- 支払いは原則、銀行振込で、補助事業者自らの名義で行った銀行振込の実績で確認をします(原則、現金払い及びクレジットカード払いは不可)。
- 単価50万円(税抜)以上の物件等については、原則として2者以上から同一条件による見積りをとることが必要です。
- 消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。
- 「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜)までを補助上限額とします(グローバル枠の場合は、1,000万円まで)
補助対象外となる経費の主な例
どの経費が対象になるか、ならないかはかなり細かく規定されています。不明な点は事前に事務局に確認するなど、慎重に進めることをおすすめします。
- 補助事業実施期間中の販売を目的とした製品・サービス等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(試作品の原材料費は除く)。
- 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用。
- 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)。
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォンなど。ただし補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)。
- 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用。
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用。
- 公租公課(消費税等)。
- 事業に係る自社の人件費(ソフトウェア開発等)。
また2025年に新登場した補助金として、中小企業新事業進出補助金があります。
何かと話題になった事業再構築補助金の後継として位置づけられており、新しい挑戦というテーマにおいては、ものづくり補助金の対象経費と重複する部分があります。状況によっては、中小企業新事業進出補助金も検討する価値があるかもしれません。

ものづくり補助金申請に必要な提出書類
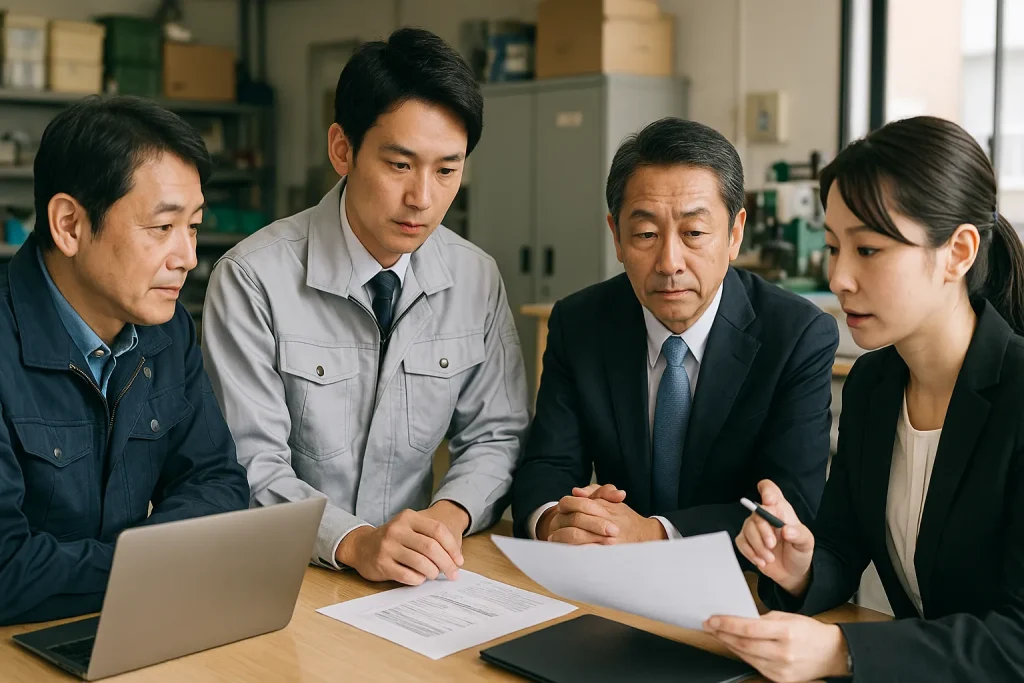
申請にあたっては、全て電子申請システムの利用が求められます。
提出書類は多岐にわたるため、漏れがないようチェックリストを作成するなどして管理するとよいです。またファイル名まで指定されるパターンも多いのですが、一見しただけでは見逃しやすく案内されているため、最初から把握しておくと無駄な作業を減らすことができます。
なおGビズIDプライムアカウントは、未取得の場合は早急に申請してください。多くの補助金で必須となるもので、発行には一定期間を要します。
提出書類(全てPDF形式でアップロード)

2025年からの主な変更点

2025年のものづくり補助金では、過去の公募からいくつかの重要な変更が加えられています。
これらの変更点を正確に理解することが、採択への第一歩となります。公募要領自体も随時更新されているため、最新版の確認を怠らないようにしてください。
申請類型のリニューアル
従来の複雑だった申請枠が見直され、主に以下の2つのシンプルな枠に再編されました。
製品・サービス高付加価値化枠
革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化を目指す取り組みを支援します。 既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて、改善・向上を図る事業は補助対象外です。 あくまで革新的な新製品・新サービス開発が対象です。
グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。 海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。
補助上限額と補助率
補助率は、中小企業で1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者で2/3が基本となっています。
製品・サービス高付加価値化枠
従業員数に応じて750万円から最大2,500万円(補助下限100万円)。具体的には、従業員数5人以下で750万円、6~20人で1,000万円、21~50人で1,500万円、51人以上で2,500万円です。※第21次公募より、従業員0人の事業者は申請不可となりました。
グローバル枠
一律3,000万円(補助下限100万円)。
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数規模に応じて補助上限額を引き上げられます。
例えば従業員5人以下なら100万円、51人以上なら1000万円の上乗せがあります。
ただし、この特例は各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者については適用不可です。
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引き上げに取り組む場合、補助率を引き上げるという特例があります。
ただし、常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者については適用不可です。
収益納付の廃止
従来、補助事業で利益が出た場合にその一部を国庫に納付する「収益納付」の規定がありましたが、これが撤廃されました。
これにより、補助事業で得た収益を自社の成長に再投資できるようになり、より活用しやすくなったと言えます。
補助金リピート制限
過去に補助金をもらっている事業者について、以下のように制限が設けられています。
本補助金の申請締切日を起点にして16ヶ月以内に特定の補助金(中小企業新事業進出促進補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金)の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点においてこれらの補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者は対象外です。
また過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者も対象外とされています。
一般事業主行動計画の公表義務
従業員21名以上の事業者は、「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必須要件となりました。
具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
掲載まで1~2週間程度かかる場合があるため、早めの対応が求められます。
事業計画書の提出形式変更
従来Word等で作成しPDFで提出していた事業計画書の本文が、電子申請システムへ直接テキスト入力する形式に変更されました。
補足の図や画像はA4サイズ3ページ以内のPDFで別途アップロードします。
これは小規模事業者持続化補助金など他の事業でも見られる形式ですが、なぜか補助金の申請システムはバグだらけなので、作業が無駄にならないように途中保存などを多用しましょう。
申請支援者・代理人の関与の明確化
申請者本人が計画内容を理解し、丸投げは禁止、契約の透明性が義務付けられるなど、外部支援者の関与に関するルールがより明確に示されました。
類似計画書・コピー申請の厳格化
他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、ペナルティが厳格化されました。
1回目は次回公募の申請を不可とし、2回目以降は次回公募以降4回分の公募の申請を不可とします。
事業実施期間の変更
製品・サービス高付加価値化枠では交付決定日から10ヶ月(ただし採択発表日から12ヶ月後の日まで)、グローバル枠では交付決定日から12ヶ月(ただし採択発表日から14ヶ月後の日まで)と期間が定められ、年度をまたぐ事業実施が可能になりました。
賃金増加要件の厳格化
賃金増加に関する要件の計算方法や達成基準がより厳格化されています。
給与支給総額の年平均成長率を2%以上増加させること、または1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、都道府県の最低賃金の上昇率以上に増加させることが必須となります。
これらの変更点を踏まえ、入念な準備を進めることが採択への鍵となることでしょう。
省力化オーダーメイド枠の後継
2024年までに設定されていた「省力化オーダーメイド枠」の後継として、中小企業省力化投資補助金の一般型があります。
こちらは2025年に大幅なパワーアップを遂げた補助金として注目されており、業務効率化や生産性向上を目指している企業様であれば、ぜひ積極的に検討しましょう。
ものづくり補助金申請の流れ
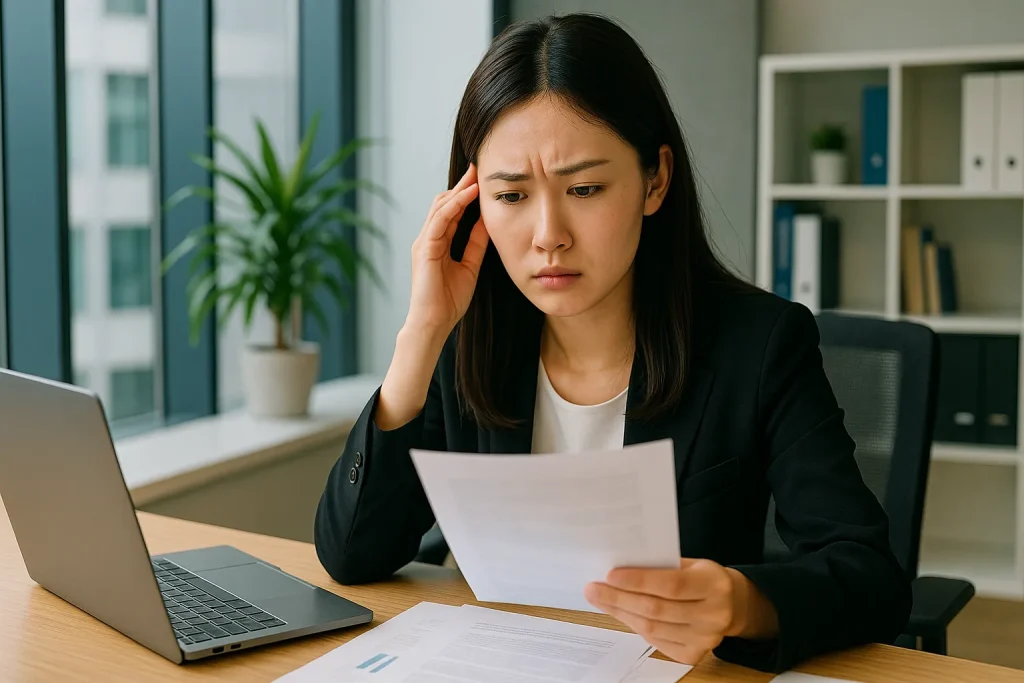
ものづくり補助金の申請から、補助金受領までの大まかな流れは以下の通りです。
- 事前準備: GビズIDプライムアカウントの取得、事業計画の策定など。
- 公募開始
- 申請(受付開始): 電子申請システムにて申請。
- 申請締切
- 審査: 書面審査、場合によっては口頭審査。
- 補助金交付候補者の採択
- 交付申請: 採択後、原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から遅くとも2か月以内とします。
- 交付決定
- 補助事業実施: 設備投資、新製品・サービス開発など。
- 補助事業実施期限
- 実績報告: 事業完了日から30日以内または実施期限の早い方。
- 確定検査
- 補助金の額の確定
- 補助金の請求・支払い
- 事業化状況報告: 補助事業完了後5年間、毎年4月に報告。
なお申請にはGビズIDプライムアカウントが必須です。発行には一定期間を要しますので、お早めにご準備ください。
申請締切直前は非常に多くの申請が予想され、申請が集中した場合は時間を要し、締切りに間に合わない可能性があるため、余裕をもって申請することをオススメします。
また補助金だけで足りない部分については、金融機関からの融資のタイミングも調整が必要です。
ものづくり補助金事業計画書の作り方

ものづくり補助金の採択を勝ち取るためには、質の高い事業計画書の作成が最も重要です。審査員の心を掴み、「この事業なら成功し、国が支援する価値がある」と思わせる計画書を目指しましょう。
基本要件の徹底理解
まず、以下の基本要件を全て満たす補助事業終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たすこと。
これらの要件は単なる努力目標ではなく、特に賃金に関する要件は未達の場合に補助金返還義務が生じるため、実現可能な計画策定が必須です。
グローバル枠特有の要件
グローバル枠の申請をする場合は、「2.5.1 基本要件」に加え、以下のグローバル要件①~④のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携することが必要です。
それぞれ詳細な要件や提出書類(海外子会社の事業概要・財務諸表、株主構成が分かる資料、海外市場調査報告書、共同研究契約書案など)が定められていますので、該当する場合は公募要領を精査してください。
これらの書類は準備が簡単なものではないため、よりいっそう早めに着手することが求められます。
補助事業の実施場所
「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。
申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。
特例措置の要件
補助上限額の引き上げや補助率の優遇を受けられる特例措置を利用する場合、追加の要件を満たす必要があります。
魅力的ではありますが、企業の状況によってはかなりハードルが高い条件となるため、無理に目指すことは控えた方が良いでしょう。
事業計画書作成のポイント
電子申請システムへの直接入力形式となった事業計画書ですが、その内容は依然として採択の最重要ポイントです。以下に作成のポイントを記載しておくので、ぜひ参考にしてください。
まず計画書作成の最初のステップとして、適切な現状分析が不可欠となります。
マクロとミクロ両方の視点でとらえた外部環境と、自社の強みと経営資源を中心とした内部環境についてSWOT分析等で整理します。そして現状の課題を明確にして、解決策として新規事業があることを示しましょう。
企業全体の成長戦略における新規事業の位置づけをわかりやすく表し、経営理念や中長期ビジョンとの関連性も記述することが望ましいです。進出する市場がどれだけ魅力的であるか、といった点も盛り込むとよいでしょう。
またこの補助金では革新性が重要視されるため、他社にはない独自性や、事業の新規性を強くアピールすることが効果的です。
どのように取り組んでいくかも、現実的かつ具体的に示すことが望ましいでしょう。
図、グラフ、画像などを使うとわかりやすいですが、A4サイズ3ページ以内のPDFという制限があります。少々扱いづらいですが、限られたスペースを最大限有効に活用してください。
以上のような要素を意識しつつ、「新規事業においてこの補助金がなぜ必要不可欠なのか」という点について、説得力を持たせた内容であることが重要と考えられます。
こういった計画書作成の面については、補助金コンサルタントをはじめとして、必要に応じて経営コンサルタントを活用することが効果的となってきます。

ものづくり補助金の審査項目と評価ポイント

提出された申請書類等に基づき、事務局にて形式要件の適格性確認を行います。
また外部有識者が「書面審査項目・加点項目・減点項目」に沿って、経営力、事業性、実現可能性等の審査を行います。場合によっては口頭審査も実施されることがあります。
書面審査項目
口頭審査
- 一定の基準を満たした事業者を対象に、外部有識者による審査を行います。
- オンライン(Zoom等)にて30分程度の予定で実施。
- 申請事業者自身(法人代表者)1名が対応。外部コンサルタント等の同席は一切認めません。
- カメラオン、音声録音、本人確認あり。
加点項目と減点項目
加点項目は最大6項目まで申請可能。採択の可能性を少しでも高めるために、加点項目は積極的に取得し、減点項目は確実に避けるようにしましょう。
補助金コンサルタントによって諸説あるものの、加点数が4つ以上あると、採択率が向上するとも言われています。
主な加点項目
主な減点項目
過去の採択率の傾向と対策
ものづくり補助金の採択率は、公募回によって大きく変動しています。
第16次までは50%前後で安定していたのですが、17次では29.4%、18次では35.8%と急激に難化してしまいました。
19次以降はもう少し上がると予想されていますが、結果が出てみないとわからないところです。
また従業員数5人以下の場合の採択率がやや低い傾向にあり、750万~1000万円の申請額の採択率が高いと言われています。
全体の採択率はさておき、自社が採択されるためには、やはり事業計画書の質が重要です。
加点項目を可能な限り取得することと、賃上げへの積極的な姿勢を示すことも、計画書の評価を高めることにつながります。
ものづくり補助金採択後に必要なこと

無事に採択された後も、補助金を受け取るまでにはいくつかのステップを越えなければなりません。
さらに実績報告をはじめ、補助事業者として求められる義務も発生します。
これらに伴って発生する様々な手続きが煩雑で、経営にかける時間が圧迫されてしまうことから、補助金申請を敬遠される企業も増えているように感じられます。
採択後の主な流れ
補助事業者の義務
補助金コンサルタント活用のポイント

ものづくり補助金は新たな挑戦に取り組む中小企業にとって、大きな飛躍のチャンスとなり得ます。
しかしながら見てきたように、採択率は決して高くなく、ルールが複雑で専門的な知識も要求されるため、申請に取り組む余裕が無い中小企業様も多いでしょう。
そこで活用したいのが、申請をサポートしている補助金コンサルタントの存在です。
補助金申請にコンサルタントを活用する中小企業が増えていることから、近年は申請される計画書全体のレベルが上がっており、自社だけで取り組むハードルがますます上がっているものと考えられます。
とはいえコンサルタントの導入にあたっては、以下のような点に注意してください。
まず補助金の申請サポートには、特別な資格なども不要なため、様々な業種から「自称コンサルタント」が参入してきています。
その中には依頼された企業の状況を考えず、補助金を獲得することだけが目的となり、獲得した後のことはまったく考慮せず、無謀な計画を作成してしまうコンサルタントも存在するのが実情です。
そうなれば仮に採択されたとしても、計画を達成するためにかなりの負担を強いられることもあり、経営に致命的な悪影響を及ぼす可能性すらあるのです。
また補助金コンサルタントの報酬の目安としては、着手金+成功報酬といった形で提示されることが多いです。
このうち成功報酬は、決定となった補助金額のうち一定の割合として設定されますが、この割合を高額に請求する業者が存在しており、公式からも注意喚起が出ています。(以下参照)
ものづくり補助金に限らず、補助金コンサルタントの成功報酬は10%~15%程度が相場かと思われますが、もし20%を超えてくるような条件を提示されたら、警戒した方が良いかもしれません。
確かに補助金コンサルタントをうまく活用すれば、採択率を上げるだけでなく、申請にかかる時間や費用を節約できます。
悪徳業者が存在することを認識しつつ、良きパートナーとなるコンサルタントを見つけてください。
事業計画書作成支援者の選び方と注意点(公募要領より)
- 認定経営革新等支援機関や専門家の支援を受ける場合には、事業者による事業の遂行や計画達成を企図しない不適切な業者等に注意してください。
- 不適切な行為の例: 作業等にかかる実際のコストと乖離した高額な成功報酬等を申請者に請求する、補助金申請代行を主たるサービスとし、申請者が理解しない内容のまま申請する、料金体系・支援内容・支援期間が明らかでない契約を締結する等。
- 料金体系、支援内容、支援期間が明確で、事業者の主体性を尊重してくれる専門家を選びましょう。
公的支援機関の活用
会社全体の事業計画の策定支援等は、よろず支援拠点等の公的支援機関でも相談窓口がございますので、利用を検討ください。
申請支援者・代理人の関与に関するルール
前述の通り、申請者本人が計画内容を理解し、「丸投げ」は禁止されています。
認定経営革新等支援機関等の外部支援を受けている場合には、事業計画書作成支援者の名称、支援内容、報酬、契約期間を必ず申告(電子申請システムへ入力)してください。
信頼できる補助金コンサルタントは、申請手続きをスムーズに進め、採択の可能性を高めるための強力なパートナーとなり得ます。
しかしながら、あくまで事業の主体は申請者自身であることを忘れず、専門家と二人三脚で取り組む姿勢が大切です。
補助金採択の後も視野に入れたコンサルタント活用を
ものづくり補助金を検討されている事業者様へ、最後にもう一度我々のサービスを紹介させてください。
エクト経営コンサルティングは、採択率80%以上の実績を誇る補助金申請のプロ集団とも提携しており、貴社に最適な専門家を選定してご紹介できるのを特徴としています。
補助金申請のお手伝いについては、企業様のご要望に合わせて必要な部分だけをサポートすることが可能。報酬も柔軟に対応できるため、他の補助金コンサルタントと比べると、申請にかかる費用を安価に抑えられる可能性も大きいです。
また我々は補助金申請だけでなく、「中小企業専門の経営相談所」として、経営コンサルタントの国家資格を持つ専門家を集めて活動しています。
そのため補助金の申請だけで終わらず、採択された後にどのように事業を進めていくかなど、ご要望に応じて事業における様々なサポートが可能。
補助金をもらうことだけで終わらず、補助金を活用してどのように経営を改善するかという視点で、幅広いお手伝いができることこそ私たちの強みと考えています。
ものづくり補助金の申請についても、最適な専門家によるお試し無料相談をご提供中です。
信頼できる補助金コンサルタントを探している経営者様や、採択後の事業についても本気でお考えの経営者様は、以下のボタンから詳細をご確認ください。
【着手金0円プラン新登場、詳しくは以下のボタンから】
よくある質問
無料相談&お問い合わせはこちら
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

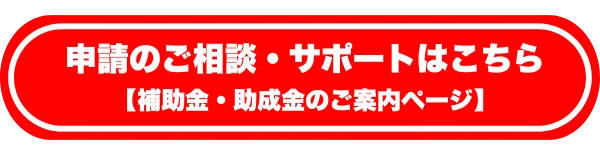
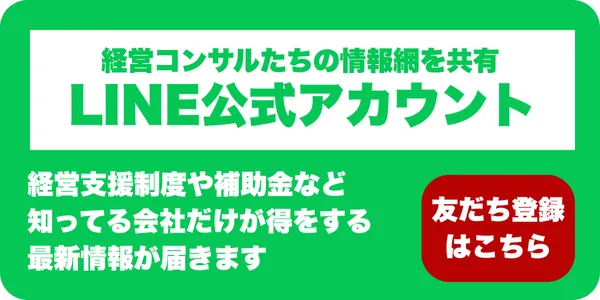













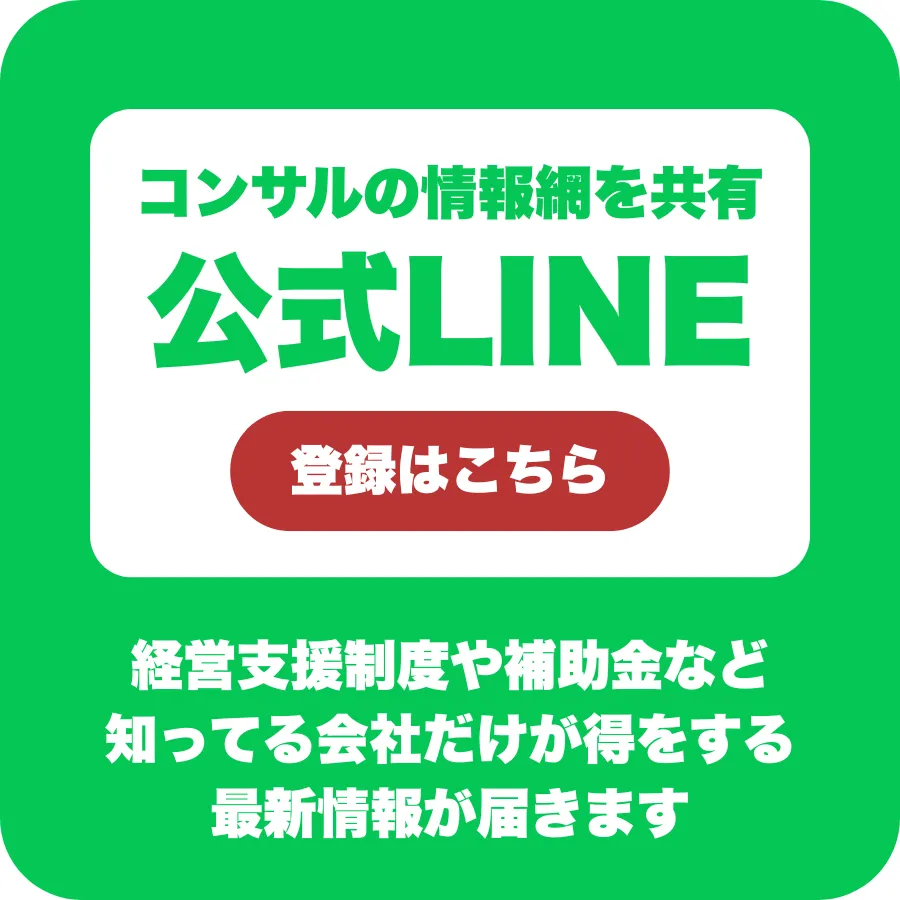












この記事へのコメントはありません。