中小企業が資金繰りを改善する方法12選!現金に余裕の無い経営は危険です

経営者の皆様、資金繰りについてお悩みではないですか?
もしくは現金がかなり減っていることに気づいてるけど、日々の業務に追われて手が回らないし、「まぁ大丈夫だろう」と対策を先送りにしていないでしょうか。
経営を安定させたいのであれば、現金には常に余裕がある状態が望ましいです。そして資金繰りを改善するには、早い段階で着手するほど成功しやすく、遅くなるほど難易度が上がってくる傾向にあります。
しかしながら適切な対策を怠ってしまい、「もっと早く改善していれば…」と後悔される事業者様が後を経たないのが実情です。
そこでこの記事では、資金繰りについてお悩みの中小企業様に向けて、改善のためにできる施策を12個集めてみました。資金繰りに不安を覚えている事業者様に向けて、経済産業省登録の中小企業診断士が、具体的な方法をわかりやすくアドバイスしていきます。
資金繰りの余計な心配を取り除き、安定した経営を実現してさらなる成長を目指すため、早期改善に取り組んでいきましょう。
目次
中小企業における資金繰り表の重要性
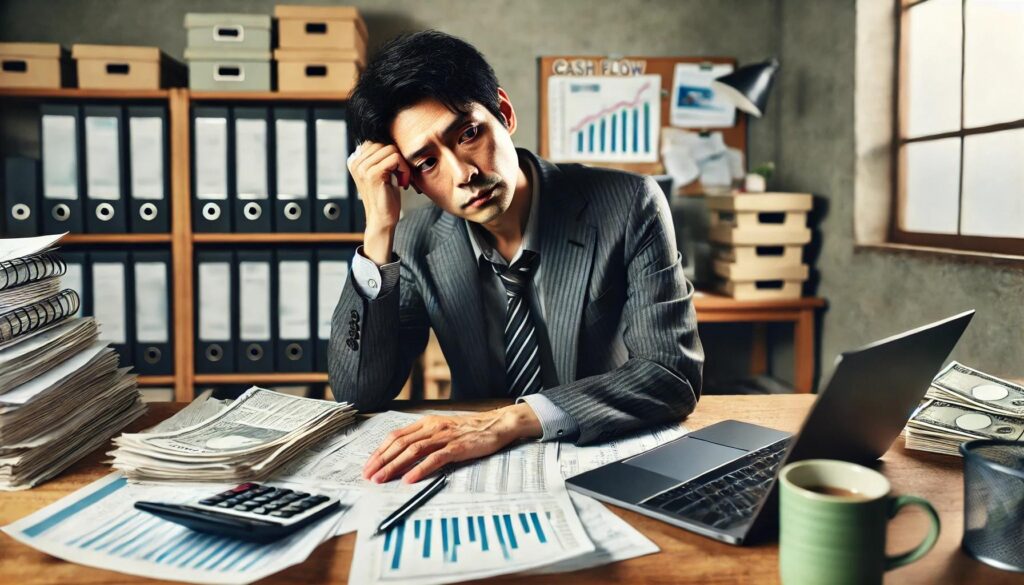
具体的な改善策の前に、「資金繰り表」の重要性についてだけ説明させてください。
御社では資金繰り表を作成しているでしょうか。もしまだであれば、この記事をきっかけに作成することを強くおすすめします。
資金繰り表を簡単に言うと、入ってくるお金と出ていくお金の予測をまとめた表です。
この表があることによって、現金の流れを「見える化」することができ、収支のバランスを正確に把握できるようになります。そしていつ資金が不足するのか、どれくらい余裕があるのかを事前に把握し、適切なタイミングでの資金調達が実施できるようになります。
後ほど詳しくお伝えしますが、普段から資金繰り表を作っておくことで、金融機関に融資を交渉する時にも役立ちます。さらに無駄な支出の削減、資金の効率的な運用にもつながり、利益率の向上にも寄与します。
逆に資金繰り表を作っていないと、短期的な現金不足が発生しやすくなり、支払遅延や信用低下といった問題が起こるリスクが高まります。
このように資金繰り表は、企業を経営する上で必要不可欠なものです。にもかかわらず、資金繰り表を作成している中小企業様はそれほど多くありません。
自社で作るのが難しければコンサルタントなどの力を借り、資金繰り表で現状を正しく把握することから始めましょう。

金融機関からの融資で資金繰りを改善する

最初にご紹介する改善方法が、ズバリ「金融機関からの融資」です。
中小企業が資金調達をする際に最も一般的な手段といえば、金融機関からお金を借りる融資ということになるでしょう。資金繰りに不安がある際も、融資を受けることで解決できると望ましいのですが、一筋縄ではいかない部分が多いのも事実です。
そこで金融機関からの融資については、他の改善方法よりも詳しく解説していきたいと思います。
金融機関の種類と特徴
まずは金融機関の基礎知識から確認していきましょう。一般的に企業が融資を受けられる先は、銀行、信用金庫、信用組合、政府系金融機関に分けられます。
このうち政府系金融機関というのは、その名のとおり国が運営している金融機関のことを指します。代表的なのが日本政策金融公庫で、中小企業がお世話になる政府系金融機関と言えばたいていココになります。
なお商工中金(商工組合中央金庫)も政府系金融機関の一つでしたが、政府が保有している株式が売却され、2025年に完全民営化することになりました。
銀行、信用金庫、信用組合は、それぞれ運営の仕組みが異なるものの、どれも民間で運営されている金融機関です。融資の基準やスタンスは、それぞれの金融機関の方針によって異なる部分があり、同じ金融機関でも支店長が変わるだけで変わる場合もあります。
銀行を大まかに分類すると、全国に支店のある大規模な都市銀行と、地域密着型の地方銀行に分けられます。メガバンクと呼ばれる巨大な銀行が代表的ですが、一般的には規模の大きな銀行ほど、中小企業を積極的に相手にしないことが多いようです。
信用金庫は地域貢献のために運営されている金融機関です。実は規模の差が大きく、広範囲に支店を持つ「メガ信金」もあったりします。基本的には。なお信用金庫と信用組合は、厳密に言うと別物なのですが、同じような位置づけと考えて問題ありません。
融資を受けやすいタイミングとは
日本政策金融公庫は、中小企業のための独自の融資制度を展開しています。
融資を受けるハードルが民間金融機関よりも低い場合が多く、中小企業にとって頼りになる存在です。とはいえ貸付にあたっての審査はしっかりと実施され、基準に満たなければ容赦なく落とされますし、場合によっては金利が割高になることもあります。
一方で民間金融機関のうち、銀行は一般企業と同じく営利目的の企業であり、自分たちの利益をきちんと守っていく使命があります。信用金庫と信用組合は非営利団体ではありますが、ボランティア団体というわけではなく、運営の原資となっているのは多くの人から預かっているお金です。
いずれにしても民間金融機関は、資金繰りが厳しい企業に対して、簡単にお金を貸してはくれません。
経営状況が厳しくなったり、資金繰りが危うくなってから借りようとしても、ハードルがかなり高くなることが想定されます。こういった傾向は、基本的には政府系金融機関においても同様です。
つまり融資がスムーズに受けられるのは、経営が順調で安定している時だけなのです。
「銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に取り上げる」というのは有名な例え話ですが、融資をする側の銀行の身になってみれば、返ってこなそうな人にお金を貸したくないのは当然です。
企業としては、晴れているうちに必要な傘(お金)を借りておかなくてはなりません。
そこで資金繰り表をしっかり作成しておけば、精度の高い天気予報になります。資金繰り表を日々チェックしておくと、将来現金が不足しそうなタイミングがわかるので、危うくなる前に金融機関へ追加融資の相談ができるというわけです。
念の為につけ加えておくと、金融機関の融資担当の方々はプロなので、経営に何か問題があることを高確率で見抜きます。決算書の数字をいじったり、不都合な事実を隠したりすることは、信頼を失って逆効果になる可能性がありますので、やめておいた方がよいでしょう。
融資に必要な保証について
企業が融資を受ける際には、万が一返せなかった時の保証が求められます。
もちろん保証が必要ないこともあるのですが、一部の特別な融資制度の場合を除いて、金融機関と深いつき合いがあり、なおかつ経営状況が良好であるという前提が必要です。そのため多くの場合、融資の際には何らかの保証条件が設定されると考えておきましょう。
定番となる保証形態の一つとして、「経営者保証」があります。
これは社長が融資の連帯保証人になるということを意味しており、日本では長らく経営者保証をつけるのが当たり前でした。しかしながら近年では国が主導となって、なるべく経営者保証を外すような動きが活発となっています。
起業を増やすために心理的負担を下げたいというのが理由ですが、既に受けている融資から経営者保証を外すという交渉も、以前よりはしやすくなっているようです。実際のところ社長が連帯保証人になったとしても、いざ会社が倒産したとなった際に、負債を全額回収するのは難しいようですね。
同様に融資の際には、「信用保証協会」の利用を求められることが多いです。
詳細については省略しますが、信用保証協会は返済できなくなった時に肩代わりしてくれる公的機関であり、多くの企業が融資を受ける際に使っています。信用保証協会を使った融資は「保証協会付き融資」、使わない融資は「プロパー融資」などと呼ばれることが一般的です。
信用保証協会を利用する場合は、利子とは別に保証料が発生します。融資を受ける企業側にとっては、この分が余計なコストになってしまうのがデメリットです。その代わり、金融機関としては取りっぱぐれのリスクが減るので、融資のハードル自体を下げることができます。
勘違いしがちなのが、もしもの時に金融機関に返済しなくていいとはいえ、肩代わりした信用保証協会には返済が必要という点です。また保証協会による審査もあるのですが、もしこの審査に落ちてしまえば、当然ながら融資の話自体が無くなってしまうという可能性もあります。
その他にも自宅をはじめ不動産を担保として設定したり、役員などの共同経営者が保証人になるなど、融資に伴う保証には様々な形態が存在しています。
既にピンチの場合はどうする?
「資金繰りが厳しい」と言っても程度の差がありますが、基本的には厳しれば厳しいほど融資を受けられる確率は低下します。
もし借りられたとしても、金利や担保などの面でかなりの悪条件になってしまうかもしれません。もはや支払いが危ういような場合は、残念ながら追加で融資を受けるのは難しい可能性が高いです。
そういった状況であっても、現在の返済を一時的に止めてもらう「リスケ」は相談することができます。金融機関としても、貸した企業が倒産してお金が返ってこなくなるよりは、返済をストップする間に経営を立て直し、将来的に返してもらった方が良いはずです。
リスケはメインで取引している金融機関だけでなく、現在借りているすべての金融機関からの同意が必要となります。とはいえ多くの場合、メインの銀行の意向に他の銀行が従うパターンが多いです。
ここで改善の見込みが無いと判断されてしまうと、リスケが拒否されるという可能性もあります。
そうならないためには、「これからどうやって改善していくか」という説得力のある計画書を作成し、金融機関に納得してもらうことが必要です。とはいえ計画書をいきなり作れと言われても、多くの方は困ってしまうと思います。
我々のような中小企業診断士に依頼すると、現実的かつ合理的な経営改善計画書を作成できます。また現状における最善のアクションをアドバイスしたり、銀行との交渉の場に同席できる場合もあるなど、外部のコンサルタントを頼ることは多くのメリットがあります。
「誰を頼っていいかわからない」という場合は、ひとまず右下の無料相談ボタンからお問い合わせください。
融資以外の資金調達で資金繰りを改善する
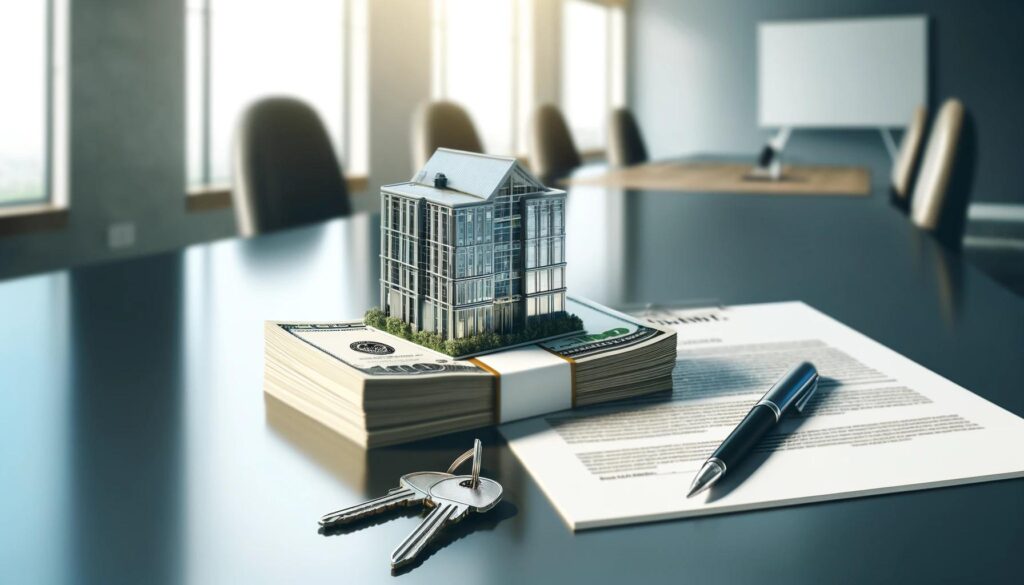
融資を受けたり自己資金を投入する以外にも、資金調達を実現する手段はいくつかあります。いずれも何らかのリスクを伴うため、実施にあたっては慎重に検討しましょう。
資産の売却
企業で保有している資産を売却し、そのお金を資金繰りの足しにするという方法です。
まずは保有する資産の全体像を把握するため、不動産、設備、車両などのリストアップを行いましょう。その中で使っていないもの、事業に直接必要のないもの、運用効率が低下しているものなどから、手放すにあっての優先順位を決めていきます。
なお資産の売却は、短期的な資金繰り改善には有効であるものの、一時的な対策にしかならないことも事実です。売却によって得た資金を活用し、根本的な部分の改善を進めることで、本質的な資金繰りの安定化を図っていく必要があります。
なお資産売却を進める際には、できれば不動産業者や税理士、弁護士など、その分野の専門家に相談することが望ましいです。資産を適正に評価してもらえれば、資金をより多く獲得できる可能性がありますし、プロに任せた方が何かとリスクを抑えられます。

ファクタリング
ファクタリングというのは、専門の「ファクタリング会社」に売掛金を売却し、その対価として現金を受け取るという資金調達手段です。あまり聞き慣れないので不安に感じてしまうかも知れませんが、誰もが知るメガバンクのグループ会社が運営しているファクタリング会社もあります。
売掛金を早期に現金化しつつ、バランスシート上では負債として扱われないため、財務面での健全性を保ちながら資金調達を実施できるのが大きなメリットです。さらに信用力が十分でない中小企業にとっても、比較的利用しやすいという利点も挙げられます。
一方でファクタリング会社へ支払う手数料が発生するため、調達額が売掛金の額面金額より少なくなる点には注意が必要です。また依頼するファクタリング会社の信頼性は十分に確認しつつ、契約内容や条件についてよく理解することが重要となります。
またファクタリングはあくまで緊急時の資金調達方法であり、この手法に依存しすぎないように注意しつつ、資金繰り改善のための財務体質強化も進めていきましょう。
補助金・助成金
国や公的機関によって提供される補助金や助成金は、中小企業の資金繰りを改善する上で強力なサポートとなる可能性があります。
とはいえ「資金繰り改善補助金」のような名称で、ストレートにお金だけくれるようなものは滅多にありません。たいていの場合は、販路拡大や生産性向上を目的に新たな取り組みを実施し、それに伴ってお金を補助してもらうという前提となっています。
補助金・助成金のルール上では、申請にあたり多くの書類を用意する必要があります。その中でも事業者様にとって、とりわけ厄介なのが計画書の類だと思います。計画書の中では、3~5年先までの数値計画を作成したり、従業員の賃上げをはじめ一定の条件が求められる場合もあります。
さらに申請してからお金がもらえるまで、かなりの時間がかかるという点も注意が必要です。そのため資金繰りの改善手段という意味では、ある程度長期的な視点で取り組む際に限定されます。
補助金・助成金の計画書作成や申請代行についても、中小企業診断士をはじめとした専門家に頼むとスムーズに進むでしょう。

消費者金融は本当の最終手段に
消費者金融は、本記事で勧めている資金繰り改善手段には含みません。
経営に必要な資金を確保するため、消費者金融に手を出してしまう社長様もいらっしゃるのですが、どうしてもやむを得ない状況になるまで控えてください。
まず消費者金融の金利は、企業の受ける融資と比べて圧倒的に高いため、返済の負担が大幅に増大します。たとえ短期的な資金調達であっても、その利息によって経営が苦しくなり、立て直せたはずの計画が頓挫してしまう可能性があります。
さらに消費者金融の利用履歴は信用情報に記録されるため、今後どこかの金融機関から融資を受ける際、その審査に影響を与える可能性があります。つまるところ、将来的な資金調達に悪影響を与えるというリスクも発生するのです。
そもそも消費者金融は個人向けの資金調達手段であり、事業資金として利用するのは適切ではありません。個人と事業の資金が混同してしまい、財務状況の正確な把握が難しくなると、事業全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
以上のような理由から、消費者金融は可能な限り利用しないことをおすすめしています。

取引先との条件交渉で資金繰りを改善する

販売先または仕入先と交渉することで、資金繰りを安定化させようというアプローチです。直近でまとまった資金を確保するというよりは、長期的な視点での改善施策となります。
売掛金の回収条件を見直す
売掛金の回収スピードを早める、つまり売上が現金化できるまでの期間を短縮することで、資金繰りを改善しようという方法です。
これを実現するためには、取引先との支払い条件を見直すことが必要です。例えば支払いサイトが60日であるところ、30日に短縮してもらえれば、その分だけ早期に現金を確保できることになります。
「そんなことしたら取引を停止されてしまう!」とあきらめる前に、ぜひ一度真剣に考えてみてください。これまでの取引実績を強調し、場合によっては自社の事情も伝えて、信頼を失わないよう誠実に交渉すれば、検討してくれる可能性がゼロとは言い切れません。
支払いを早めてもらう代わりに、いくらか値引きをするという条件も提案してみる価値があります。数%でも割引条件があれば、相手にとってもメリットがあり、必ずしも悪い話とは受け取られないはずです。
また自社でオンライン決済を導入し、これを機に回収条件を見直してほしいという交渉の切り口も考えられます。ついでに自社の経理業務が効率化できる他、顧客にとっても支払いの手間を削減するメリットにつながるかもしれません。
なおこういった決済・受発注関連ITツールの導入は、一部費用を補助金で賄える可能性もあります。
買掛金の支払条件を見直す
商品や原材料の仕入先と交渉して、支払い期間を延長してもらえないか交渉するという方法です。
長期的な取引があり、一定の信頼関係が構築できている場合は、そこを強調して条件変更を相談します。相手側が弱い立場にあることも多いと思いますので、先方の状況も尊重しつつ、信頼を失わない交渉姿勢が大切です。
支払サイトを延長してもらう代わりに、発注量の増加や長期契約を提案するのも一案です。資金に余裕のある相手であれば、むしろ喜ばれる可能性もあります。
ただどんな交渉をするにしても、「あそこの会社は危ない」なんて噂が立たないように、交渉の際の言い回しについては細心の注意を払いましょう。
また新規の仕入先を新たに開拓し、複数の仕入先を持っておくというのは、資金繰りだけでなく経営全体の安定化につながる方法です。新規仕入先の支払条件が柔軟であれば、それを材料に既存の仕入先と交渉することもできるはずです。
売上を拡大して資金繰りを改善する

シンプルに売上を上げることで、資金繰りを改善しようという考えです。そう簡単にはいかないかもしれませんが、しっかりと利益が残るのであれば最善策となります。
値上げ
現在の商品・サービスを値上げして収益性を高めれば、資金繰りの改善に大いに貢献するはずです。
とはいえ今後の取引に影響したり、売れ行きに悪影響を与える場合もあるため、値上げというものは慎重に検討しなくてはなりません。競合他社や物価などを参考に、顧客が納得できる範囲を想定し、妥当な値上げ幅を決定する必要があります。
顧客に値上げを受け入れてもらいやすくするためには、実行する時期も重要です。年度の変わり目、新製品のリリース時期、季節需要期など、顧客にとって影響が最小限にできるタイミングを図ります。状況によっては、段階的に値上げを進めるというのも考えた方がよいでしょう。
値上げについて顧客への説明が求められる場合は、経緯や理由を分かりやすく伝えると共に、品質維持や付加価値といった面を訴求できるとよいです。できれば値上げと同時に、商品の付加価値を向上させると、顧客に納得してもらえる可能性も高まるはずです。
また値上げ実施後に必要なアクションとして、収益の変化や顧客の反応についてアンテナを強化し、その影響をしっかりと見極めていきましょう。
新商品の投入
新商品や新サービスを投入し、純粋に売上を積み増して資金繰りを改善します。
早期に資金繰りを改善したいという状況であれば、短期間で多くの売上を獲得するため、思い切った販売戦略をとりたくなるかもしれません。しかしながら、軽率にスタートするのは危険です。一か八かで結局売れなかった場合、余計に資金繰りが悪化する可能性もあります。
そこでまずは徹底的な市場調査を行い、商品やサービスが顧客に受け入れられるものであるか、収益面で採算が取れるものであるか、冷静にじっくりと分析しましょう。勝算があると判断できてから、販売に向けて迅速に準備を進めるのが理想的な流れです。
またクラウドファンディングを活用すれば、テスト販売と同時に資金調達を得ることが可能です。とはいえこちらも簡単ではありませんので、前段階での慎重な市場調査は不可欠となります。
新規市場・新規事業への進出
新規市場や新規事業への進出は、資金繰りを改善する大きなチャンスとなる一方、リスクも大きいことを理解しておく必要があります。
新天地でビジネスを展開するとなれば、当然ながら失敗する可能性も高くなるためです。資金繰りに問題を抱えているような状況だと、小さな失敗が既存事業にも影響を与えかねないため、命取りとなってしまうかもしれません。
それでも進出をあきらめられない場合は、やはり慎重に計画を立てて検討しましょう。徹底的な市場調査と分析を実施し、成功の見込みがあるかを冷静に判断してください。競合状況を分析した結果、どのように差別化して戦うかを明確にできないと、進出先で成功することは厳しいかもしれません。
新たな投資が必要なことも多いと思いますが、そもそも資金繰り改善のためであれば、大きな投資ができる余裕はあまりないはずです。できればスモールスタートで事業を開始し、テスト販売を通じて段階的に拡大していくと、リスクを抑えながらの展開が可能となります。
もしインターネットを利用した事業展開に力を入れていない場合は、比較的低リスクで新たな市場を見つけられるかもしれません。
パソコンやスマホを通して実施するデジタルマーケティング施策なら、あまり大きな投資をすることなく展開できる可能性があるためです。例えばネットショップを開店すれば、高額な設備や機械を投入することなく、商品の販路が全国に広がります。
もちろんネットショップ(ECサイト)も一筋縄ではいきませんが、我々は中小企業のネットショップ開店支援も得意としています。興味があれば、こちらの記事も読んでみてください。
コスト削減によって資金繰りを改善する

コスト削減のためには、現状を詳細に把握することが重要です。まずは全ての費用を固定費と変動費に分けて、それぞれを細かく整理するところから始めましょう。
不要なコストの見直し
現在発生している費用をリストアップして、削減のための優先順位を設定してみましょう。
そこで維持費の高い資産、使ってないのに契約しているサービス、何だかよくわからない費用…など、精査した上で明らかに不要なコストが出てきたら、優先的に削減対象となるはずです。
とはいえ中小企業においては、日頃からコスト削減に努めている事業者様も多く、無駄遣いなんてほとんど無いという場合も多いと思います。そこでさらに一歩踏み込んで、「これは本当に必要か」を社内全体で議論し、削減できる部分を徹底的に洗い出してみてはいかがでしょうか。
例えば賃料、維持費、管理費といった属性のコストについては、契約条件を交渉したり、他の業者に乗り換えることで削減できる可能性があります。
さらに月額制などのサブスクリプションによる料金体系のサービスは、欠かせなければ解約までいかなくとも、もう少し安いプランに変更するという選択肢があるかもしれません。
コスト削減時の注意点として、本当に必要な費用まで削減しないように注意しましょう。自社の収益を生み出している源泉が何かをよく考え、それを維持・成長させるためにかかる必要経費を見極めるべきです。
こういった判断を含めて、無駄なコストの見極めは客観性も大切になるので、コンサルタントなど外部の視点を取り入れるのも有効な手段となります。
アウトソーシングの活用
従業員が辞めてしまうのは寂しいものですが、一方で固定費削減のチャンスという側面もあります。
退職するスタッフの担当している業務について、この機会にアウトソーシング(外注化)を検討してみてはいかがでしょうか。自社で新たに従業員を雇うよりも、人件費が安上がりになる可能性は大いにありますし、それでいて業務のクオリティが高くなる可能性もあります。
雇用というものは、大切な人財を獲得できる手段ではありますが、近年では多大なリスクがつきまとうようになっています。
もし問題のある人を採用してしまうと、トラブルばかり起こしていても簡単にクビを切れないどころか、過剰にハラスメントを主張されて訴えられる可能性すらあります。さらに雇用の場合、採用や社会保険などに大きなコストがかかるのを考えると、アウトソーシングの方が何かとメリットが大きいのではないでしょうか。
昨今は人手不足が深刻な社会問題となり、今後も改善の見通しが無いという中で、アウトソーシングを提供するサービスが充実してきています。
誰でもできる単純作業、専門的スキルが必要な作業、プロジェクトマネージャーなど、今までの外注化といえばこういった業務が定番でしたが、今後は販売戦略や財務戦略の策定といった上流工程においても、アウトソーシングの活用がますます重要となっていくでしょう。
業務効率化
生産性の向上が叫ばれるようになって久しいですが、中小企業ではなかなか進んでいないのが現状だと思います。
もしこういった取り組みが不十分であれば、資金繰り改善のためのコスト削減を目指すにあたり、業務の効率化についても見直してみてはいかがでしょうか。特に日々のルーティンワークに限っては、もしかしたらアウトソーシングすら必要なくなるかもしれません。
例えば事務作業においては、ペーパーレス化や自動化などの様々なITツールを活用すると、事務コストを大幅に削減できるかもしれません。
また在庫管理についても、改善が大きく期待できる部分です。専用のITツールを導入して、在庫回転率を向上させることにより、資金繰りが大幅に楽になる可能性があります。
さらに製造業では、エネルギーや資材の使用量を削減できる省エネ設備を導入することで、コストを大きく削減できるだけでなく、SDGsへの取り組みが評価される副次効果も期待できます。
こういった業務効率化を目的とした経費についても、補助金が活用できる場合がとても多いです。しかしながらルールが複雑で、企業によって要件も異なるため、自社だけで申請するのが難しいことも多いでしょう。
補助金を活用したコスト削減に興味のある方は、個別に最適な方法などもご提案できますので、右下の「詳しく見る」ボタンからお気軽にご連絡ください。
資金繰りの改善について相談できる場所

現金に余裕の無い経営状態はリスクが大きく、金融機関や調査会社からも「危険」と判断されます。
そして資金繰りが厳しくなればなるほど、改善が難しくなってしまう傾向にあります。
本来は苦しくなる前に対策が必要なのですが、今からでも手遅れになる前に、できるかぎり早めの改善に取り組みましょう。もし「来月の請求が支払えない」など、直近の資金繰りに支障をきたしている状態であれば、すぐにでも行動が必要かもしれません。
資金繰りを改善する上では、中小企業診断士をはじめとしたコンサルタントの力を借りるのが近道です。
もちろん自社で解決できればベストではありますが、資金繰り関連の支援経験が豊富なコンサルタントであれば、もっと望ましい方法を提案できる可能性があります。
また資金関連の問題というのは、従業員に相談しづらい場合が多いはずです。経営者様だけで孤独に悩んでいると、どうしても視野が狭くなりがちなので、支援者の存在が心の支えにもなってくれるでしょう。
エクト経営コンサルティングでは、経済産業省登録の中小企業診断士を中心として、資金繰りに強いコンサルタントが貴社のご相談を承ります。
中小企業でも無理のないリーズナブルな費用で、事業者様の状況に応じた支援内容を提案し、柔軟にサービスを提供できるのが我々の強みです。
さらに資金繰りだけにとどまらず、例えば売上拡大や組織人事など、様々な専門分野を持ったコンサルタントによる経営全般のサポートが可能。
もしお悩みがあれば、以下よりお気軽にご相談をお待ちしております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

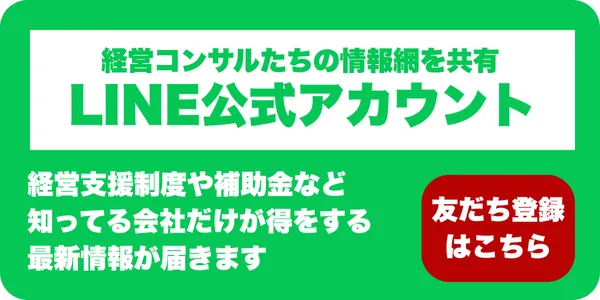














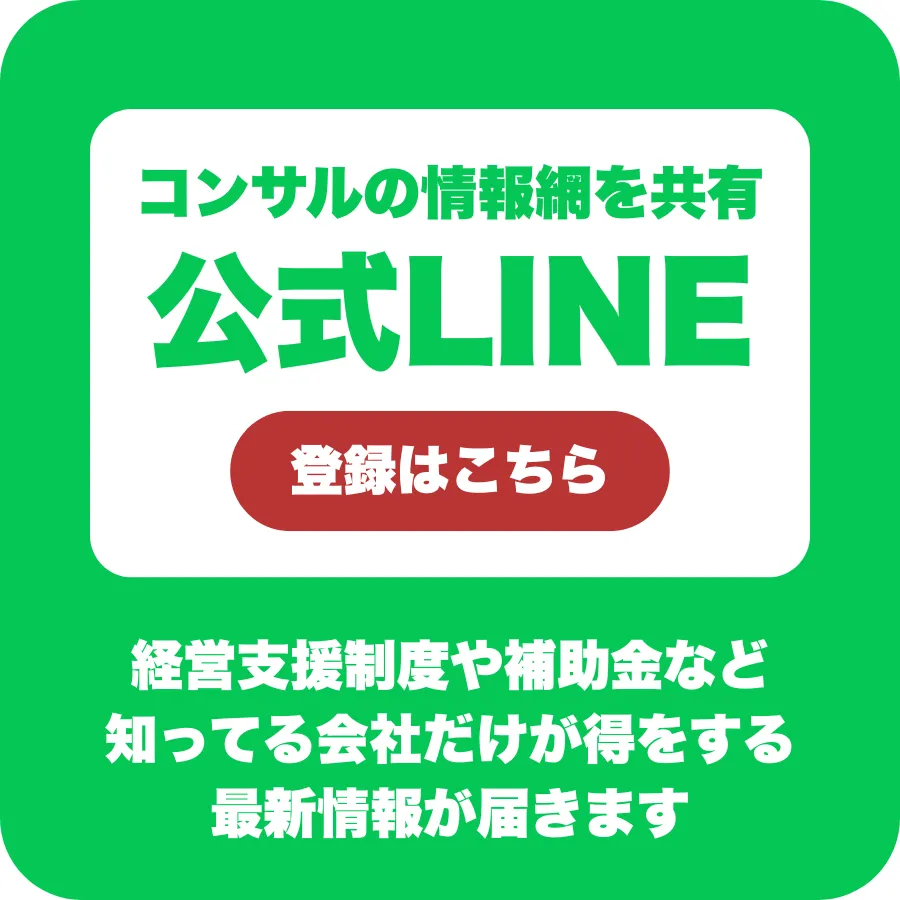











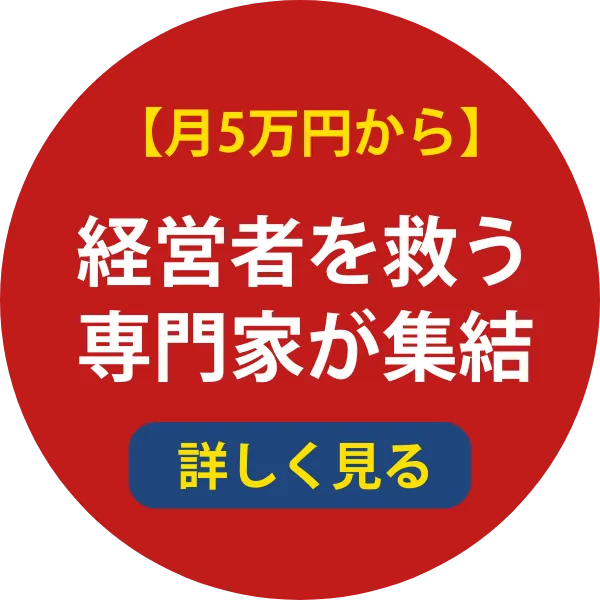
この記事へのコメントはありません。