【2026年版】中小企業省力化投資補助金の対象と申請方法、経営コンサルタントが徹底解説します

中小企業専門の経営相談所、エクト経営コンサルティングです。
「人手不足で事業が回らない!」
「生産性を上げたいけどお金がない!」
「従業員の給料を上げたくても余裕がない!」
最近はこのようなお声を、中小企業の経営者様から聞くことが多くなってきました。
そこで今回は、そんなお悩み解決の糸口になる中小企業省力化投資補助金をご紹介。
人手不足や生産性向上といった課題があり、「省力化」の設備導入を検討している中小企業に対して、設備の購入費用を国が補助してくれるという制度です。
実はこの補助金、2025年になって大幅にパワーアップされたことをご存知でしょうか。
2026年も継続されており、条件が合う企業にとって大きなチャンスなのですが、一方で制度が複雑になったため、よくわからないと感じている方も少なくないはずです。
そこで今回は、経営コンサルタントが制度の概要をできる限りわかりやすく解説。
中小企業省力化投資補助金の対象になる企業、対象になる設備、獲得するにはどうしたらよいかなどといった点について、要点をまとめたガイドとしてお届けします。
省力化によって事業の未来を切り開くために、この記事で最初の一歩を踏み出しましょう!
他のコンサル会社と比べると、コスパが圧倒的に高いことがきっとお分かりになるはずなので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。
目次
【2026年1月速報】最新第5回、2026年2月から公募受付スタート予定
中小企業省力化投資補助事業(一般型)に関する情報です。
2025年12月19日、第5回公募の内容が公表されました。申請は2026年2月上旬に受付スタート、締切はその直後2月下旬という短期間となるようです。
「激アツ」な補助金という情報が広まっているため、今後は採択率が低下する可能性も大いにあります。今のうちから、早めに準備を進めて臨みましょう。
申請についてのお悩みや、サポートを必要とされている方は、こちらのフォームからお問い合わせください。
また2025年10月28日には、「承継等事業主体が変更となる場合の注意事項」が発表されています。
事業承継やM&Aを予定されている事業者様は、重要な注意点となるためよくご確認されることをお勧めします。
中小企業省力化投資補助金の採択結果
第3回公募の採択結果が明らかになりました。
申請数2,775のうち採択数は1,854、採択率は66.8%と、高い水準を保っていることが明らかになっています。
他の補助金は採択率が50%にも届かないものも多い中で、第1回で68.5%、第2回でも60.9%と、やはり驚異的な高水準という結果に終わっています。お伝えしてきたとおり、やはり2025年に狙い目な補助金の筆頭格と言えるでしょう。
採択率がこれほどまでに高い理由としては、やはり深刻化する人手不足が背景にあると考えられます。
中小企業の生産性向上が進まず、賃上げが物価上昇に追いついていないという実情を打開するため、この補助金が改善の起爆剤となるよう、国としては期待しているのでしょう。
採択の明暗を分けるポイント
これだけ高い採択率を誇る中でも、落ちる企業は落ちるという事実を忘れてはいけません。
これまでの結果を分析すると、採択されている企業にはいくつかの傾向が見られるようです。今後予定されている第5回以降の公募に向けて、ポイントを必ず押さえておきましょう。
計画書の完成度
中小企業省力化投資補助金においても、事業計画書の内容は採択に大きく影響すると考えられます。
そして事業計画の説得力を担保するのは、具体的な数値と言えます。本補助金の場合、以下の指標は審査における重要なポイントとなっています。
- 省力化指数: 導入する設備によって、どれだけの作業時間が削減されるのかを明確に数値化します。
- 労働生産性: 計画期間中に、従業員一人当たりの付加価値額がどう向上するのか。
- 投資回収期間: 設備投資が何年で回収できる見込みなのか。
これらの数値を「事業計画書その3」に正確に落とし込み、計画の実現可能性をアピールすることが採択への近道です。
加点項目で差をつける
ほぼ同点の事業計画が並んだ際、最後に勝敗を分けるのが「加点項目」となります。
具体例としては以下のような部分になりますが、聞き慣れないことも多いかと思うので、コンサルタントに一度相談することをおすすめします。
- 事業継続力強化計画(BCP)の認定
- 高水準の賃上げ計画の表明
- 成長加速化マッチングサービスへの登録
今後の見通しについて
これまでの高い採択率を見て、次回以降に申請が増加することが想定されます。検討されている中小企業様は、競争の激化に備えて今すぐにでも準備を始めてください。
すぐにできるアクションとしては、以下のようなものが挙げられます。
- GビズIDプライムアカウントの取得: 電子申請に必須のアカウントです。既に取得されている企業様は問題ありませんが、取得には2週間以上かかる場合もあるため、未取得の企業は最優先で手続きを進めてください。
- 専門家への相談: 書類作成の難易度は決して低くありません。自社だけで抱え込まず、コンサルタントの力を借りることも、採択への有効な一手となります。
- 情報収集の徹底: 公式サイトでは、採択された事業計画名の一覧や、対象となる製品カタログなどが随時更新されています。過去の採択事例から傾向を学び、自社の計画に活かしましょう。
人手不足はもはや避けられない経営課題ですが、ぜひこの機会に補助金を有効活用し、自社の生産性を高めることを検討してみてください。
本気で申請に取り組むのであれば、信頼のおける適切なコンサルタントを活用し、採択の可能性が高い計画書作成サポートを受けることをおすすめします。
数多くの補助金の採択実績を持つ専門家が、まずは複雑な制度の理解からお手伝いしますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
【着手金0円プラン新登場、詳しくは以下のボタンから】
中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助金は、その名のとおり「省力化」のために設置された補助金です。
労働力不足が社会問題となって久しいですが、そんな世の中ではできる限りの省力化、すなわち人の手をかけずに事業を運営していこうという取り組みが必要不可欠。
そこで国が企業の省力化投資を促進し、その結果として企業の付加価値額や生産性を向上させることで、賃上げにつなげることを目指しているのです。
制度上の大きな特徴が、「一般型」と「カタログ型」の2つに大きく分けられること。
どちらも基本的にはIoTやロボットをはじめ、生産性向上を後押しする設備導入が補助の対象となるものの、要件や対象となる設備、申請方法までが大きく異なってきます。
それぞれについては後述しますが、自社の状況に合わせて最適な型を選ぶことが、この補助金を活用するための大前提と言えるでしょう。
ちなみに中小企業省力化投資補助金が誕生したのは2024年、まだ歴史の浅い補助金であり、発表当初は多くの事業者から期待を集めていました。
しかし制度の詳細が公開されると、導入できる設備がかなり限定されており、あまりに実用性に乏しく使いづらいことが判明。
やがて中小企業から見向きもされないようになり、一時は我々コンサルタントの間でも、記憶から消えゆく存在になりかけたのです…。
そういった反省もあってか、2025年になって中小企業省力化投資補助金は大幅に強化され、充実した内容を伴ってリニューアルとなりました。
補助金全体の予算金額も3000億円と大きく、ここに来て再度大きな注目を集めており、今後は多くの事業者から申請が集まるものと予測しています。
他の補助金との違い
中小企業省力化投資補助金は、ものづくり補助金や中小企業新事業進出補助金など、他の有名な補助金としばしば比較されることがあります。
確かに一部は重複するところもありますが、補助金はそれぞれ目的が明確にされているため、申請の前に使い分けを理解しておくことが必要です。
例えば中小企業省力化投資補助金が生産プロセス等の効率化(省力化)を目的としているのに対して、ものづくり補助金は革新的な新製品・新サービスの開発を目的としています。
新商品開発によって積極的な販路開拓を目指すための設備投資などは、ものづくり補助金の方が適していると言えます。
中小企業省力化投資補助金の目的は省力化であるため、その意図に合致しない申請となる場合は、他の補助金を検討した方がよいでしょう。

一般型とカタログ型の違い

ここでは中小企業省力化投資補助金の「一般型」と「カタログ型」、自社に適しているのがどちらなのかを見極めるため、それぞれの特徴をざっくりと確認していきます。
一般型の特徴
「一般型」は事業者の課題に応じて設計・開発された、オーダーメイドの機械装置やシステムが補助対象となります。
システム構築を伴う場合も対象となり、自社の現場や事業内容、特殊な事情に合わせて、「カタログ型」ではできないような、自由度の高い省力化投資が可能。
多様な課題を柔軟に解決にできるのは嬉しいですが、その分審査項目は多くなっており、省力化効果や革新性などについて、総合的かつ厳正に審査される傾向にあります。
また申請については、申請者自身が電子申請システムで行う必要があるので把握しておきましょう。
カタログ注文型の特徴
国によって省力化の効果を認められ、あらかじめカタログに登録された汎用製品の中から選んで導入するのが「カタログ型」です。
カタログに掲載されているのは、清掃ロボット、配膳ロボット、自動調理器、作業ロボット、券売機など。他にも様々な業種が想定された設備があり、2024年の開始当初と比べるとかなり充実してきました。
「一般型」に比べると自由度は低いですが、審査項目が少なく申請のハードルも低くなっています。
販売事業者との共同申請が必須となり、足並みを揃える必要はあるものの、その分申請にかかる負担も少ないのは大きなメリットと言えます。
一般型とカタログ型は併用できる?
結論として、「一般型」と「カタログ型」の併用は可能です。
ただし同じ補助対象(設備)に対して併用することはできません。別の設備であれば、一方は「カタログ型」、もう一方は「一般型」で申請する、といった選択肢もあります。
また「一般型」を検討している場合でも、まずは「カタログ型」の製品カタログを確認するようにしましょう。
カタログに掲載されている製品であれば、国が省力化効果を認めたものと認識できるため、一般型で同様のカテゴリの製品を導入する場合には、審査上で有利に働く可能性があります。
それぞれに適した企業は?
以下に該当するような企業は、「一般型」を選ぶことをおすすめします。
- 自社の業務プロセスに合わせて,オーダーメイドの設備を導入したい
- 汎用的な設備では、自社の課題に対応できない
- 省力化による生産性向上に徹底的に取り組みたい
対して「カタログ型」がおすすめなのは、以下のような企業です。
- 速やかに省力化設備を導入したい
- 必要な設備が製品カタログに掲載されている
- 補助金申請の手続きにかかる負担を極力減らしたい
中小企業省力化投資補助金の対象となる事業者

一般型・カタログ型ともに、補助金の対象となる事業者には共通の要件があり、以下のように細かく規定されています。
そもそも自社が補助金の対象となるのかという点については、申請前に必ず確認しておきたいところです。
補助対象となる企業の規模
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業、個人事業主、その他の一部法人が対象になります。
業種ごとの規模
- 製造業、建設業、運輸業: 資本金3億円以下 または 常勤従業員数300人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下 または 常勤従業員数100人以下
- サービス業(ソフトウェア業、旅館業等を除く): 資本金5,000万円以下 または 常勤従業員数100人以下
- 小売業: 資本金5,000万円以下 または 常勤従業員数50人以下
- ゴム製品製造業: 資本金3億円以下 または 常勤従業員数900人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業: 資本金3億円以下 または 常勤従業員数300人以下
- 旅館業: 資本金5,000万円以下 または 常勤従業員数200人以下
- その他の業種: 資本金3億円以下 または 常勤従業員数300人以下 * 個人事業主も申請可能です。
補助率が優遇される事業者
上記の業種ごとに定められた条件の中でも、常勤従業員数が以下の基準を満たすと「小規模企業者・小規模事業者」に分類され、補助率が優遇される場合があります。
- 製造業その他: 20人以下
- 商業・サービス業: 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 20人以下
またこの補助金で定義された「再生事業者」と呼ばれる事業者は、補助率などの面で優遇される場合があります。
「再生事業者」とは、中小企業活性化協議会などの団体から支援を受け、事業再生計画書の策定に取り組んでいる事業者とされています。
要するにかなり経営状況が悪く、専門の機関から支援を受けつつ、事業の立て直しを図っている最中の事業者のことを指しています。
その他対象となる法人
- 企業組合、協業組合、事業協同組合などの組合関連
- 一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一定の要件を満たす社会福祉法人
- 資本金10億円未満で一定の従業員数以下である特定事業者の一部(一般型のみ)
補助対象外となる事業内容
事業内容が以下に該当する場合は、中小企業省力化投資補助金の対象外となります。
- 補助金の目的に沿わない事業(単なる設備更新で省力化効果がないなど)
- 公序良俗に反する事業、法令に違反する事業
- 国の他の助成制度と補助対象経費が重複している事業(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複も対象外)
- 主として従業員の解雇を通じて生産性向上を操作するような事業
- 購入した設備を自社で使わず、第三者に長期間貸し出すような事業
- 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注または委託する事業
補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者も、補助対象外となりますのでご注意ください。
みなし大企業
中小企業者の範囲でも、実質的に大企業の支配下にあると見なされる事業者。例えば、単一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有している場合などが該当します。過去3年間の課税所得が年平均15億円を超えるような、大きな利益を上げている企業も対象外です。
みなし同一法人
親会社と議決権の50%超を有する子会社は同一法人とみなされ、いずれか1社しか申請できません。グループ会社はすべて同じ会社とみなされるため、親会社と子会社が同時に申請することはできません。代表者や住所が同じ法人も同様です。
その他
暴力団関係者や、過去に本事業で不正受給などにより交付決定を取り消された事業者、経済産業省及び中小機構から、補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者は対象外となります。
また過去3年間でものづくり補助金の交付決定を2回以上受けている、といった例をはじめ、別の補助金の交付を受けている事業者については、一定の条件にあてはまる場合に対象外となる可能性があります。
中小企業省力化投資補助金「一般型」の詳細
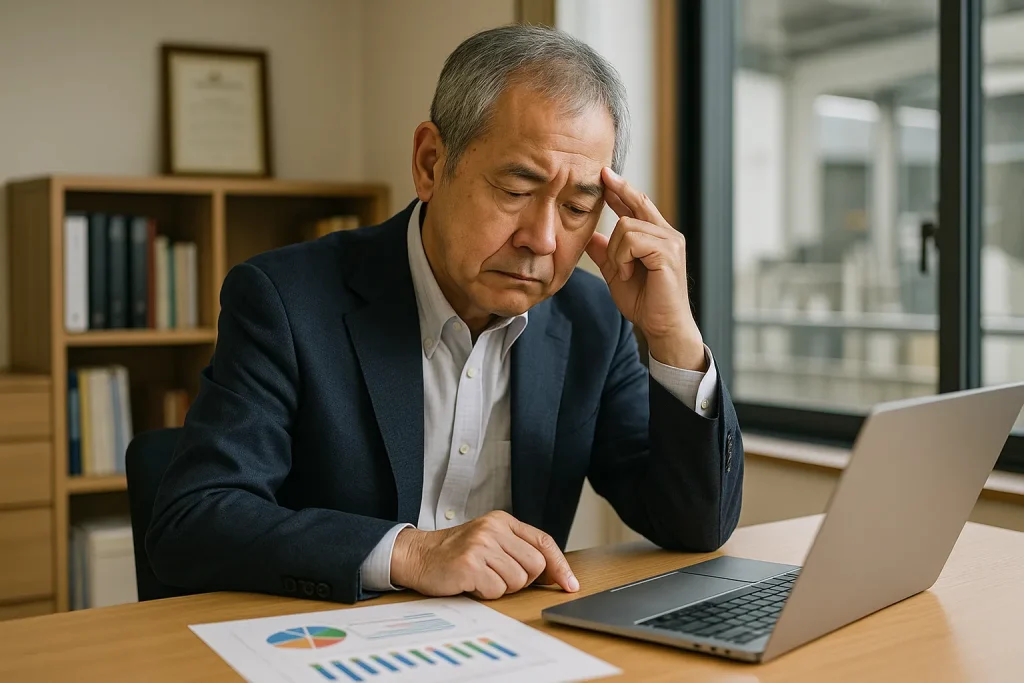
ここからは「一般型」の内容について、さらに詳しく解説していきます。
概要
「一般型」は人手不足解消に役立つ、オーダーメイドの専用設備を導入するための事業費を補助し、生産性向上と賃上げにつなげることを目的としています。
実質的に「ものづくり補助金 省力化オーダーメイド枠」の後継となる制度と言えるでしょう。
しかし汎用設備を組み合わせる計画も対象となるなど、中小企業の実態に合わせる形で、より柔軟な要件に緩和されています。
補助上限額
補助上限額は従業員規模に応じて設定されており、特例を適用することでさらに引き上げが可能です。
- 従業員数5人以下: 750万円(大幅賃上げ特例適用時:1,000万円)
- 従業員数6~20人: 1,500万円(大幅賃上げ特例適用時:2,000万円)
- 従業員数21~50人: 3,000万円(大幅賃上げ特例適用時:4,000万円)
- 従業員数51~100人: 5,000万円(大幅賃上げ特例適用時:6,500万円)
- 従業員数101人以上: 8,000万円(大幅賃上げ特例適用時:1億円)
補助率
投資金額に対する補助の割合である補助率は、基本的に1/2と定められています。
「小規模事業者」と「再生事業者」については特別扱いとなっており、補助金額が1,500万円以下の部分に限り、補助率が2/3に引き上げられます。
ただしすべての事業者共通で、補助金額が1,500万円を超える部分は1/3の補助率となる、というルールとなっています。
このようにちょっとややこしいのですが、もらえる金額1,500万円を境目として、補助率が変動するという点には注意が必要です。
例えば中小企業の場合、投資金額が3,000万円までは補助率1/2が適用されるため、1,500万円の補助金をもらえます。しかし投資金額が3,000万円を超える部分については、補助金が1/3しかもらえません。
もし4,500万円の設備投資をする場合は、投資金額3,000万円分に対しては補助率1/2が適用されるので、1,500万円の補助金がもらえます。
しかし残りの投資金額1,500万円分に対しては、補助率が1/3となるため500万円しかもらえません。
この場合、もらえる補助金は合計で2,000万円となり、2,500万円は自社で用意しなくてはいけないことになります。

賃上げ条件達成による補助上限額引き上げ
より高度な賃上げ目標を達成することで、補助額の上限を250万円~2,000万円上乗せすることができます。こちらはかなりややこしいですが、ひとまず概要を記載しておきます。
大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例
以下の両方の要件を満たすと、上記の補助上限額をさらに引き上げる特例を受けられます。
- 給与支給総額: 年平均成長率+6.0% 以上増加させること
- 事業場内最低賃金: 事業実施都道府県の最低賃金+50円 以上の水準とすること
常勤従業員がいない場合、この特例は適用されません。
給与支給総額を毎年6%上げるのは、決して簡単ではないはずです。さらに要件が未達の場合は、引き上げ分の補助金を返還しなくてはならず、リスクが大きい特例条件と言えます。
最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例
小規模事業者と再生事業者でなくても、以下の要件を満たす事業者は、補助率を2/3に引き上げることができます。
- 指定する一定期間において、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる月が3か月以上あること。
こちらも何を言っているのか、初見で理解することは困難かと思いますが、要は「給料が安い従業員が多い中小企業」であれば特例条件にあてはまりやすいです。
少なくとも毎年給与支給+6%より、クリアできる企業の数は多いでしょう。
なお「指定する一定期間」に該当する期間は、公募要領等で具体的な日時が定められているので、最新情報をチェックしてみてください。
申請に必要な基本要件
「一般型」を申請するためには、以下の全ての要件を満たす3~5年の事業計画を策定する必要があります。
- 労働生産性の向上: 年平均成長率(CAGR) +4.0% 以上向上させること
- 労働生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働者数
- 賃上げ目標: 以下のいずれかを達成する計画を策定し、従業員に表明すること
- 1人当たり給与支給総額: 年平均成長率が、事業実施都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上
- 給与支給総額: 年平均成長率 +2.0% 以上
- 最低賃金: 事業場内最低賃金を、毎年、事業実施都道府県の最低賃金 +30円 以上の水準にすること
- 事業計画期間中、毎年の3月末時点で判断される
- 一般事業主行動計画の公表: 従業員数21名以上の事業者は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」で公表すること
これらの要件が未達の場合、補助金の返還義務が生じることがあります。
ただし、天災や、付加価値額が増加せず事業計画期間の過半数が営業利益赤字であるなど、事業者の責めに帰さない正当な理由がある場合は、返還が免除されることもあります。
補助対象経費
中小企業省力化投資補助金「一般型」で補助対象となる経費は以下の通りです。
- 機械装置・システム構築費(必須): 機械装置、工具・器具の購入、製作、借用や、専用ソフトウェア、情報システムの購入・構築費用です。単価50万円(税抜)以上の設備投資が必須です。
- 運搬費: 運搬料、宅配・郵送料などです。設備の設置にかかる費用も運搬費として対象になります。
- 技術導入費: 知的財産権等の導入に要する経費で、補助対象経費総額(税抜)の1/3が上限です。
- 知的財産権等関連経費: 特許権等の取得に要する弁理士費用などで、補助対象経費総額(税抜)の1/3が上限です。
- 外注費: 専用設備の設計等の一部を外注する場合の経費で、補助対象経費総額(税抜)の1/2が上限です。
- 専門家経費: 事業遂行のために依頼した専門家への謝金、旅費で、補助対象経費総額(税抜)の1/2が上限です。
- クラウドサービス利用費: クラウドサービスの利用に関する経費です。
逆に対象外となる経費の例としては、事務所の家賃、消耗品代、中古品購入費、自社の人件費などがあります。またパソコンをはじめとして、汎用性があって目的外使用になり得るものと見做されると、基本的には対象外となってしまいます。
また本来は対象となる経費であっても、交付決定日以降に発注し、補助事業期間内に支払いが完了したものでなければ、補助対象とならないことには厳重に注意が必要です。
支払い期間を誤ってしまうのは、他の補助金でも非常によくあるトラブルです。
なお導入する設備について、補助金だけで足りない金額については、金融機関からの融資も適切に利用しましょう。
申請から効果報告まで
補助金申請の準備からもらった後の報告まで、簡単な流れを以下に記載しておきます。
- 事前準備: GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。取得には時間がかかるため、早めに手続きを行いましょう。
- 応募申請: 電子申請システムにて申請します。事業計画書(PDF形式)を添付します。自社の現状をわかりやすく記載しつつ、この補助金があることでどのように課題解決できるのか、客観的に納得感の高いストーリーを作成しましょう。省力化投資で人手不足を解消することにより、より付加価値が高い事業に取り組むことができ、最終的には賃上げにつながるという構成が一般的です。
- 審査: 事務局による書面審査が行われます。補助申請額が一定規模以上の場合は、オンラインでの口頭審査も実施されます。審査項目は「適格性」「技術面(省力化指数、投資回収期間など)」「計画面」「政策面」など多岐にわたります。それとは別に、いくつかの「加点項目」も設定されているため、クリアできるものが無いかチェックしておきましょう。
- 採択・交付決定: 審査を通過すると補助金交付候補者として採択され、その後、見積書などを揃えて交付申請手続きを行い、交付決定となります。
- 補助事業実施: 交付決定後に設備の契約・発注・納入・支払い等を行います。交付決定前の発注は補助対象外となるため、絶対に避けてください。なお補助事業実施場所は申請時点で確定している必要があり、建設中の建物などは対象外です。補助事業実施期間は、交付決定日から18か月以内です。
- 実績報告: 事業完了後、実績報告書を提出します。
- 補助金の支払い: 事務局の確定検査後、補助金が支払われます。
- 効果報告: 補助事業完了後、5年間、毎年度、事業の効果を報告する義務があります。
中小企業省力化投資補助金「カタログ型」の詳細

次に「カタログ型」の内容について、さらに詳しく解説していきます。
概要
人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を、簡易で即効性がある形で導入できるよう支援することを目的としています。
最大の特長は、あらかじめ国が省力化効果を認めて「カタログ」に登録した製品の中から導入したいものを選ぶ点です。これにより、申請手続きが大幅に簡素化されています。また、申請は販売事業者との共同申請が必須となります。
補助上限額と補助率
事業者の従業員数によって、補助上限額が変わる仕組みとなっています。
- 従業員数5人以下: 200万円(大幅な賃上げを行う場合:300万円)
- 従業員数6~20人: 500万円(大幅な賃上げを行う場合:750万円)
- 従業員数21人以上: 1,000万円(大幅な賃上げを行う場合:1,500万円)
「カタログ型」における「大幅な賃上げ」の要件は以下のとおりです。
- 事業場内最低賃金を45円以上増加させること
- 給与支給総額を6%以上増加させること
- 上記双方を補助事業実施期間の終了時点で達成する見込みであること。
なお補助率は、1/2以下として共通となっています。
申請に必要な基本要件
「カタログ型」の申請にあたっては、以下の要件を満たす事業計画を策定する必要があります。
- 労働生産性の向上: 補助事業終了後3年間で、労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる(2回目以降の申請は4.0%以上)。
- 人手不足の申告: 申請時に、自社が人手不足の状態にあることを示す必要があります。具体的には、以下のいずれかに該当することを選択し、証明書類を提出します。
- 従業員の平均残業時間が月30時間を超えている
- 前年度比で従業員が5%以上減少している
- 求人を出したが充足に至らなかった
簡単ではないかもしれませんが、「一般型」と比べれば申請にかかる負担は大幅に低く抑えられます。全体的なルールについても、「カタログ型」の方がかなりシンプルと言えるでしょう。
補助対象経費
「カタログ型」で補助対象となるのは、製品本体価格と導入経費(導入のためにかかる費用)のみとなっています。
- 製品本体価格: カタログに登録された製品の購入または借用に要する経費
- 導入経費(製品本体価格の2割が上限): 設置作業、運搬費、動作確認費用、マスタ設定等の導入設定費用
中古品や交付決定前に購入したものは、「一般型」と同様に対象外となります。
もし似たような設備の導入を検討しているものの、主な目的が省力化ではなく事業拡大に近い場合は、同じく2025年注目の中小企業新事業進出補助金を検討してみるとよいかもしれません。

申請から効果報告まで
「カタログ型」の申請からもらった後の報告まで、流れを簡単に記載しておきます。
- 事前準備:
- GビズIDプライムを取得します。
- カタログから導入したい省力化製品と、それを取り扱う販売事業者を選択します。
- 販売事業者と連絡を取り、共同で事業計画を策定します。
- 交付申請: 電子申請システムを利用し、販売事業者と共同で申請します。
- 審査・採択・交付決定: 事務局による審査を経て、採択と同時に交付決定が行われます。
- 補助事業実施: 交付決定後、製品の導入を行います。
- 実績報告: 製品導入後、支払いや導入実績に関する証憑を添えて実績報告を行います。
- 補助金の支払い: 事務局による補助額の確定後、補助金が支払われます。
- 効果報告と実地検査: 補助事業終了後、3年間の効果報告が必要です。また、効果報告期間が終了するまでの間に、製品が適切に導入されているかを確認するための実地検査が行われます。
申請のポイントと注意点

補助金の申請を成功させるためには、周到な準備が不可欠です。申請を検討されている事業者は、以下の点に特に注意して準備を進めましょう。
GビズIDプライムの早期取得
まず、最も基本的かつ重要な準備として、GビズIDプライムアカウントの取得が挙げられます。
「一般型」「カタログ型」ともに、本事業の申請は電子申請システムで行うため、このアカウントが必要不可欠となります。
またアカウントの発行には一定の期間(通常2~3週間)を要するため、公募の開始を待つのではなく、申請を決めた段階で速やかに取得手続きを進めることが肝心です。
必要書類の準備
中小企業省力化投資補助金では、申請に必要な書類が多岐にわたります。
特に「一般型」は、書類の準備には1ヶ月程度の期間を見ておくのが賢明でしょう。事前に提出書類のリストを確認し、計画的に準備を進めることをおすすめします。
金融機関からの借入を予定している場合は、「金融機関確認書」の取得が重要となります。自己資金が十分でないにもかかわらず、金融機関の確認書なしで申請すると、審査で実現可能性を疑われてしまうかもしれません。
「カタログ型」も負担が小さいとはいえ、多くの書類の準備が必要です。
販売事業者に作成・添付を依頼する「省力化効果判定シート」など、「カタログ型」特有の必要書類が求められます。
また人手不足の状況を客観的に示すための書類として、直近の時間外労働時間の記録や、過去の求人情報などが必要になります。さらに「大幅な賃上げ」を目指す場合には、賃金台帳などの要件に応じた書類も必要です。
「一般型」事業計画書の作り込み
これまで説明してきたとおり、「一般型」で採択を勝ち取るためのハードルは高いです。
採択のためには、事業計画書の質が極めて重要になりますが、審査員を納得させる計画書を作成するために、以下のような点に注意しましょう。
数値目標の根拠を明確にする
事業計画書に記載する労働生産性や賃上げに関する数値目標は、単に目標値を掲げるだけでは不十分です。現状分析の数値を元にして、なぜその目標が達成可能なのか、誰が見ても納得できる算出根拠を具体的に示すことが求められます。
一貫したストーリーの構築
「なぜその設備が必要なのか」「設備の導入によってどのような課題が解決されるのか」「結果としてどのように生産性向上へつながるのか」という、具体的なストーリーを描くことが重要です。
省力化後のリソース再配分を具体的に
この補助金では、省力化によって生まれた時間や人材といったリソースを、より付加価値の高い業務へどう再配分するのかを具体的に示すことが求められます。この点が、単なるコスト削減目的の設備投資との大きな違いであり、審査においても重視されるポイントと考えられます。
外部支援者情報の記載漏れに注意
認定経営革新等支援機関などの外部支援者に協力を依頼した場合は、その情報を申請画面に漏れなく記載してください。この記載を怠ると、虚偽申請と見なされ、不採択や採択取消の理由になる可能性があるため、細心の注意が必要です。
「カタログ型」販売事業者との円滑な連携
一方で「カタログ型」では販売事業者との連携も成功の鍵を握ります。共同申請が前提となるため、以下の点に注意して連携を進めましょう。
- 信頼できる販売事業者の選定: まずはカタログから、自社が導入したい製品と、それを扱う信頼できる販売事業者を選定することがスタートラインです。
- 事業計画の十分なすり合わせ: 申請前に、販売事業者と事業計画の内容、特に省力化の効果や目標設定について、十分にすり合わせを行うことが不可欠です。円滑なコミュニケーションが、スムーズな申請と採択につながります。
中小企業省力化投資補助金のよくある疑問

Q: 申請は一度しかできませんか?
「一般型」は、各公募回で1申請に限られます。過去に採択された事業者も、補助金の支払いが完了していれば再度申請できる場合がありますが、条件があります。
「カタログ型」は、補助上限額の範囲内であれば複数回の申請が可能です。ただし、2回目以降の申請は、それ以前の申請にかかる補助金の支払いが完了した後に行う必要があります。
Q: リースでの設備導入も対象になりますか?
「一般型」では、「借用」として補助対象経費に含まれます。
「カタログ型」では、ファイナンス・リース取引に限り、認定された対象リース会社と共同で申請することで対象となります。この場合、補助金はリース会社に支払われ、中小企業はリース料が減額される形で還元を受けます。また、賃貸借契約による導入も可能です。
Q: すでに所有している設備の更新も対象になりますか?
単に汎用設備を単体で更新する事業は補助対象とはなりません。一般型で申請するには、既存設備の更新であっても、複数の設備を組み合わせたり、自社の環境に合わせてカスタマイズしたりするなど、新たな省力化効果や付加価値を生み出す計画が必要です。
Q: 補助金はいつ支払われますか?
補助金は、原則として事業完了後に実績報告書を提出し、事務局による検査を経て補助金額が確定した後に支払われる「精算払(後払い)」となります。
Q: 賃上げ要件が未達だとどうなりますか?
基本要件や特例措置の賃上げ目標が未達だった場合、補助金の一部または引き上げ分の返還を求められることがあります。ただし、天災や、付加価値額が増加せず事業計画期間の過半数が営業利益赤字であるなど事業者の責めに帰さない理由がある場合は免除されることもあります。計画策定は慎重に行いましょう。
コンサルタントの活用で補助金申請も省力化を

中小企業省力化投資補助金は、人手不足という大きな課題に直面する中小企業にとって、起死回生の一手にもなり得る可能性を秘めています。
しかしながら申請にあたっては、指定の書類をはじめ様々な準備をしなければならず、とりわけ不慣れな計画書作成に多くの時間がかかるのが厄介なところ。
また生産性を大幅に向上させるにあたっては、設備を導入しただけではうまくいかず、業務フローや組織全体の改善を伴うことも多いため、事業者様が自社だけでの取り組みに限界を感じられることもあるようです。
こういった点で不安なところがあれば、外部の経営コンサルタントを活用するのことを推奨します。
エクト経営コンサルティングは、様々な分野の専門家が集まる経営コンサルタントオフィス。
採択率80%以上の実績を誇る補助金申請のプロ集団とも連携しており、無料相談で貴社に最適なコンサルタントを選定できるため、様々なご要望に柔軟に対応することが可能です。
さらに導入した設備を最大限に活かし、生産性を向上させるための社内体制づくりや、業務効率化についても専門家からのサポートが受けられます。
中小企業専門の経営相談所として活動しているから、料金も驚くほどリーズナブル。3ヶ月以内にコンサルタントの成果にご満足いただけなければ、初期費用については全額返金いたします。
中小企業省力化投資補助金に関して、申請のプロ集団からのサポートをはじめとして、相談したいことがある企業様は以下のボタンから詳細をご確認ください。
【着手金0円プラン新登場、詳しくは以下のボタンから】
お問い合わせはこちら
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

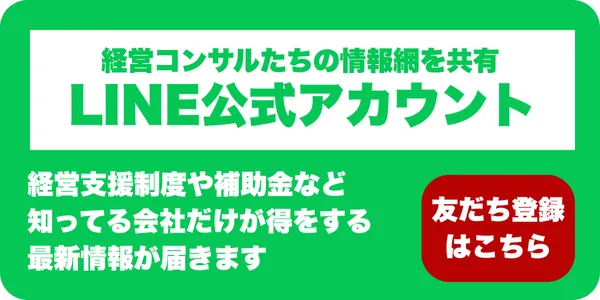
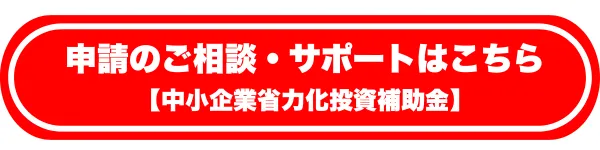












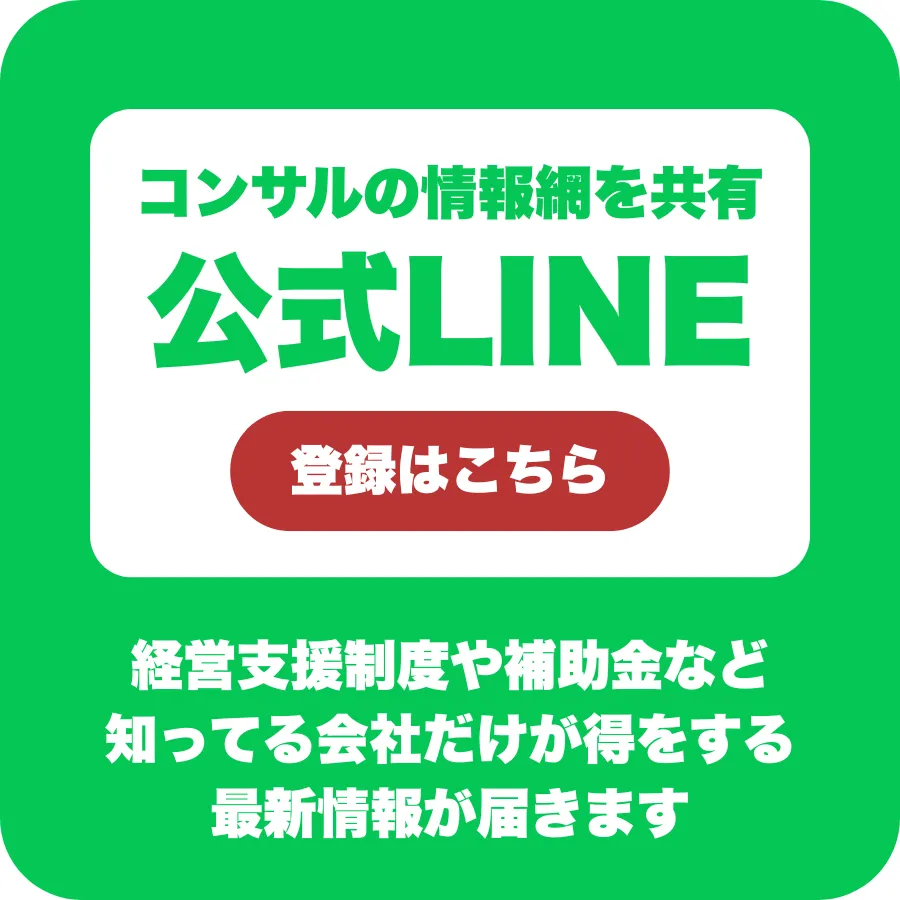












この記事へのコメントはありません。