2025年版、中小企業が見逃せない補助金5選!経営コンサルタントがわかりやすく解説します

中小企業の経営相談所、エクト経営コンサルティングです。
今回は中小企業なら見逃せない、2025年に注目の補助金5種類について解説していきます。
補助金という制度は、事業で必要となる投資の一部を国が負担してくれるありがたいもので、経営のために活用しない手はありません。
しかし補助金を利用するにあたっては、ルール自体が理解しづらいのが大きな障壁です。
公式に案内されている補助金の資料は、たいてい複雑で回りくどい書き方をしているため、自社が対象になるのかわからないことも多いと思います。
かくいう私も、今でこそコンサルタントとして助言する立場でありながら、初めて某補助金の公募要領を見た時は、何を言っているのかほとんど理解できませんでした。
もともとお固い文章には抵抗感がありましたが、それにしてもあまりに分かりづらいので、当時はルールを把握するために膨大な時間を費やし、イライラさえも感じていたような気がします…。
そこでこの記事では、中小企業が獲得しやすい5種類の補助金について、経営者の皆様が貴重な時間を無駄にしないように、公式資料の内容をわかりやすさ重視で解説。
まずは「自社が対象となるのか」という点が判断できるように、細かい部分はとりあえず置いといて、膨大なルールから要点だけをまとめさせていただきました。
もし皆様の会社で補助金が使えるのであれば、経営において大きな助けとなるはずです。
「補助金がもらえるのに知らなかった…」なんてもったいないことが無いように、この記事で自社に合った補助金がないかよくチェックしてくださいね。
※各補助金の最新ルールが改正され、この記事の内容と異なる可能性もあるため、必ず最新の公募要領と併せて確認してください。
採択率80%以上のプロ集団が対応!
補助金の申請サポートが必要な方はお問い合わせください
目次
中小企業が補助金を検討する前に知っておきたいこと

各補助金を検討する前に、いくつかの注意点を必ず抑えておきましょう。
基本的に補助金というものは、中小企業の事業で必要となる投資の一部が補助されるものです。
コロナ時代にばらまかれた給付金のようなものではなく、もらうためには定められた条件を達成しなければなりません。
そのため申請だけなら多くの企業ができますが、実際に対象となるのは投資を本当に必要としていて、条件をクリアできる力のある企業だけに限られているのです。
こういった話を敢えて記載したのは、「財源が税金だから」といった類の理由ではなく、補助金申請が貴社にとってマイナスになることを防ぐためです。
というのも、例えば「○年後に給料や利益を○%必ず上げること」など、条件達成のハードルが高い補助金は少なくありません。
補助金をもらうこと自体が目的となり、このような条件を無理やり目指しつつ、本来は不要な投資を押し進めたことで、経営に深刻なダメージを負ってしまった企業もあります。
またたいていの補助金では、申請の際に計画書が求められます。
この計画書を作成する労力は大きく、その他の準備も含めるとかなりの手間になるのですが、すべて苦労して申請を完了したとしても、必ず補助金がもらえるとは限りません。
多くの補助金では全体の予算が決まっており、応募のあったすべての企業の申請内容を評価し、どの企業に補助金を与えるかを相対的に審査しています。
つまり補助金をもらうのも、他の企業との競争になるということなのです。
申請のあったすべての企業の中で、実際に補助金をもらえた企業の割合を表す「採択率」には波があります。
一部の補助金では、過去の採択率が30%以下にまで低下した例もありますが、これは10社のうち3社以下しかもらえないほど競争が激しかったということです。
せっかく苦労して申請したとしても、「不採択」となればお金と時間の無駄。
補助金を申請するために費やした時間や、条件達成のために増加させた人件費をはじめとするコストが、もらえる金額と果たして見合っているかどうか、慎重に検討する必要があります。
以上のような点を十分理解した上で、補助金の検討を進めていきましょう。
中小企業新事業進出補助金

新しい事業に挑戦しようと考えている中小企業を対象にした補助金です。
コロナ禍をきっかけに生まれた「事業再構築補助金」が終了となり、その後継として誕生した新しい補助金で、2025年4月22日に詳細が発表されたばかり。
一部では「2025年の目玉補助金」という声も聞かれ、ひときわ大きな注目が集まっています。

中小企業新事業進出補助金の対象となる経費は?
中小企業新事業進出補助金の補助金額は、対象となる経費の1/2とされています。
補助上限金額は2,500万円~9,000万円、下限金額は750万円で、以下のような経費が対象となります。
機械装置・システム構築費:新しい事業に必要な機械や、コンピューターシステムを作る費用
建物費:新しい事業に必要な工場やお店などを建てたり、改修したりする費用
運搬費:補助金で購入した設備などを運ぶ費用
技術導入費:新しい事業に必要な特許などの権利を買う費用
知的財産権等関連経費:新しい事業で生まれた発明などを特許登録するための費用(弁理士さんへの依頼費用など)
外注費:仕事の一部を他の会社にお願いする費用(全体の補助金額の10%までなどの制限あり)
専門家経費:コンサルタントなど専門家にお願いする費用(1日あたりの金額に上限あり)
クラウドサービス利用費:新しい事業で使うインターネット上のサービスの費用
広告宣伝・販売促進費:新しい製品やサービスを紹介するためのパンフレットや動画、ウェブサイトを作る費用、展示会に出る費用など(使える金額に上限あり)
ただし以上にあてはまる経費であれば、必ず補助金がもらえるというわけではありません。
まず「機械装置・システム構築費」か「建物費」のどちらかが必ず含まれていなくてはならない、というルールには要注意です。例えば広告宣伝費や外注費だけを申請したくても、計画に「機械装置・システム構築費」または「建物費」が無ければ、この補助金では対象外ということです。
また中小企業新事業進出補助金という名前のとおり、この補助金では中小企業の新しい事業を支援することを目的としています。そのため以上の対象経費に当てはまっていても、計画自体が既存事業とあまり変わらない内容だと認められません。
他にも「あれはダメ」「これはOK」「ただしこの場合はNG」のように複雑なルールとなっているため、対象として認められるかはよく確認が必要です。
しかし中小企業の経営者様にとって、日々の業務に追われて忙しい中、難解な文章を読み解く時間は惜しいはず。
自社の事業が対象になるのかという点だけでも、専門家に相談してみるのも一手でしょう。
中小企業新事業進出補助金をもらうための条件は?
中小企業新事業進出補助金には、指定された内容を盛り込んだ計画書の提出が必須となります。
また以下のような条件が設定されており、補助金をもらった後も計画通りに事業を進めて、いくつかの目標は必須で達成しなければなりません。
新事業進出要件
提出する計画の内容が、その企業にとって本当に新しい事業である必要があります。
具体的には、補助金を使う事業の製品やサービスが新しいものでありつつ、これまでの事業と異なる新しい市場(顧客)でなくてはいけません。
さらに最終的には、補助金を使う新しい事業の売上が会社全体の売上の10%以上、または付加価値額で15%以上を占める、という見込みの計画が求められます。
付加価値額を簡単に説明すると、会社の儲けに人件費と減価償却費を加えた指標です。
付加価値額要件
3〜5年の期間に、会社全体の付加価値額が年平均で4.0%以上成長するという計画を立て、それを達成する必要があります。
賃上げ要件
3〜5年の間に、支払っている給料の金額を一定以上に増やす必要があります。具体的な目標値として、以下のどちらかの達成が必要です。
①「従業員一人あたりの給料の平均額」の年平均成長率を、都道府県の過去5年間の最低賃金の年平均成長率以上にすること
②会社全体の給料の年平均成長率を2.5%以上にすること
1番目の条件は、パッと見ただけでは非常に理解しづらいですが、要は「最低賃金の上げ幅よりも高い割合で給料を上げてね」ということです。
また賃上げの計画は、事前に従業員に説明しておくことが義務づけられています。
事業場内最低賃金要件
3〜5年の間に、毎年、事業を行う場所での最低賃金(パート・アルバイト含む)を、その地域の法律で定められた最低賃金よりも30円以上高くする必要があります。
ワークライフバランス要件
「次世代育成支援対策推進法」という法律に基づいて、子育て支援などに関する会社の行動計画を作り、それを国のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表している必要があります。
金融機関要件
もし、この新しい事業のために金融機関から融資を受ける場合は、その金融機関に事業計画を見てもらい、確認書をもらう必要があります。
中小企業新事業進出補助金の申請に適している企業
この補助金に適しているのは、ちょうど新事業をスタートしたいと考えている、一定以上の企業規模がある中小企業です。
補助金額の下限が750万円、さらに機械装置・システム構築・建物のいずれかが必須という点から、それなりに大きな設備投資が必要となります。
そのためある程度大きい中小企業には検討の価値がありますが、小規模よりの企業様にとっては金額が現実的でないことが想定され、あまり向いているとは言えません。
また新事業進出要件や賃上げ要件といった条件は、企業によってはかなりハードルが高いことも想定され、達成できなければ返還が求められる場合があります。
以上のような点から、中小企業新事業進出補助金を申請するにあたってはそれなりの「覚悟」が必要であり、リスクを十分に理解した上での申請をおすすめします。

小規模事業者持続化補助金
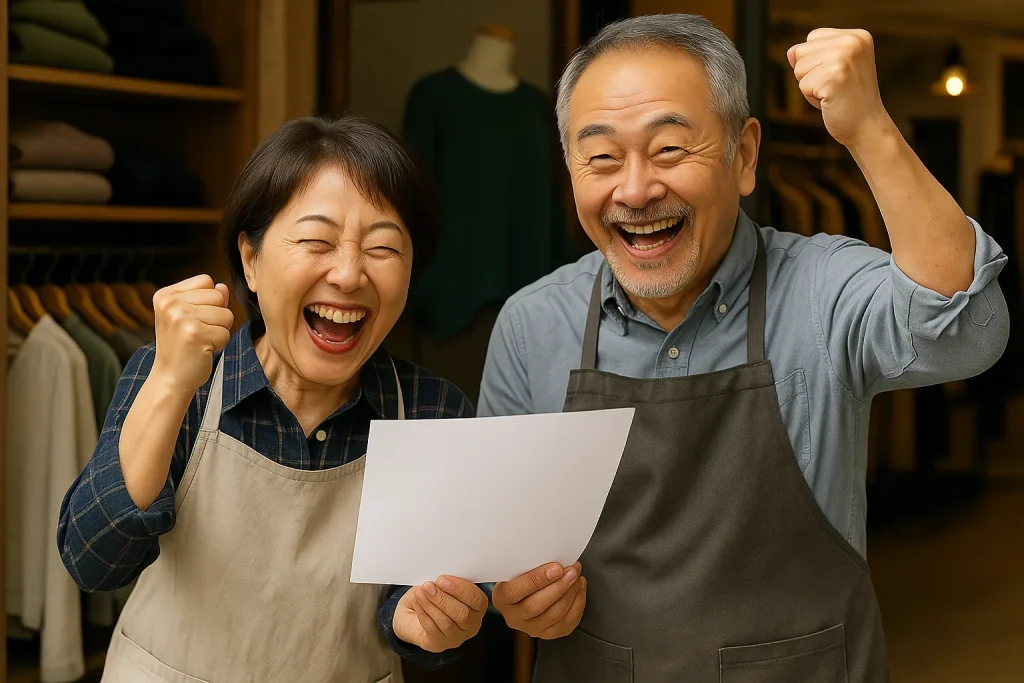
小規模な中小企業から個人事業主を対象とした補助金です。
「第○回」といった形で何度も公募されており、今まで多くの事業者に愛され続けてきました。
というのも申請の際の手間が比較的少なめ、採択率が比較的高い、条件さえ満たせばおかわりOK…など、リスクよりもメリットの方がかなり大きい内容なのです。
計画書の提出は必要となりますが、他の補助金と比べればかなりシンプル。
補助対象となる経費も幅広く、一定の条件つきとはいえホームページやWEB広告に使えるのも希少であり、そういった使い勝手の面でも好評となっています。

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は?
この補助金事業の概要として、「小規模事業者の販路開拓と、それに伴う業務効率化で発生する費用の一部を補助すること」と記載されています。
販路開拓も業務効率化も、多くの費用が想定されることもあり、以下のような幅広い経費が対象になります。
補助率は2/3から3/4、補助金額の下限は設定されておらず、上限は基本的には50万円。ただし次項で説明するように、条件を満たせば最大250万円まで引き上げることもできます。
機械装置等費
新しいサービスを提供したり、仕事を効率化するために必要な機械や設備を買う費用です。
ただし単なる買い替えや、パソコン・自動車など他の用途にも使えるものは対象外になることが多いです。
広報費
会社の商品やサービスを知ってもらうためのチラシ、ポスター、看板などを作る費用です。
新聞や雑誌に広告を出す費用も含まれますが、会社全体の紹介パンフレットなどは対象外です。
ウェブサイト関連費
商品を売るためのホームページやECサイトを作ったり、それを運用したりするための費用です。インターネット広告の費用もここに含まれます。
注意点として、この費用だけで申請することはできず、補助金全体の4分の1までという上限設定が設定されています。
展示会等出展費
新しい商品やサービスを多くの人に知ってもらうために、展示会や商談会に参加するための費用です。出展料や運搬費が中心であり、オンラインの展示会も対象になります。
旅費
展示会への参加や、新しい取引先を探すために遠方へ出張する際の交通費や宿泊費です。ただし、一定のルールに基づいた金額計算が必要です。
新商品開発費
新しい商品を開発するための試作品作りに必要な材料費や設計費用などです。
借料
事業に必要な機械や設備をリース・レンタルする費用です。事務所の家賃は原則対象外ですが、販路開拓のために新たに借りる場合は対象になることもあります。
委託・外注費
店舗の改装や、専門的なデザインなど、自社だけでは難しい業務を他の会社にお願いする費用です。
「特例」について
小規模事業者持続化補助金では、特定の条件を満たすことで「特例」が適用され、補助上限額を引き上げることが可能です。
一つは「インボイス特例」です。消費税の新しい仕組みであるインボイス制度に対応するために、これまで消費税を納めていなかった事業者がインボイス発行事業者として登録した場合、補助上限額が50万円上乗せされ、最大100万円まで補助が受けられる可能性があります。
もう一つは「賃金引上げ特例」です。従業員の給料を、申請時よりも50円以上引き上げる計画を実行する場合、補助上限額が150万円上乗せされ、最大200万円まで補助が受けられる可能性があります。
もし、インボイス特例と賃金引上げ特例の両方の条件を満たす場合は、合計で200万円が上乗せされ、最大250万円まで補助を受けられる可能性があります。
ここまでの金額がもらえるとなると、小規模事業者の経営に与えるインパクトはかなり大きいですよね。
さらに「賃金引上げ特例」を使う事業者のうち、赤字である場合は補助率が特別に3/4に引き上げられます。
小規模事業者持続化補助金をもらうための条件は?
小規模事業者持続化補助金をもらうために必要な条件としては、以下のようなものが挙げられます。
経営計画・補助事業計画の作成と実行
まず自社の経営状況を見直し、「これからどうやって事業を続けていくか」という経営計画と、「そのために具体的に何をするか」という補助事業計画を作成する必要があります。
これらの計画は、補助金の審査に大きく関わってきます。補助金の採択は相対評価であり、他社より優れた計画を書くことが、補助金がもらえるかどうかの基本的なポイントとなります。
そして補助金が採択されたら、この計画に沿って販路開拓などの取り組みを実行しなければなりません。
商工会・商工会議所の支援
この補助金は、地域の商工会または商工会議所のサポートを受けながら進めることが前提です。計画作成の段階から相談し、申請前には「事業支援計画書」という書類を発行してもらう必要があります。
なお商工会・商工会議所に入っていなくても、「事業支援計画書」を発行してもらうことは可能です。
加点項目
他の補助金と比べるとハードルが低いとはいえ、申請すれば必ずもらえるわけではありません。
また申請時に専門家のアドバイスを受ける事業者も増えており、計画書のレベルは年々上がってきていると言われています。
つまり競争が激しくなっているわけですが、そんな中で採択率を少しでも上げるためには、ルール上で設定された「加点項目」を達成することが重要になっています。
加点項目は必須条件ではないものの、様々な加点要素をクリアすることが、この補助金をもらうためのポイントとなるはずです。
特例の条件達成
「インボイス特例」や「賃金引上げ特例」を利用し、補助金の上限額を増やしてもらっている場合は、それぞれの特例の条件をきちんと達成している必要があります。
具体的にはインボイス発行事業者として登録されていること、事業場内最低賃金を50円以上引き上げることです。
もし達成できなかった場合は補助金がもらえないことになりますが、上乗せされた部分だけに限らず、補助金全体がもらえなくなってしまうので注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金の申請に適している企業
この補助金は様々な経費が対象になり、デメリットが比較的少ないという点から、多くの小規模事業者様へ積極的におすすめしたい補助金です。
注意点として、名前の通り「小規模事業者」でないと補助金はもらえません。
小規模事業者の定義は業種によって異なりますが、常時雇用している従業員の数が一定以下の事業者のことを指しています。
具体的には、卸売業・小売業・サービス業では従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業と娯楽業は従業員20人以下、その他の業種では従業員20人以下の事業者のことであり、企業だけでなく個人事業主、特定のNPO法人なども該当します。
そもそも小規模事業者持続化補助金の目的として掲げられている、「販路開拓」や「生産性向上」といったテーマは、ほとんどの小規模事業者が抱えている課題と絡んでいるはずです。
補助金のために無理な投資をするのはオススメしませんが、当てはまる経費があるならぜひ検討してみるとよいでしょう。
IT導入補助金

ITツールと呼ばれる、ソフトウェアやクラウドサービスを導入するのに使える補助金です。
この補助金では、ITツールを導入したい中小企業の皆様を「補助事業者」と呼んでおり、皆様にITツールを売りたいベンダーや販売業者を「支援事業者」と呼んでいます。
そして「補助事業者」と「支援事業者」が、補助金をもらうために共同で申請する仕組みとなっており、一見するとややこしいルールに見えるかもしれません。
しかし中小企業の皆様にとっては、ITツールを購入する先の業者が「支援事業者」となることで、「補助事業者」である皆様の申請をサポートしてくれるため、実際は申請のハードルが比較的低い補助金となっています。
IT導入補助金の対象となる経費は?
この補助金の目的は、中小企業の皆様の生産性を向上させることです。
国としてはITツールの導入を支援することにより、中小企業のデジタル化や業務効率化を促すことで、日本全体の生産性を上げたいと考えているのです。
そういった前提の下に対象となる経費として、具体的には以下のようなものが挙げられます。
ソフトウェア購入費:生産性向上に役立つソフトウェアの購入費用
クラウドサービス:生産性向上に役立つクラウドサービスの利用料(最大2年分)
オプション:導入するITツールの機能を追加するための費用
役務:ITツールを導入するための設定やサポートにかかる費用
ハードウェア:パソコンやタブレットなどの購入費用、ただし一部のITツールを同時に導入するという条件つき
ソフトウェアやクラウドサービスは様々なものがありますが、どのようなITツールが対象になるかは、公募要領の中でかなり細かく分類されています。
ここでは詳しい説明を省きますが、「生産性を向上させる」という目的に合致していれば、かなり幅広いITツールが対象となっている印象です。
また補助金金額の上限や補助率は、ITツールや申請する「枠」によって異なっています。
条件は細かく分けられていますが、ほとんどの中小企業は「通常枠」もしくは「インボイス枠」のどちらかを利用することが多いはずです。
この2つの枠に限って説明すると、補助上限額は5万円~450万円、補助率は1/2~4/5となっています。
IT導入補助金をもらうための条件は?
IT導入補助金をもらうための条件はたくさんあるものの、クリアするのに決して難しくない内容が多いです。
多くの条件の中から、この補助金で特徴的な3つについて解説します。
「SECURITYACTION」の宣言
「SECURITYACTION」とは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が推進する、中小企業・小規模事業者等が情報セキュリティ対策に自主的に取り組むことを宣言する制度のことです。
企業が自社の情報セキュリティリスクを認識し、対策を行うことを促すというものですが、この制度自体あまり知られていないのが実情です。
IT導入補助金を申請するためには、「SECURITYACTION」で定められた「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかの宣言を行う必要があります。
★一つ星:情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言
★★二つ星:情報セキュリティ基本方針を定め、より高度な対策に取り組むことを宣言
宣言自体は難しくないものの、証明するIDが発行されるまでに1週間前後の時間がかかります。詳細は以下のIPAのウェブサイトで確認できます。
労働生産性向上のための計画作成
IT導入補助金では、3年間の事業計画を提出することが義務付けられています。そして計画の期間中に、「労働生産性」という指標を一定以上まで向上させる必要があります。
労働生産性の詳しい計算式は省きますが、非常にざっくりと説明すると、「労働時間に対する利益+αの割合」といったところです。
この労働生産性を1年後に3%以上増加させ、さらに3年間の年平均成長率を3%以上にするという、実現可能な計画を作成する必要があるのです。
もし計画目標が達成できなかった場合は、補助金の返還を求められる場合もあります。
支援事業者との連携
この補助金はITツールを販売している支援事業者と共同で申請する形となるため、様々な部分で連携が求められます。
とはいえ補助金の交付申請に必要となる手続きや書類作成などについて、IT導入支援事業者のサポートを受けられる点はメリットと言えます。
補助金をもらった後には、ITツールの活用状況や生産性向上に関する効果報告を行う必要がありますが、この際もIT導入支援事業者との連携が必要となる場合があります。
IT導入補助金の申請に適している企業
ITツールの導入を検討している企業、業務効率化による生産性向上を目指している企業、自社の古いシステムを刷新しようと思っている企業など、多くの中小企業にとってIT導入補助金はとても役立つはずです。
インボイス制度への対応を考えている事業者様にとっては、検討しないともったいないとさえ言えるかもしれません。
労働生産性の向上は簡単ではないかもしれませんが、これからも長きにわたって経営を続けていく上では、いずれにしても生産性の向上が避けられない課題となるはずです。
補助のあるなしに関わらず、生産性を向上させたいという前向きな意欲のある企業にとって、IT導入補助金は強い味方となるでしょう。
中小企業省力化投資補助金

中小企業の「省力化」を実現するための、設備導入を補助してくれる補助金です。
2024年に誕生した比較的新しい補助金で、発表された際はとても期待されていました。
ところがフタを開けてみると、指定されたカタログに載っているごく一部の設備しか対象にならず、使い勝手が極めて悪いことが明らかとなったため、一転してほとんどの事業者から見向きもされない状態に…。
そういった点が見直され、2025年は当初の「カタログ型」に加えて、比較的自由な「一般型」が新設、だいぶ実用的になってリニューアルされたのです。
以上のような経緯もあって、この補助金は「カタログ型」と「一般型」でルールが大きく異なります。
中小企業省力化投資補助金の対象となる経費は?
「カタログ型」はその名の通り、カタログに載っている機械装置、工具・器具、ソフトウェアなどの購入費用、またはリース・レンタル費用が対象です。
導入に伴う設置作業費、運搬費、動作確認、初期設定などの費用も、一部の条件下で対象となります。
このように「カタログ型」は良くも悪くもシンプルなのですが、「一般型」ではオーダーメイドの発注をはじめ幅広い経費が認められるので、申請にあたってはその範囲をよく理解しておく必要があります。
以下では「一般型」で対象となる経費について、簡単に解説していきますね。
機械装置・システム構築費
機械装置、工具、器具、ソフトウェア、システムにかかる費用で、購入だけでなく「借りる」費用も含まれるのがポイントです。
これらを改良したり、設置したりする費用も対象です。
「一般型」で申請する場合のルールとして、この費目の中で必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置などを導入する必要があります。
運搬費
機械装置などを運ぶための運搬料、宅配や郵送の料金です。
技術導入費
事業に必要な特許権などの知的財産権を導入するための費用です。
専門家経費
設備を導入するにあたって必要となる専門家への相談料や、指導を受けたりする際に支払う費用です。旅費も含まれる場合があります。
クラウドサービス利用費
事業専用で利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用料です。サーバーのディスク領域を借りる費用なども該当します。
外注費
オーダーメイド設備の設計などを、他の会社に一部お願い(外注)する場合の費用です。
知的財産権等関連経費
特許権などを取得するための弁理士への手続き代行費用などです。
補助上限額について
中小企業省力化投資補助金の補助上限額は「カタログ型」か「一般型」で異なりますが、従業員の数によっても変わってきます。
「カタログ型」の場合は、「5人以下」で200万円、「6人~20人」で500万円、「21人以上」で1,000万円です。また下限が25万円に設定されています。大幅な賃上げを達成すると、上限額がさらに引き上げられます。
一方で「一般型」は、一番少ない「5人以下」の会社で750万円、一番多い「101人以上」の会社で8,000万円です。こちらも大幅な賃上げを達成することで、上限額がさらに引き上げられます。
補助率について
「カタログ型」か「一般型」かによって異なり、細かいルールが設定されています。
「カタログ型」の補助率は、かかった費用の1/2以下で統一されています。
「一般型」で補助金額が1,500万円の場合は、基本的には補助率1/2です。ただし小規模事業者や事業再生に取り組む企業など、条件を満たしていれば2/3まで補助率が引き上げられます。
ただし1,500万円を超える部分は、一律で1/3となります。
人手不足で悩む企業は非常に増えていますが、根本からの解決になり得る「省力化」にこれだけの補助が受けられるのは、とてもありがたいですね。
中小企業省力化投資補助金をもらうための条件は?
やはり「カタログ型」か「一般型」かで条件は異なりますが、どちらも省力化投資によって仕事の効率を上げ、給料を増やそうという方向性では共通しています。
カタログ型の条件
以下の条件を満たす事業計画を作り、実行する必要があります。
カタログの製品を導入することによりどれだけ仕事が楽になるか、そしてその結果、空いた時間や人をどのように活用するか、という計画が求められています。
■労働生産性の向上
3年間で「労働生産性」を年平均3.0%以上向上させることが必要です。労働生産性という指標は、「労働時間に対する利益+αの割合」を指しています。
■人手不足であることの証明
残業時間が多い、人が辞めて減ってしまった、求人を出しても人が集まらないなど、人手が足りない状況であることを示す必要があります。
■賃上げ特例を目指す場合
一定期間内に会社の中で一番低い時給を45円以上アップさせ、会社全体で支払うお給料の総額を6%以上増やすことが求められます。またこれらの賃上げ計画を、従業員に伝えることも必要です。
■その他
カタログに登録された製品は、想定される業種や業務プロセスで正しく使われることが条件です。
一般型の条件
主に以下の条件を満たす事業計画を作成し、実行する必要があります。
■労働生産性の向上
3~5年の間に、労働生産性を年平均4.0%以上向上させることが求められます。労働生産性という指標は、「労働時間に対する利益+αの割合」を指しています。
■賃上げ
3~5年の間に、賃金を一定以上に増やす必要があります。具体的な目標値として、まず以下のどちらかの達成が必要です。
①「従業員一人あたりの給料の平均額」の年平均成長率を、都道府県の過去5年間の最低賃金の年平均成長率以上にすること
②会社全体の給料の年平均成長率を2.0%以上にすること
つまり最低賃金の上げ幅よりも高い割合で給料を上げるか、給料の総額を毎年だいたい2%以上上げるか、どちらかを選ぶ必要があるということです。
このような条件達成に加えて、さらに会社の中で一番低い時給の人は、都道府県の最低賃金よりも30円以上高くしなければなりません。
以上のような賃上げ条件は、企業によってはハードルが高いものとなるため、「一般型」を申請するかどうかの大きなポイントとなるでしょう。
中小企業省力化投資補助金の申請に適している企業
人手不足に悩んでいる幅広い業種の企業、生産性を上げるために仕事のやり方を変えたいと考えている企業であれば、この補助金はぜひ検討したいところです。
特にカタログ型であれば、求められる条件のハードルも比較的低い上に、申請に関する負担も比較的低いと言えます。
カタログに載っている製品も、2024年にスタートした当初は非常に少なかったと記憶しています。
しかし2025年5月時点のカタログを見ると、対象業種から用途までバラエティ豊かな製品が掲載されていて、以前よりもかなり充実した印象を受けます。
昨年は不人気でしたが、本当に必要な製品がカタログにあるなら、中小企業が積極的に検討すべき狙い目の補助金だと思います。
それに対して一般型は、対象となる製品が柔軟で補助額も高い一方、やはり条件達成のハードルの高さが気がかりなところです。
事業計画による採択の可能性や、財務面から現実的に賃上げができるのかという点においても、一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
まずは「カタログ型」の製品を見て、自社に合う製品がないかを確認してみて、見つからない場合は「一般型」を検討するという流れで検討しましょう。
ものづくり補助金

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と言います。
2013年からずっと続いている歴史ある補助金で、2025年5月時点では第20次となる公募が始まっています。
概要としては、中小企業が新しい製品やサービスを開発したり、海外への展開を目指したりする際に必要となる、設備投資を補助してくれるものです。
ものづくり補助金には大きく分けて2つの枠(タイプ)があり、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」それぞれでルールが異なります。
ものづくり補助金の対象となる経費は?
この補助金の対象となるのは、「革新的な新製品・新サービス開発」に必要な投資に関する費用か、「海外事業」に必要となる費用が中心です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
機械装置・システム構築費
事業を進める上で必要となる機械やシステム、工具、器具などに関する費用です。
購入だけでなく、リースやレンタルの場合も認められます。さらにこれらの改良、修理、設置する費用も対象となり、新品ではなく中古の設備であっても、いくつかの条件を満たせば対象になる場合があります
なお機械装置・システム構築費が最低50万円含まれていることが、ものづくり補助金を申請する上では必須の条件となります。
技術導入費
事業に必要な特許などの知的財産権を手に入れるための費用です。
専門家経費
補助金を使う事業を進めるにあたって、専門家からアドバイスを受けたり、手伝ってもらったりするのにかかる費用です。
運搬費
開発した試作品や機械装置などを運ぶための費用です。
クラウドサービス利用費
補助金を使う事業「専用」で利用するという条件で認められる、クラウドサービスの利用料などです。
原材料費
試作品を作るために必要な材料や部品を買う費用です。
外注費
新しい製品やサービスの開発に伴い、設計や検査などを他の会社にアウトソーシングする場合の費用です。
知的財産権等関連経費
特許などを取得するための弁理士への手続き代行費用や、外国へ特許を出すときの翻訳料などです。
海外展開のための経費(グローバル枠のみ)
海外出張のための旅費、通訳や翻訳を依頼するための費用に加えて、海外向けの広告宣伝・販売促進の費用が対象となります。
広告宣伝費は「製品・サービス高付加価値化枠」だと対象にならないため注意が必要です。
補助金額について
補助金の金額や割合は、「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」のどちらかによって異なります。
■製品・サービス高付加価値化枠
補助上限額:750万円~2,500万円、従業員数によって異なります
補助下限額:100万円
補助率:中小企業はかかった費用の1/2、小規模事業者および再生事業者は2/3
■グローバル枠
補助上限額:3,000万円
補助下限額:100万円
補助率:中小企業は1/2、小規模事業者は2/3
特例について
お給料を大幅に上げる目標を立てて達成すると、補助上限額が最大100万円~1,000万円まで引き上げられます。
また一定の条件を満たした上で最低賃金の引き上げに取り組むと、補助率が2/3に引き上げられます。
ものづくり補助金をもらうための条件は?
この補助金をもらうためには、いくつかの要件を満たす3年~5年の事業計画を作って実行する必要があります。以下では計画において、必ず達成すべき基本要件について説明します。
会社全体の付加価値額をアップさせること
3~5年の間に、「付加価値額」を毎年平均で3.0%以上増やすという計画を立て、達成することが求められます。「付加価値額」とは、簡単に言うと会社の儲けに人件費と減価償却費を加えた指標です。
給料を増やすこと
3~5年の間に、役員と従業員の給料を一定以上に増やす必要があります。具体的な目標値として、まず以下のどちらかの達成が必要です。
①「従業員一人あたりの給料の平均額」の年平均成長率を、都道府県の最低賃金の年平均成長率以上にすること
②会社全体の給料の年平均成長率を2.0%以上にすること
つまり最低賃金の上げ幅よりも高い割合で給料を上げるか、給料の総額を毎年だいたい2%以上上げるか、どちらかを選ぶ必要があるということです。
以上の条件達成に加えて、さらに会社の中で一番低い時給の人は、都道府県の最低賃金よりも30円以上高くしなければなりません。
賃金の目標については、申請する前に従業員や役員に伝えておく必要があること、達成できないと補助金を返還の義務があることなどにも注意が必要です。
こういった目標は、企業によっては負担がかなり大きいため注意が必要です。
仕事と子育ての両立を応援する計画を公表すること(従業員21名以上の場合)
「次世代育成支援対策推進法」という法律に基づいて、従業員が仕事と子育てを両立しやすくするための会社の行動計画を作り、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表する必要があります。
グローバル枠の追加条件
グローバル枠の申請は上記のような基本要件に加えて、実現可能性調査をする、また海外事業の準備状況を示す書類を提出するなど、様々な条件を満たす必要があります。
ものづくり補助金の申請に適している企業
名前こそものづくりとついていますが、製造業専用の補助金というわけではありません。
実質的には公募要領に記載されているとおり、「革新的な新製品・新サービス開発」に取り組む企業か、海外展開に挑戦する企業のための補助金となっています。
どちらかにあてはまる企業であれば、製造業でなくとも検討してみる価値は大いにあるのですが、以下のような点について必ずチェックしておいてください。
まず採択率についてですが、近年のものづくり補助金はだいたい40%台の低水準で推移しており、決して簡単な補助金とは言えません。
さらに「革新的な新製品・新サービス開発」という記述の表現が、抽象的でよくわからないことに大きな注意が必要です。
この記述について公式資料を確認すると、「顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発すること」と補足されています。
続けて「業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません」などと書かれているのですが、やっぱり曖昧でハッキリしませんね。
様々な情報を総合的に判断すると、今までになかったような新製品や新サービスであり、業界でも画期的な事業であることが求められているようです。
この辺はどこからがOKという線引きが難しいため、敢えて曖昧に記載されているものと推測されます。
そのため裏を返せば、審査のさじ加減でどのように判定されるかが不透明であり、もとより採択率の低いことも相まって、もらえるかどうかの不確実性が高い補助金と言えます。
以上のような点から、ものづくり補助金は魅力的であるものの、経営の上では決してアテにしてはいけない補助金であり、獲得できたらラッキーくらいに考えておいた方がよいでしょう。
もし申請するのであれば、せっかく今後の計画を作るのだから、もらえた場合ともらえなかった場合の2パターンを想定しておくとよいかもしれません。
補助金の獲得はプロのコンサルタントに相談を

2025年の見逃せない補助金5種類は以上ですが、最後に補助金の支援サービスを紹介させてください。
多くの企業の中から採択に選ばれるには、他社よりも優れた計画書を作成したり、最新の情報を把握しておく必要があります。
近年は補助金専門のコンサルタントを利用する企業が増加しており、計画書のレベル自体が上がっているようで、獲得のための競争は今後も激化していくことでしょう。
エクト経営コンサルティングは、補助金申請サポートのプロフェッショナルも含め、様々な業種・業界の専門家が集まる「中小企業の経営相談所」です。
一般的な補助金コンサルタントの場合、計画書作成を中心にほぼ代行という形で支援する分、高額な成功報酬手数料が取られることも珍しくありません。
一方で我々の場合は、計画書の大変な部分のみをサポートするなど、ご要望に応じて柔軟かつ低価格な支援メニューもご用意。
さらに採択後の計画実行フェーズには、様々な分野の専門家からリーズナブルに支援を受けることも可能なので、多くのプロを集めた我々だからこそ実現できるサービスとなっています。
もし補助金申請に関するご相談があれば、以下のボタンから詳細をご確認ください。
採択率80%以上のプロ集団が対応!
補助金の申請サポートが必要な方はお問い合わせください
お問い合わせはこちら
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

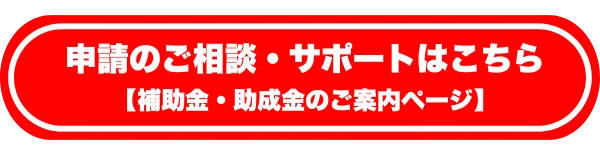
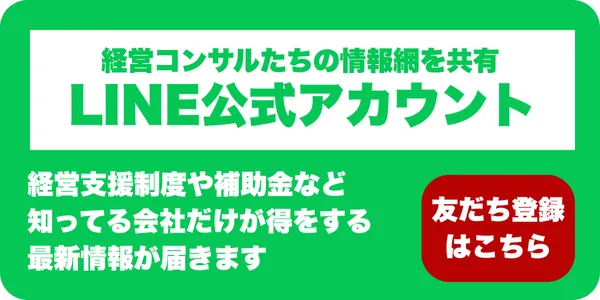
















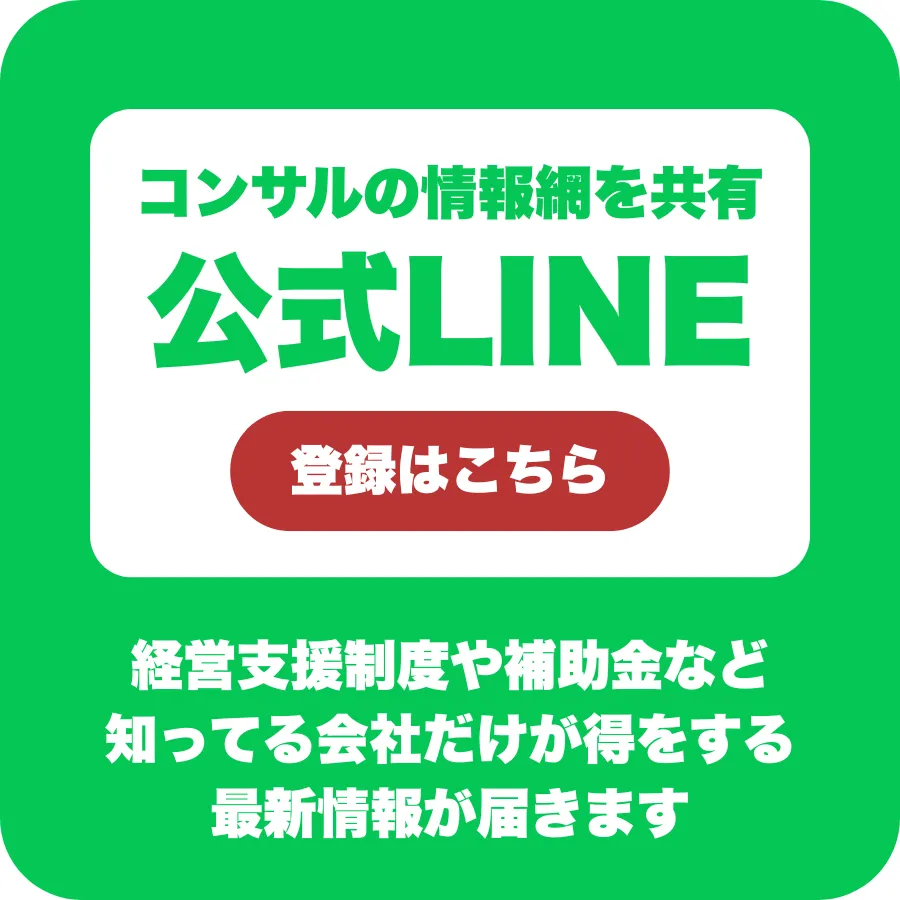












この記事へのコメントはありません。