2026年、中小企業が直面する5つの経営課題と解決策
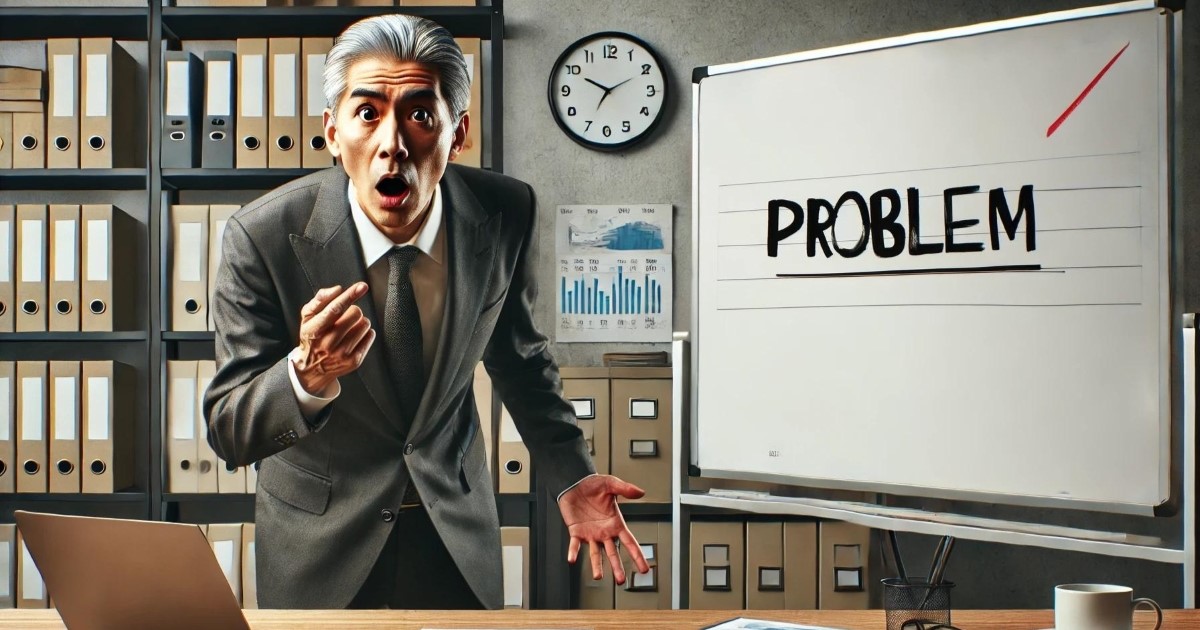
経済産業省登録の中小企業診断士が運営するコンサルタントオフィス、エクト経営コンサルティングです。
中小企業の経営には課題が山積みと言われており、生き残りをかけた競争はますます激しくなっています。実際にいろいろな事業者様とお話ししていると、絶好調という方も中にはいらっしゃるものの、大多数の方は何らかの問題にお悩みのようです。
そこで今回は、2026年に中小企業が直面している経営課題について、多くの事業者様に関係するものをピックアップしてまとめてみました。簡単ではありますが、解決策の方向性も併せてご紹介しています。
2026年の荒波を乗り越え、飛躍の年にするために。まずは自社の課題にしっかりと向き合い、然るべき対策を実施していきましょう!
人手不足のさらなる深刻化

まだまだ悪化する見通しの人手不足
経営者様からの「求人しても人が来ない」というお話は、ここ数年で何度聞いたかわかりません。
帝国データバンクの発表による2025年上半期の集計では、倒産件数が5,000件を上回っています。
上半期で5,000件に達したのは2013年上半期以来で、実に13年ぶりの水準に達したことになります。そしてこのうち「人手不足倒産」は214件で、過去最多を記録しました。
このような人手不足は既に深刻な社会問題となっていますが、他にも複合的な要因によって引き起こされている根深い問題で、2026年も解決できる見通しが立っていないのが実情です。
人手不足が起こっている要因としては、まず日本の人口構造の変化が挙げられます。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2030年には日本の生産年齢人口(15〜64歳)が約7,179万人まで減少すると予測されています。
これは2020年と比較して、約300万人以上も減少している数値となります。
中小企業にとって、この人口減少の影響は極めて大きいと言えるでしょう。なぜなら大企業と比べて、知名度や給与水準、福利厚生などの面で不利な立場にある中小企業は、人材の確保がより困難になると予想されるからです。
日本商工会議所の調査によると、2022年時点で既に約70%の中小企業が実際に人手不足を感じており、この割合は年々増加傾向にあるとされています。
また日本政策金融公庫のレポートでは、人手不足のあまり受注を断らざるを得なかったり、採用難に苦しむ中小企業の状況が記載されています。
外部環境変化への対応策を
人口減少だけでなく、産業構造の変化も人手不足問題を加速させる要因となっています。
デジタル化やAI技術の進展により、特定のスキルを持った人材への需要が高まる一方で、従来型の労働集約的な業務は減少しています。環境変化に適応できない中小企業は、必要な人材を確保することがますます困難になると予想されます。
その顕著な例として、ITスキルを持つ人材の需要と供給のギャップが年々拡大しており、2026年から2030年の間では、最大80万人弱の不足が生じると経済産業省は試算しています。
こういった問題への取り組みとしては、業務効率化による生産性向上が有効となります。
具体的に言うと、ITツール導入や業務プロセス見直しなどを実施して、より少ない人数で経営できる体制を整えようという試みを進めるということです。
業務効率化が成功すれば、限られた人数で効率的な経営を実現できます。
ある製造業の中小企業では、IoTセンサーとAIを活用した生産管理システムを導入することで、必要な人員を20%削減することに成功しています。またRPAツールを活用して事務作業を自動化し、従業員の労働時間を毎週10時間削減したという小売業の事例もあります。
私たちが日々の支援情報を集める中で、国としても生産性向上という課題をかなり重視していることが感じとれます。
2025年には「中小企業省力化投資補助金」が大幅に強化され、2026年も引き続き継続される可能性が高い他、業務効率化のための設備に対する補助制度は各自治体でも提供されています。
ただし単なる人員削減を目的とするのではなく、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えて、より事業を成長させる体制を実現することが重要と言えるでしょう。
生産性向上だけでは限界が…
業務効率化による生産性向上は非常に重要ではあるのですが、それだけで人手不足問題を完全に解決することは難しいです。
そこで重要になるのが、女性、高齢者、外国人といった多様な人材の採用と、それに伴う職場環境の整備です。またテレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入することも、人材確保のために有効な手段となります。
ある建設業の中小企業では、子育て中の女性従業員向けに柔軟な勤務体制を導入し、さらに高齢者の技術継承プログラムを実施することにより、5年間で従業員数を1.5倍に増やしたという成功事例もあります。
外国人人材の活用も、今後よりいっそう重要になってくるはずです。
特定技能制度の拡充により、2028年までの5年間で最大82万人の外国人労働者の受け入れが見込まれています。ただしその活用には、言語や文化の壁、適切な労働環境の整備など、克服すべき課題も多くあります。
そして人手不足の対策として、最も注目したいのがアウトソーシングの活用です。
業務の一部をうまく外注化することができれば、従業員を雇用するよりも低いコストで、より高い効果を上げられます。
実際に私が対応させていただいた事業者様からのご相談で、人件費を増加させる余裕が無い場合には、アウトソーシングを勧める機会がかなり多いです。
外注化する業務としては、日々の単純作業はもちろんですが、今や経営の上流工程においてもアウトソーシングの活用が普及しています。コンサルタントを活用すれば、自社だけでは不可能な様々な課題を解決できる可能性があります。
コンサルタントというと、大規模な企業だけのものというイメージがあるかもしれませんが、今や中小企業でもコンサルタントが不可欠となってきています。
具体的に何をしてくれるかという事例は、以下の記事も参考にしてみてください。

DX化への対応
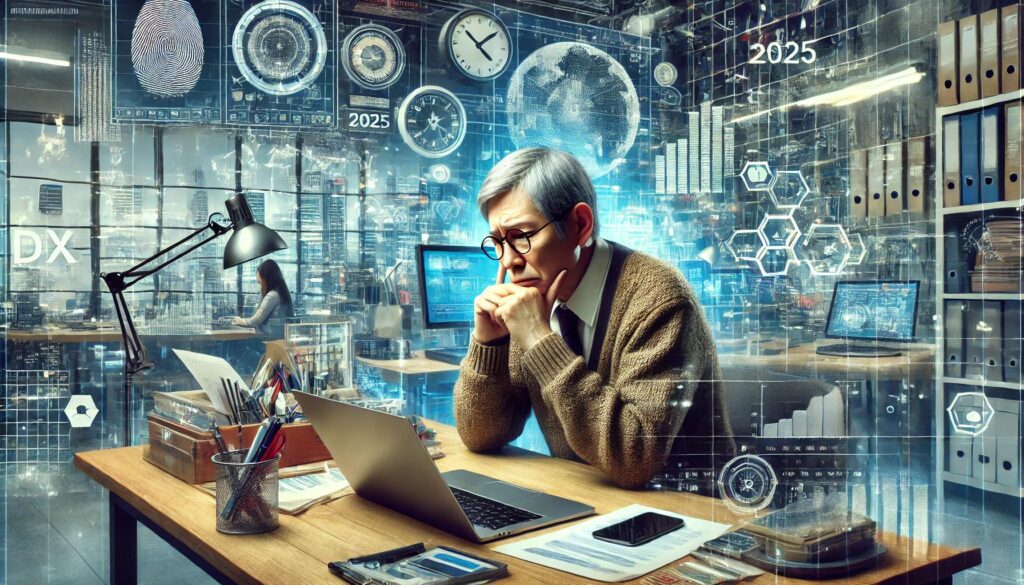
2025年の崖
懸念されていた「2025年の崖」に、日本の中小企業はいよいよ直面しています。
経済産業省の「DXレポート」では、2025年までにレガシーシステムの刷新や新たなデジタル技術の導入が進まない場合、日本の経済損失は最大12兆円に上ると試算されていました。
こういったDXに関する一連の問題が「2025年の崖」と呼ばれ、国としてもその対策を積極的に推進してきたものの、デジタル化が一向に進まない企業はまだまだあるのが実情です。
その一方で、近年の経営環境の変化はさらにそのスピードを増しているように思えます。
DX化への対応は重要な経営課題の一つであり、デジタル化の波を今まで何とか避けてきた中小企業も、いよいよこれからは逃れられなくなるでしょう。
IPA(情報処理推進機構)による「DX動向2025」では、アメリカやドイツと比べて日本企業のDXが大きく遅れをとっていることが数値で示されています。
また日本のDXの傾向として、業務効率化といった改善に偏っていることがわかりました。これに対して他国では、「新規ビジネス創出」「顧客満足度向上」など、企業がより成長していくための成果につなげています。
政府の支援策は「IT導入補助金」をはじめとして、これからも続くことが予想されます。
そういったサポートをうまく活用しつつ、より加速する外部環境変化に対応していくことは、中小企業にとって生き残りをかけた取り組みとなるでしょう。
DX化への取り組み
ではDX化が遅れている中小企業は、どのように取り組んでいくべきでしょうか。
大前提として重要になるのは、DXを単なる技術導入ではなく、経営戦略の一環として捉えることです。
まずは自社のビジネスモデルを再評価し、デジタル技術を活用してどのような価値を提供できるかを明確にしましょう。そしてDX推進計画を策定し、一度にすべてを変革するのではなく、優先順位をつけて段階的に取り組むのがおすすめです。
DX化にあたって、社内でデジタル人材を育成することも重要ではありますが、特に初期では外部専門家を活用して進めることが成功の秘訣です。
中小企業庁の調査によると、DX推進の最大の障壁は人材不足であると指摘されています。
「2025年の崖」問題として予測されていたとおり、古いシステムが「誰も触れない」という状態に陥ったり、社内にセキュリティ面のノウハウが無いことで危険にさらされるケースも増えていくでしょう。
DX人材の課題に対しては、社員でリスキリングを進める、デジタル人材の中途採用を進める、コンサルタントを活用するなど、複合的なアプローチで対応していかなくてはいけません。

DX化の成功事例
ある機械部品を製造するメーカーでは、工場のIoT化によって生産効率を30%向上させただけでなく、大手企業との取引を新たに獲得したという事例もあります。
また別の小売業では、DX化のための現実的な計画を策定し、第一歩として在庫管理システムのクラウド化から着手。次に顧客管理システムの導入、最終的にはAIを活用した需要予測システムの構築へと、段階的にDXを進めることにより、3年間で売上を2倍に伸ばすことに成功しています。
DX化が重要になるのは、効率化だけでなく販売という面でも同様です。
コロナ禍をきっかけとして、これまでネット通販を使わなかった消費者の間にも、ECサイトが急速に普及しました。こういった流れを見逃さず、いち早くECサイトを導入した中小企業の中には、売上を大幅に伸ばした事例が多数報告されています。
ある地方の食品製造業では、ECサイトの開設とSNSマーケティングの活用により、わずか1年で売上を50%増加させることに成功したそうです。逆に従来の店舗型ビジネスモデルだけでは、競争力を維持することが困難になるケースもあるようです。
ECサイトを活用した販売方法に興味があれば、こちらの記事も併せてご覧ください。
高齢化する中小企業経営者

経営者の高齢化がもたらす問題
帝国データバンクの調査によると、2024年における日本の社長の平均年齢は60.7歳と、過去最高を更新したようです。
さらに憂慮すべきなのは、これら高齢経営者の半数以上が、事業の後継者を決めていないという事実。
事業承継が円滑に行われなければ、企業における技術・ノウハウの喪失、雇用の減少、地域経済の衰退などが頻発し、日本全体の産業構造に重大な影響を与える可能性もあります。
ある調査によると、事業承継に失敗した企業の約60%が5年以内に廃業、または倒産に至ったという報告もあります。このまま優良な中小企業が減ってしまえば、サプライチェーン全体や地域経済に波及効果をもたらすことになるでしょう。
一方で2025年11月の東京商工リサーチの記事によると、柔軟な思考を持った年齢の若い社長の企業ほど、業績を伸ばしている傾向が強いようです。
もし経営者様が高齢であるなら、2026年こそ事業承継計画を本格的に検討しなくてはいけません。
事業承継に向けての取り組み
では事業承継という難しい問題に、中小企業はどのように取り組んでいくべきでしょうか。
まず重要なのは、事業承継を単なる経営者の交代として捉えるのではなく、企業の持続的成長のための機会としてポジティブに考えることです。そして社内で協力体制を敷き、事業承継に向けての詳細な計画を作成することが必要となります。
事業承継は5年から10年という期間を要する場合もあるため、早期の計画立案に着手すれば選択肢が広がるというメリットがあります。
なお事業承継には多額の資金が必要となる場合もあるため、財務面の考慮も忘れてはいけません。自社株式の評価額、相続税対策などを含めて、綿密に財務計画を練っておきましょう。
また後継者の選定は、家族内だけを候補とするのでなく、従業員や外部人材からの登用も含めて検討する必要があります。中小企業庁の調査によると、従業員や外部人材への承継を選択した企業の方が、経営革新や新事業展開に積極的な傾向が見られるようです。
ある製造業の中小企業では、経営者が50代の時点から後継者の育成を開始し、5年かけて長期的に経営のノウハウを伝授する計画を立てました。その結果、スムーズな事業承継を実現することができ、その後3年間で売上を20%増加させることに成功しています。
またデジタル技術を活用し、経営者の暗黙知を形式知化することで、企業全体のスキル向上を実現した企業もあります。
こういった取り組みを適切に実施すれば、事業承継を単なるリスク回避ではなく、企業のさらなる発展の機会として活用することもできるのです。
事業承継支援の活用
どうしても後継者が見つからないという場合は、M&Aも一つの選択肢として考えましょう。
跡継ぎがいないことがきっかけで同業他社と合併し、規模の経済を活かして競争力を高めたという成功事例も多く存在します。
とはいえこういった取り組みは、個々の企業の努力だけでは解決するには不十分なことも多いです。そこでぜひ検討したいのが、政府や地方自治体、金融機関、商工会議所などが提供する事業承継支援プログラム。
事業承継・引継ぎ支援センターはその代表的な例であり、専門家による無料相談や、買収を希望する企業とのマッチングサービスなどを提供しています。こういった公的支援を利用した企業の中には、後継者問題を解決し、新たなスタートを切ることに成功した事例も多数報告されています。
以上のような事業承継への取り組みは、企業の持続的発展のみならず、日本の産業競争力の維持向上、地域経済の活性化にもつながる重要な鍵となるでしょう。
さらに事業承継・M&A補助金といった支援制度も、使えるようであれば積極的に検討してみてください。
賃上げに対する圧力

中小企業に迫る賃上げの波
日本の中小企業は、これまで以上の賃上げ圧力に直面すると予測されています。
その背景には、最低賃金の引き上げや労働市場の変化、物価上昇による生活費の増加などの経済的要因が存在します。政府も中小企業の賃上げに尽力しており、補助金交付の要件として、賃上げを必須としているケースも増えています。
従業員の生活水準を向上させることは、社会全体の消費を促進し、国家の経済成長にも寄与します。そういった狙いからも、企業への賃上げ圧力は高まっていくでしょう。
こういった状況が進むにつれて、人材の奪い合いもよりいっそう激化していくはずです。
終身雇用が崩壊した現在、従業員は簡単に会社を辞め、より良い待遇を求めて転職を繰り返すことに躊躇しません。そんな状況の中では、事業の発展にとどまらず現状維持するだけでも、人材確保を目的とした賃上げが欠かせなくなってきます。
それにしても近年の人件費高騰は凄まじく、実際に経営者様のお話を聞いていると、もはやどうしようも無い状況に追い込まれている企業もあります。
2026年はこの状況に耐えられず、「体力の限界」を迎える中小企業が続出することが懸念されます。
賃上げのリスク
賃上げは従業員が喜ぶ一方で、多くの中小企業に絶大なリスクをもたらします。
まず直接的な問題として、給与の引き上げに伴う人件費増加が挙げられます。当然ながら社会保険料や退職金の負担も増加します。
人材確保のために競合他社との賃金競争が激化すれば、収益率が低下する可能性もあるでしょう。さらに賃金コストを商品価格に転嫁しようとすれば、価格競争力を失ってしまい、顧客離れを招くというリスクがあるはずです。
簡単に従業員を解雇できない日本の場合、無計画な賃上げが仇となって、資金繰りの悪化により経営基盤を揺るがす可能性も否定できません。加えて2026年に法案提出予定の労働基準法改正が火に油を注ぎ、中小企業をさらに苦しめるシナリオも想定されます。
2024年度の中小企業白書では、中小企業の実に36.9%が防衛的賃上げを強いられていることが記載されています。
これは業績改善したわけではないものの、従業員確保のために仕方なく賃上げを行う企業が多いことを指しており、実際に私たちにも人件費に関する相談は多く寄せられています。
2026年もこの動向は収束する気配が無く、最低賃金がさらに上昇していくのもほぼ確実視されており、防衛的賃上げを強いられる中小企業は非常に多いことが予測されます。
雇用というリスクを軽減するため、賃上げにおいても戦略的なアプローチが必要となってきます。

賃上げを成長の機会に変える
十分な利益が出ておらず、賃上げへの対応が容易ではない事業者様も多いはずです。
しかし賃上げを単なる負担として捉えるのではなく、成長の機会として活用しようというマインドこそ、2026年の中小企業を救う鍵となるかもしれません。
賃金の引き上げは従業員のモチベーションを向上させ、それが生産性やサービス品質の向上につながっていく可能性があります。競合他社よりも良い報酬を提示し、その分だけ業務の成果を求めるという方針も、優秀な人材を確保するための選択肢の一つです。
いずれにしても、ここ数年で企業と従業員の関係性は大きく変化してきています。賃上げを機会として、従業員にスキルアップを促すと共に、会社に貢献しようと意欲を持ってもらえるような工夫が必要です。
このように中小企業が直面している賃上げ圧力は、雇用に対する考え方の転換にもつながるのではないでしょうか。

さらなるコストの上昇
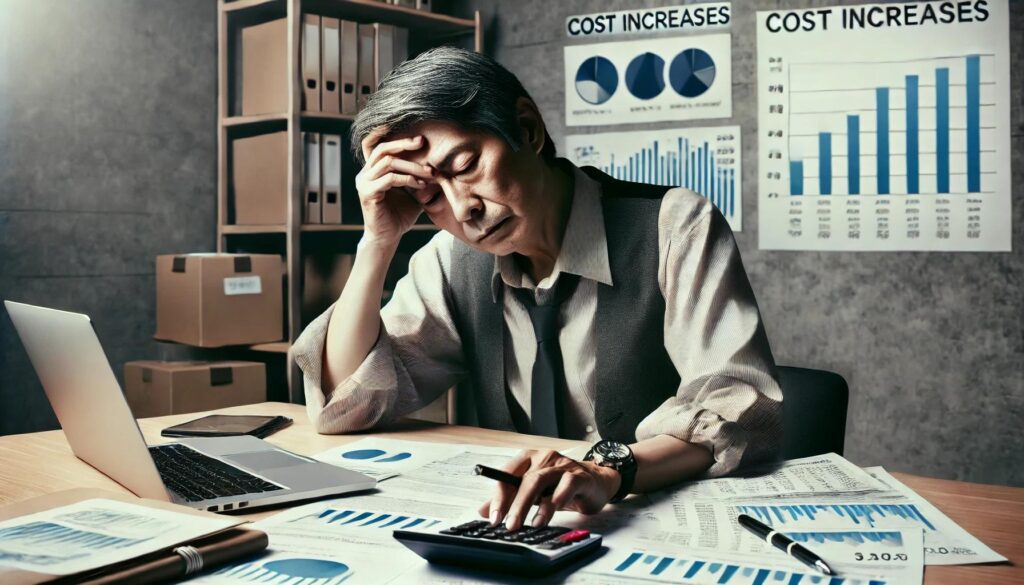
原材料やエネルギー価格の高騰が続く
日本銀行の企業物価指数を確認すると、2022年以降の原材料価格は年平均5%以上上昇しています。
近年の急激なコスト増は、既に多くの中小企業にとって大きな負担となっているはずです。しかしながら残念なことに、コストはまだまだ上昇する可能性があります。
具体的に増加が見込まれるコストとしては、前述の賃上げによる人件費に加えて、エネルギーや原材料価格が考えられます。
同じく日本銀行による見込みによると、2026年は上昇幅が緩やかになると予測されているのは、せめてもの救いと言えるかもしれません。
ある中小企業では、2022年から2024年にかけて、年間の電力コストが30%増加したようなケースもあります。エネルギーコストの上昇は、生産コストの増加という部分に直結し、企業の利益率を大きく圧迫しています。
またある電子部品メーカーでは、主要部品の調達コストが2年間で50%以上上昇し、利益率を大きく圧迫していることに悩みを抱えています。こういった事例は業種を問わず、程度の差はあれど様々な分野で発生しているものと考えられます。
コスト上昇の要因
昨今のコスト増は、グローバルな経済の変化、国内の構造的な問題、そして予期せぬ外的要因など、複合的な要因によって引き起こされています。
地政学的リスクの高まりによるサプライチェーンの混乱は、一服したとはいえまだまだ続くでしょう。
グローバルなサプライチェーンの問題は、中小企業の調達コストを押し上げている主要因の一つとして広く認識されましたが、これからも世界では何が起こるかわかりません。
原材料が落ち着いたとしても、人件費が確実に上がっていく状況では、結果的に仕入価格の上昇につながっていくはずです。
加えて環境規制の強化も、コスト増の要因となっています。2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、企業には環境負荷の低減が求められており、これに伴う設備投資や運用コストの増加が避けられない状況です。
これらは一時的な現象ではなく、経済環境の構造的な変化を反映しており、中小企業にとっても避けて通れない課題となっています。

コスト増加への対策
中小企業がコスト増の脅威に立ち向かうためには、やはりデジタル技術を活用した業務効率化が効果的です。
具体的な例としては、RPAをはじめとした自動化システムの導入、AIを活用した需要予測と在庫最適化、IoTを用いたエネルギー管理などが挙げられます。
ある中小企業の製造業の事例では、工場にIoTセンサーを導入し、生産設備のリアルタイムモニタリングを実施することで、エネルギー消費を20%削減することに成功したそうです。
この企業では、各設備のエネルギー消費パターンを分析し、AI技術を用いて最適な稼働スケジュールを自動で作成しています。その結果、ピーク時の電力使用量を抑制し、電力料金の大幅な削減を実現しました。
別の運送業を営む中小企業では、配送伝票の処理や請求書発行などの定型業務にRPAを導入し、これらの業務にかかる時間を70%も削減することに成功しました。こういった取り組みにより、業務効率が大幅に向上し、間接コストの削減につながっています。
以上のような事例は、単にコスト削減というだけでなく、生産性向上による人手不足対策にもつながっており、一石二鳥の効果を生んでいると言えます。
いずれにしてもデジタル技術の活用は、2026年に中小企業が立ち向かう経営改善に、大きな可能性を秘めています。
度重なるコスト増で資金繰りに不安がある方は、こちらの記事も読んでみてください。
2026年の経営課題を乗り越えるために
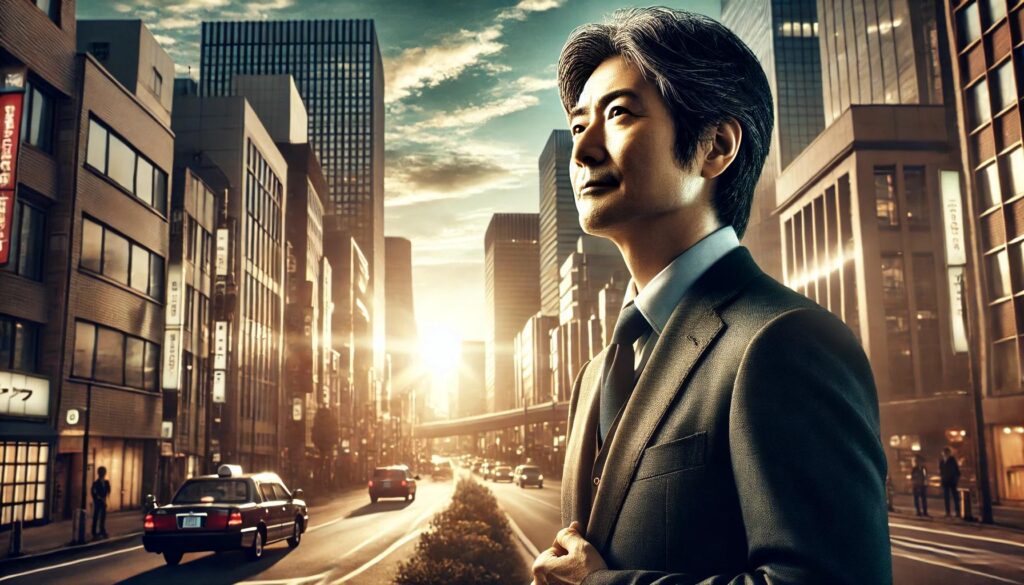
これまで見てきたように、2026年も引き続き多くの経営課題が待ち受けています。
どれも一筋縄ではいかないものばかりかもしれません。しかし事業のさらなる発展のため、あるいは最低限の現状維持のため、できるだけ早期に対策を進めることが求められています。
もし自社での解決が難しい場合は、外部の専門家の力を借りるのが有効な手段です。
今や中小企業においても、専門家のサポートを受けることはごく普通となっており、その道のプロに課題を解決してもらうのは、極めて合理的な経営判断と言えるでしょう。
エクト経営コンサルティングは、様々な分野のプロフェッショナルが集まる、中小企業専門の経営相談所。
そして全員が経済産業省登録の中小企業診断士であり、貴社のお悩みに合わせて最適な専門家からのサポートを、月5万円~という圧倒的にリーズナブルな料金でご提供しています。
メリットは他にもいろいろありますが、中小企業にとって本当に価値あるコンサルティングを追求して誕生した、画期的なサービスであると自負しています。
経営を改善したいなら、まずは最初の一歩を踏み出すのが大切。
もし自社だけで取り組むのに限界を感じており、コンサルタントに解決を依頼したい課題があれば、以下のボタンから詳細をご確認ください。
2026年を飛躍の年にするため、まずは無料相談から経営改善をスタートしましょう。


お問い合わせはこちら
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

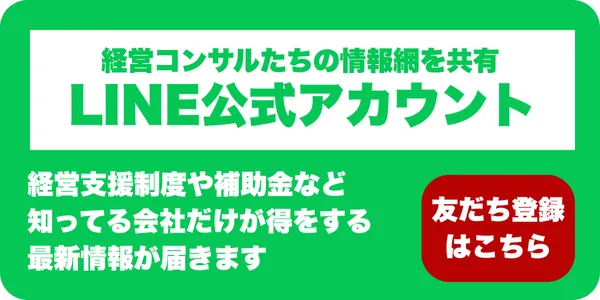





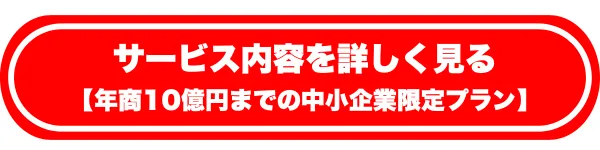










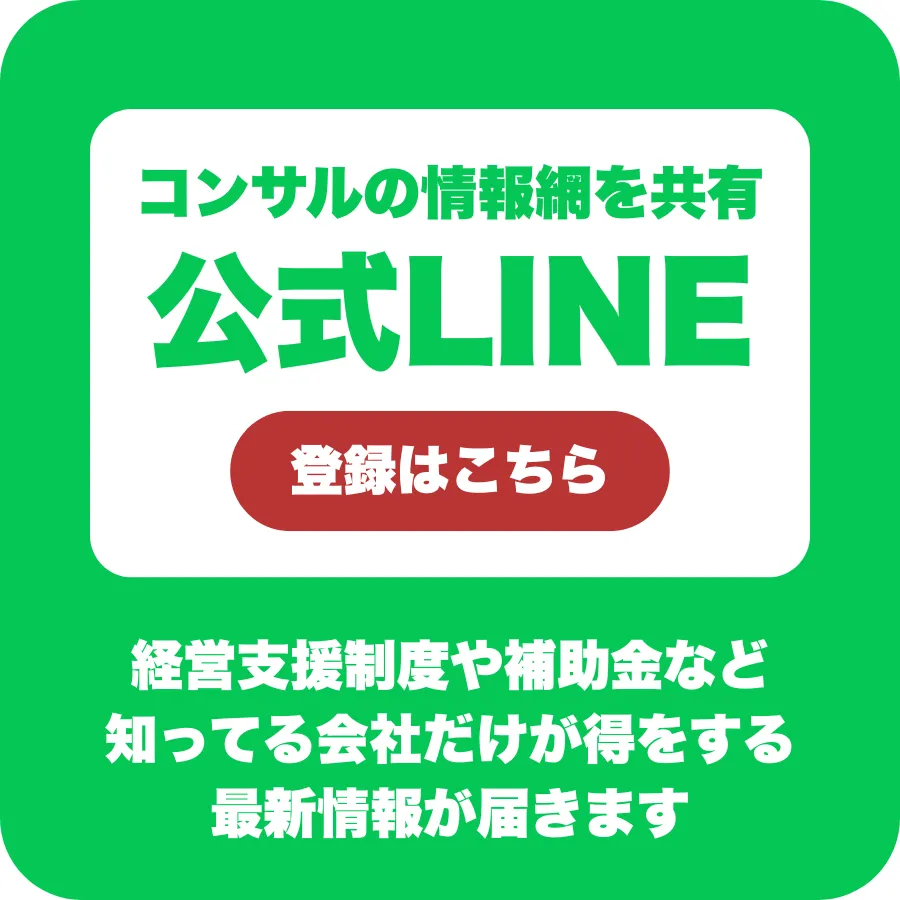











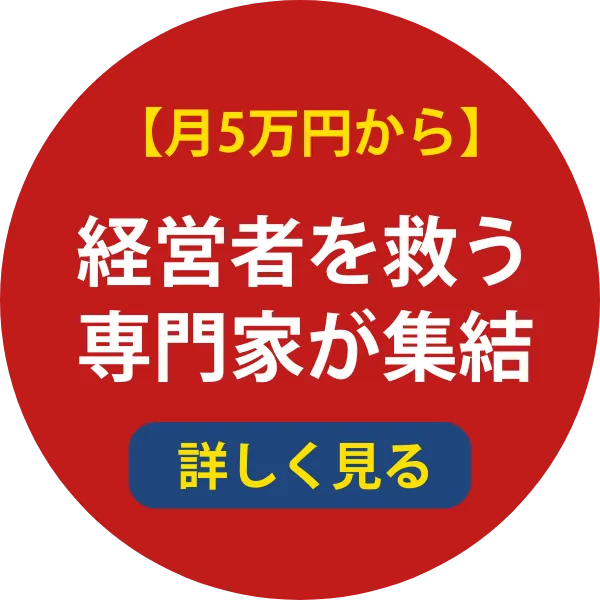
この記事へのコメントはありません。